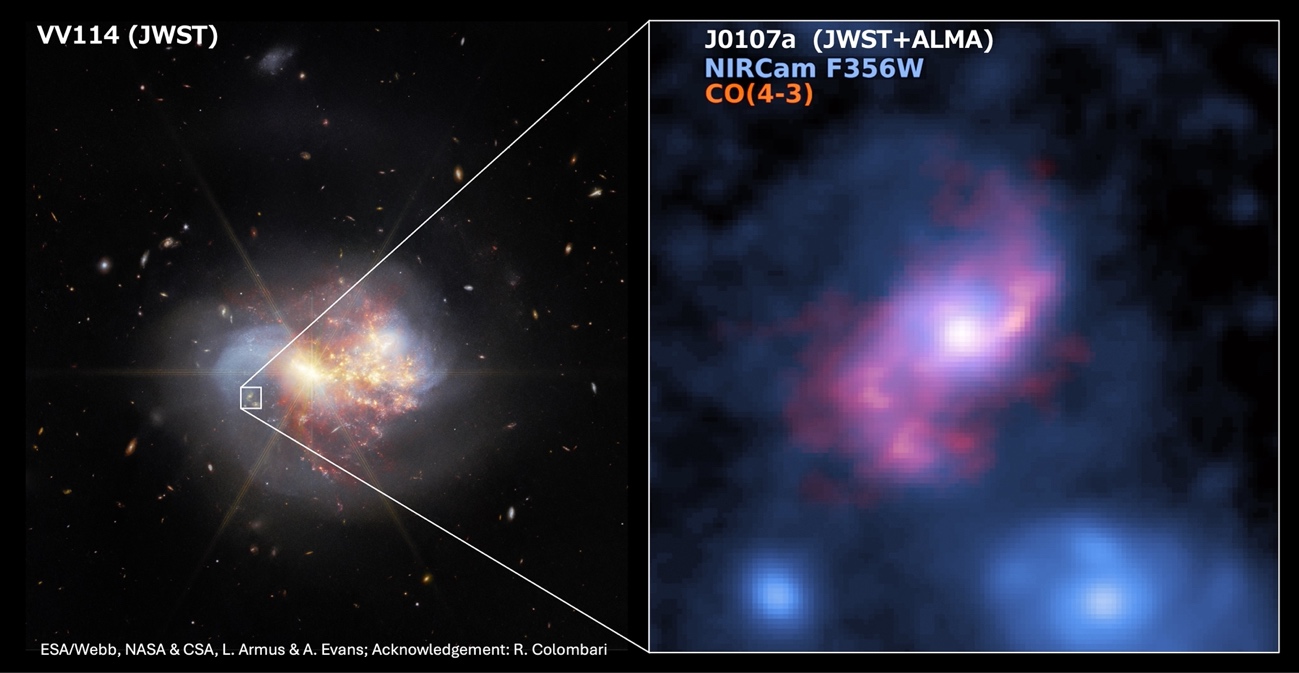 2025年5月22日
プレスリリース
2025年5月22日
プレスリリース
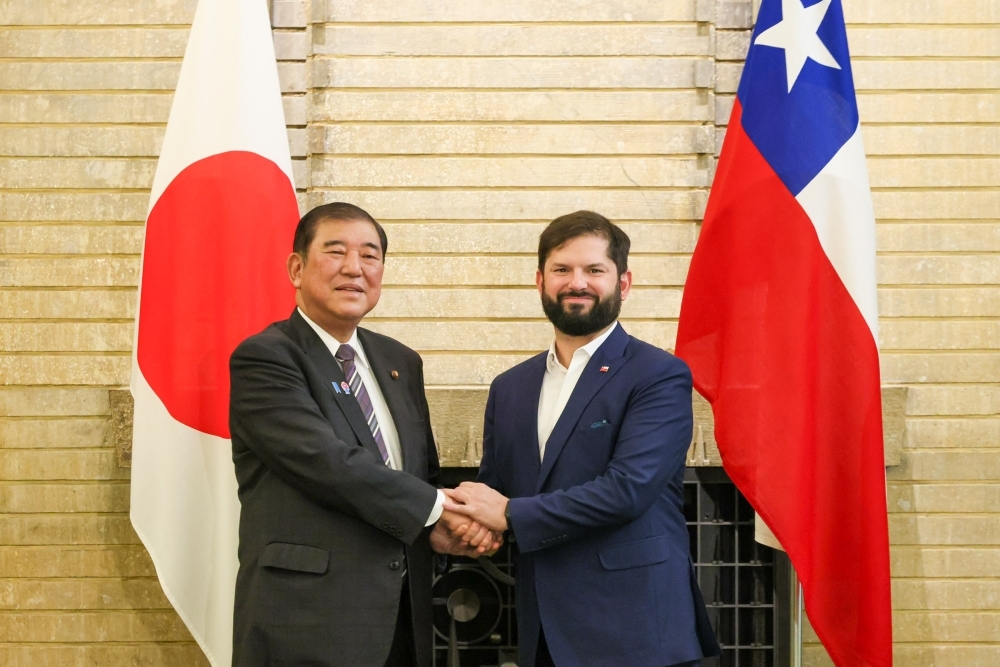 2025年5月13日
ニュース
2025年5月13日
ニュース
 2025年3月24日
ニュース
2025年3月24日
ニュース
 2025年2月12日
ニュース
2025年2月12日
ニュース
 2025年1月16日
ニュース
2025年1月16日
ニュース
 2025年1月7日
ニュース
2025年1月7日
ニュース
 2024年10月19日
イベント
2024年10月19日
イベント
 2024年9月30日
ニュース
2024年9月30日
ニュース
 2024年5月2日
ニュース
2024年5月2日
ニュース
 2023年10月28日
イベント
2023年10月28日
イベント
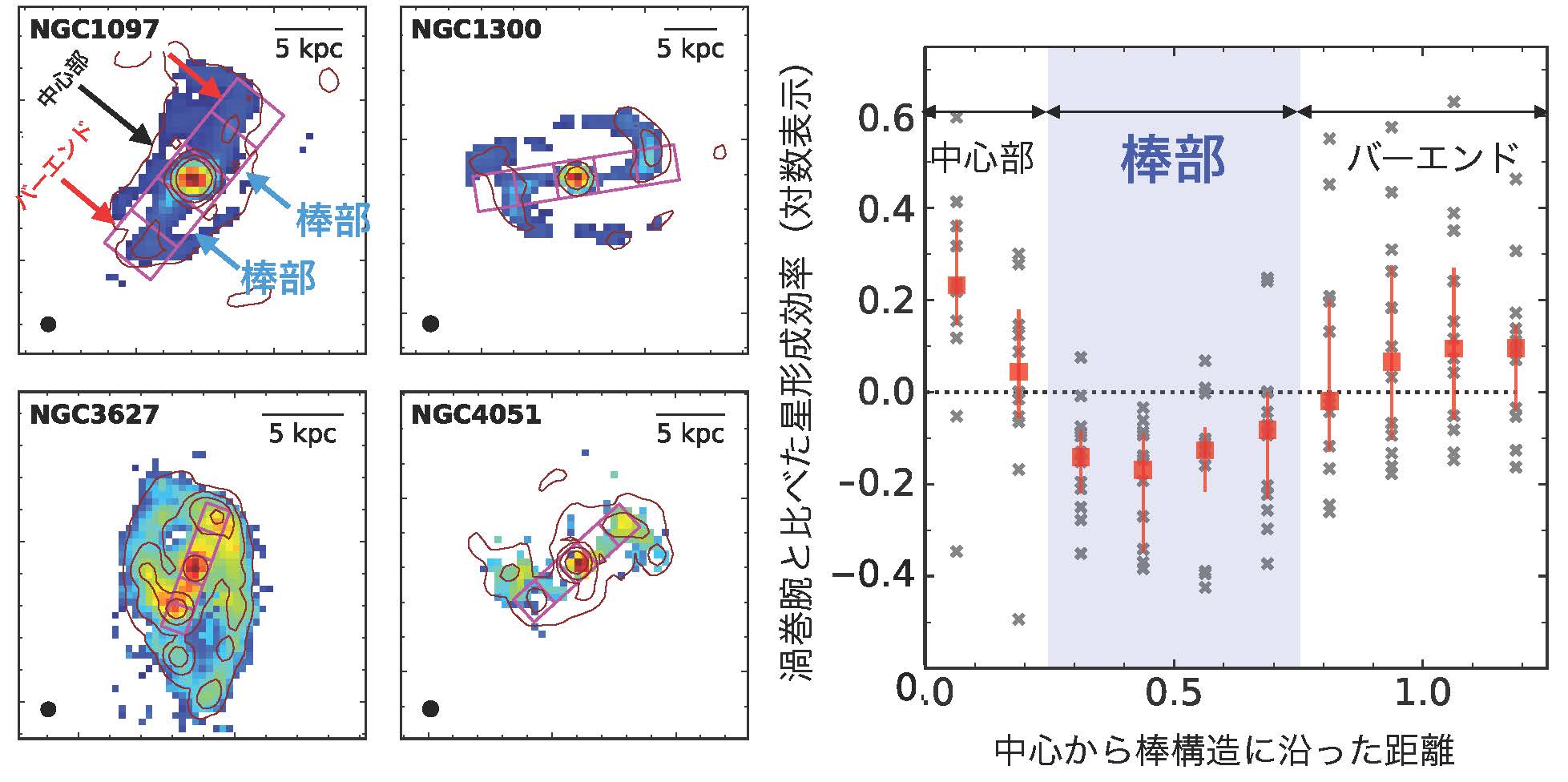 2023年6月30日
ニュース
2023年6月30日
ニュース
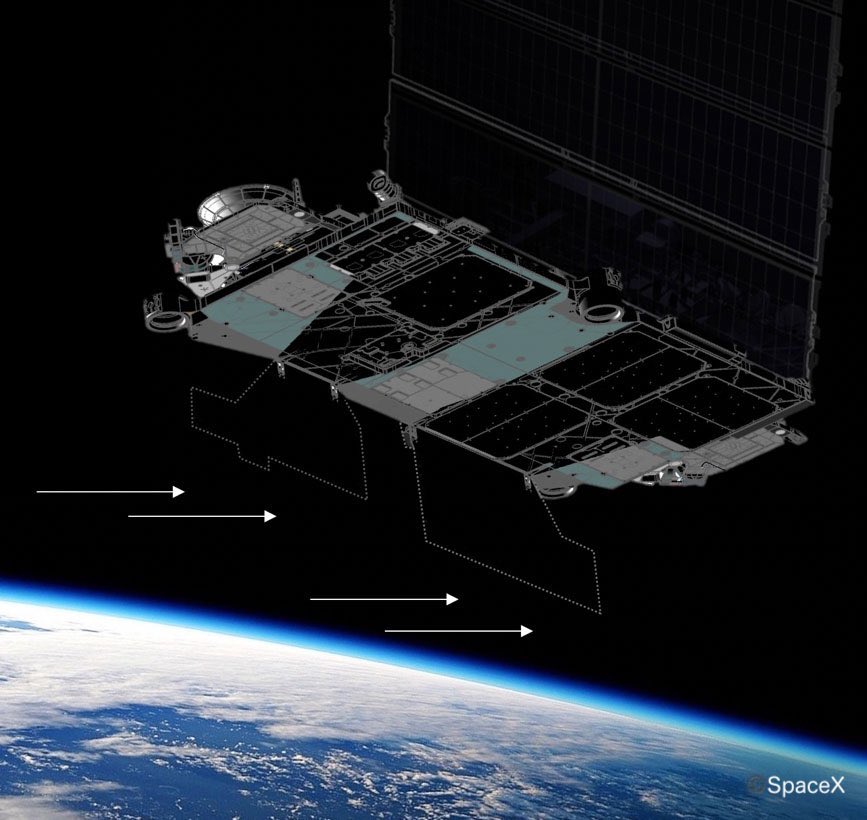 2023年4月24日
ニュース
2023年4月24日
ニュース
 2023年4月7日
プレスリリース
2023年4月7日
プレスリリース
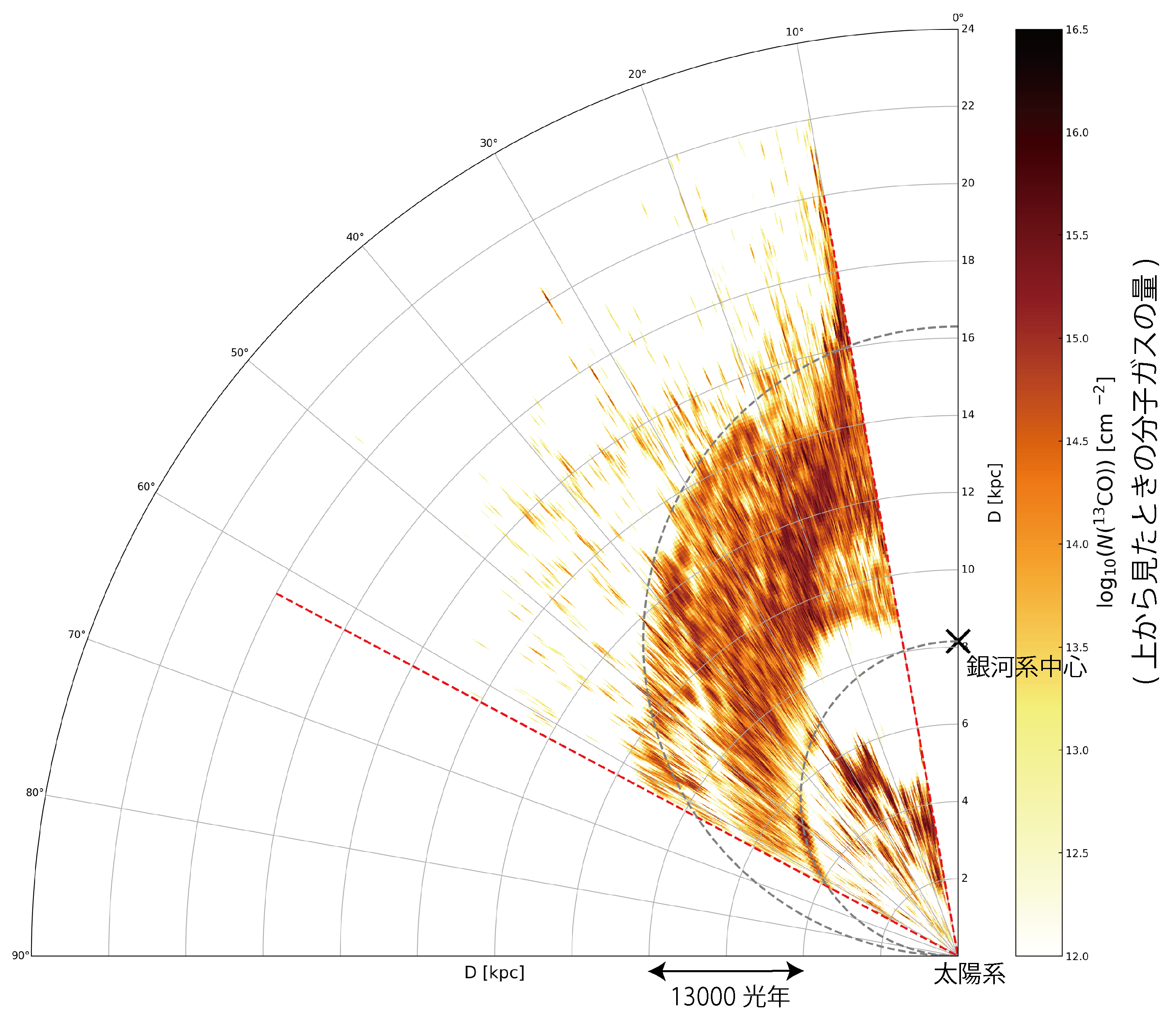 2023年1月30日
プレスリリース
2023年1月30日
プレスリリース
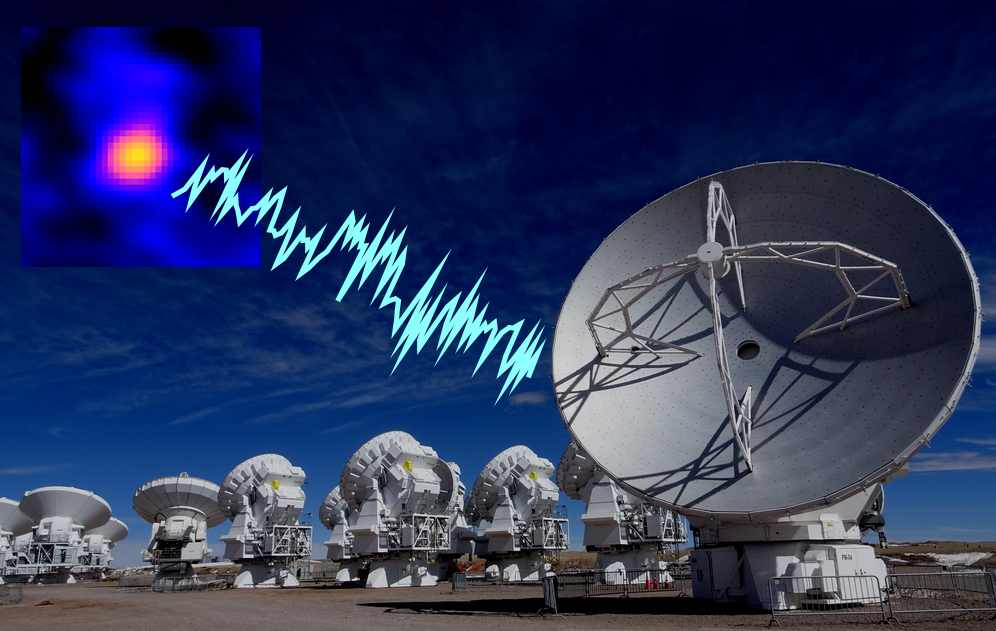 2022年11月28日
プレスリリース
2022年11月28日
プレスリリース
 2022年10月29日
イベント
2022年10月29日
イベント
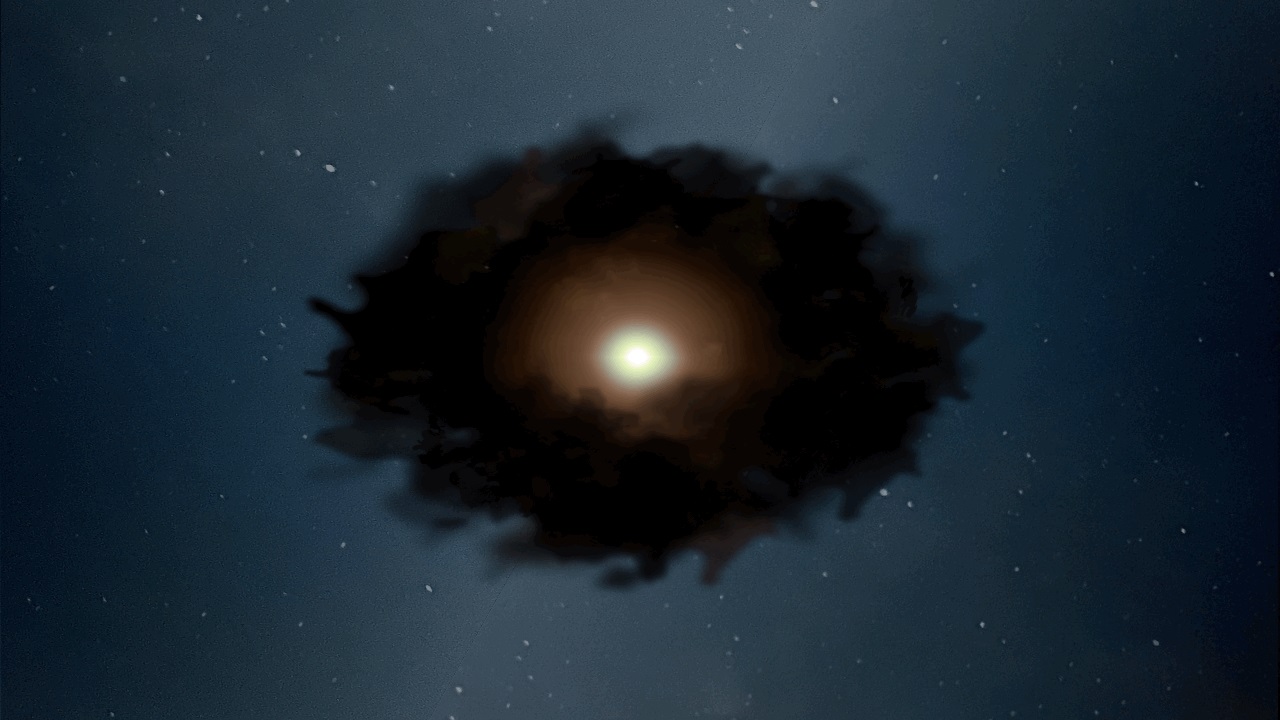 2022年9月16日
プレスリリース
2022年9月16日
プレスリリース
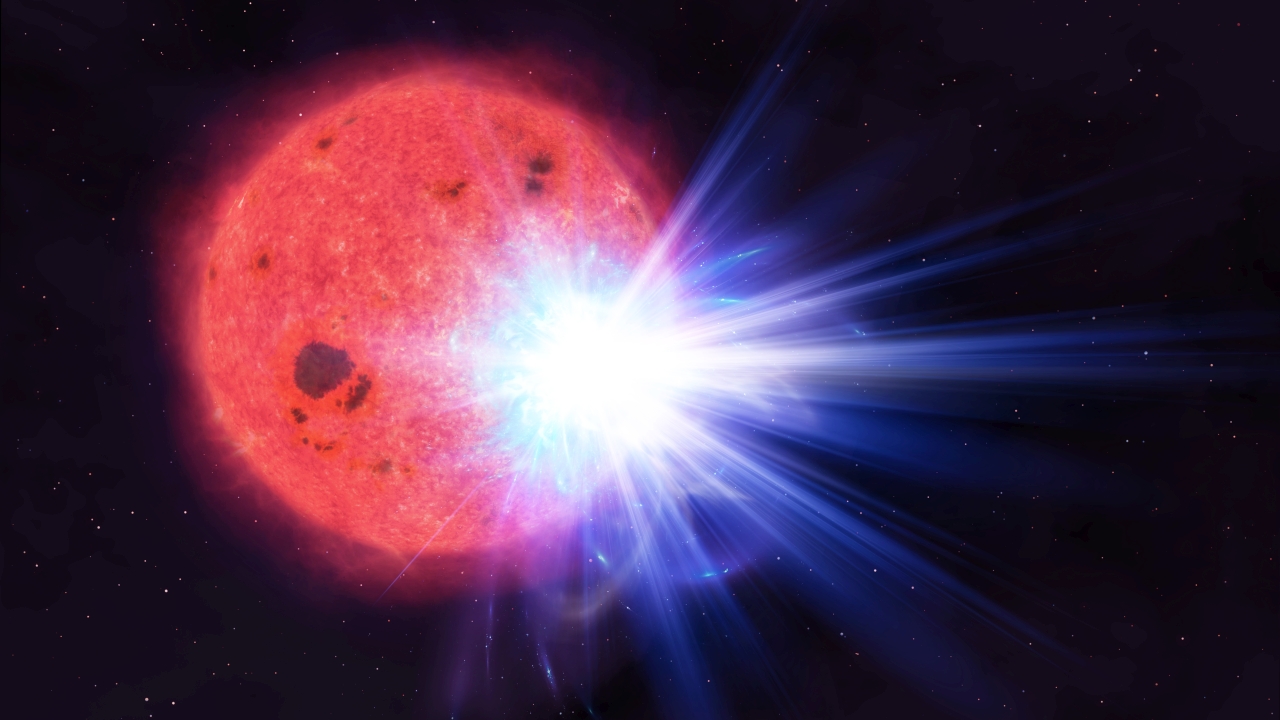 2022年8月9日
プレスリリース
2022年8月9日
プレスリリース
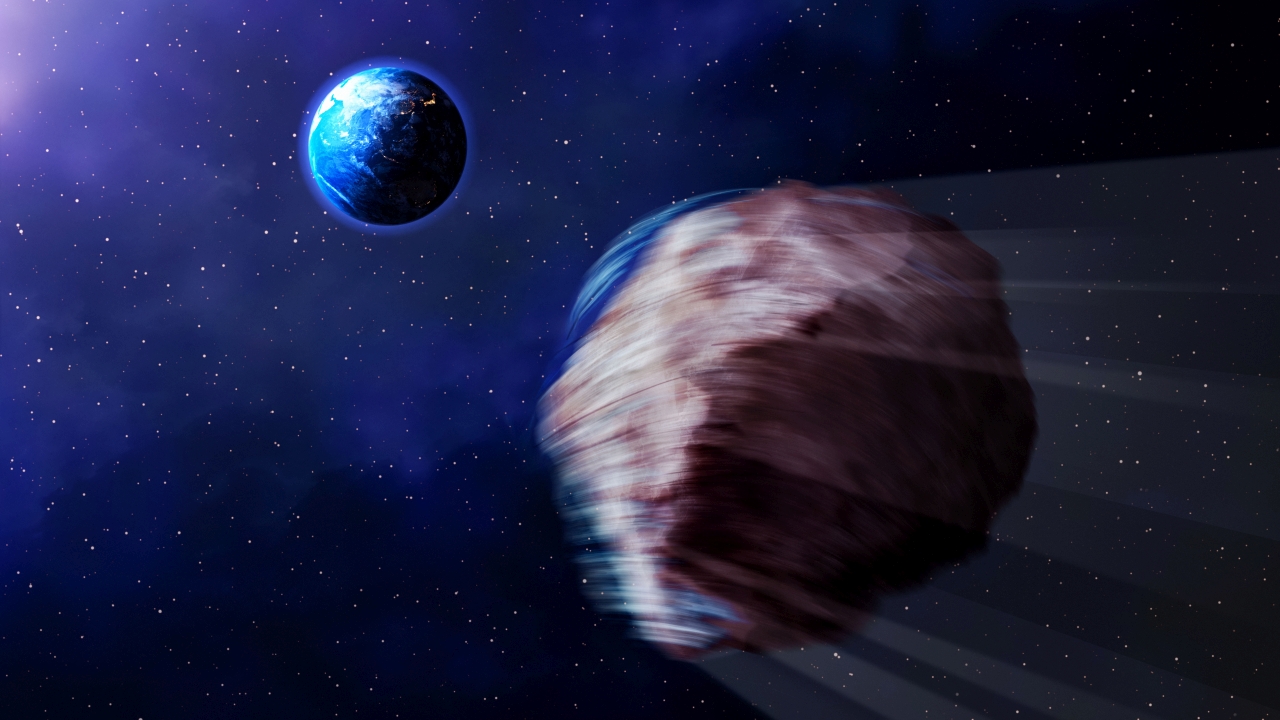 2022年7月13日
プレスリリース
2022年7月13日
プレスリリース
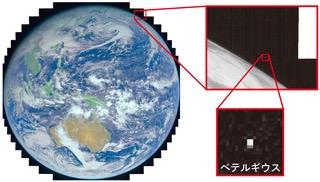 2022年5月31日
ニュース
2022年5月31日
ニュース
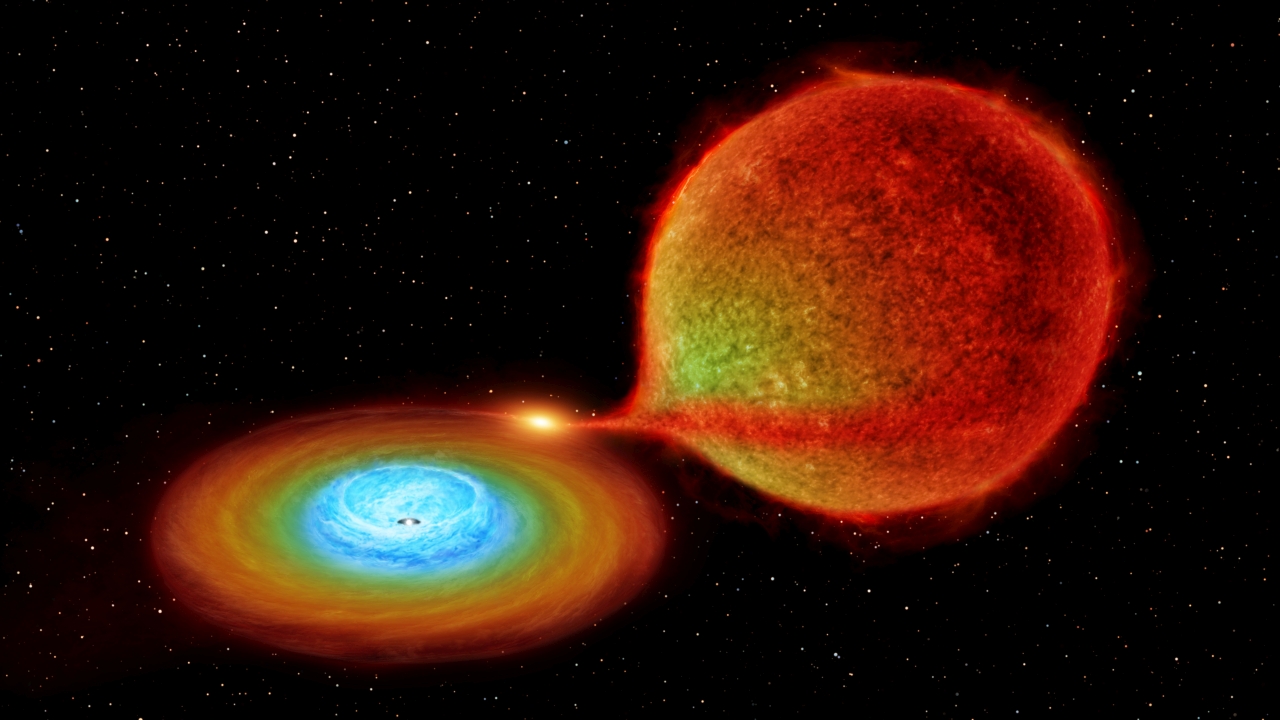 2022年5月18日
プレスリリース
2022年5月18日
プレスリリース
 2022年4月7日
ニュース
2022年4月7日
ニュース