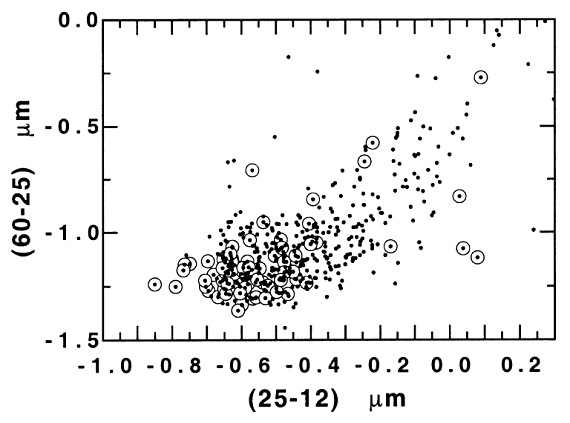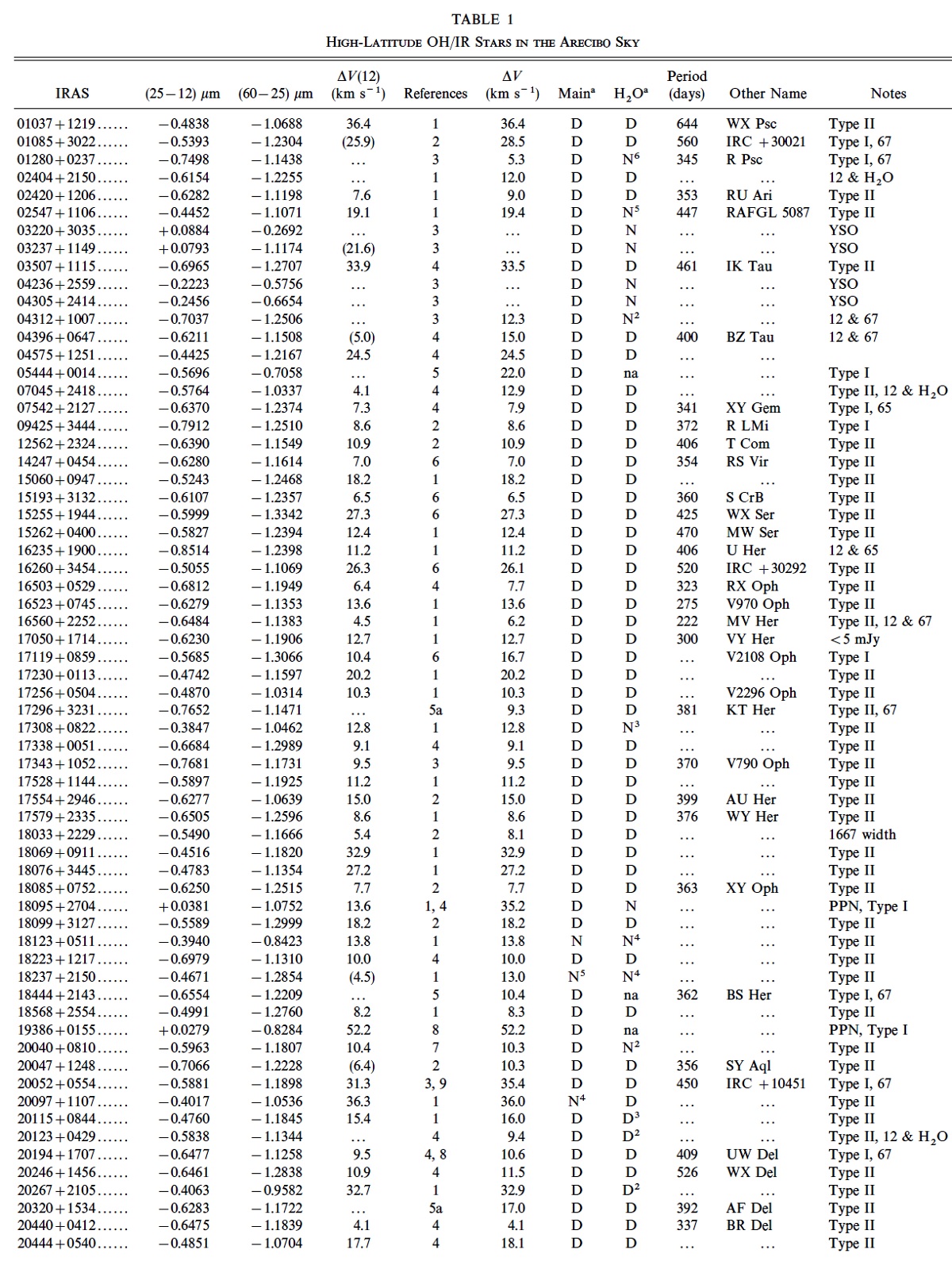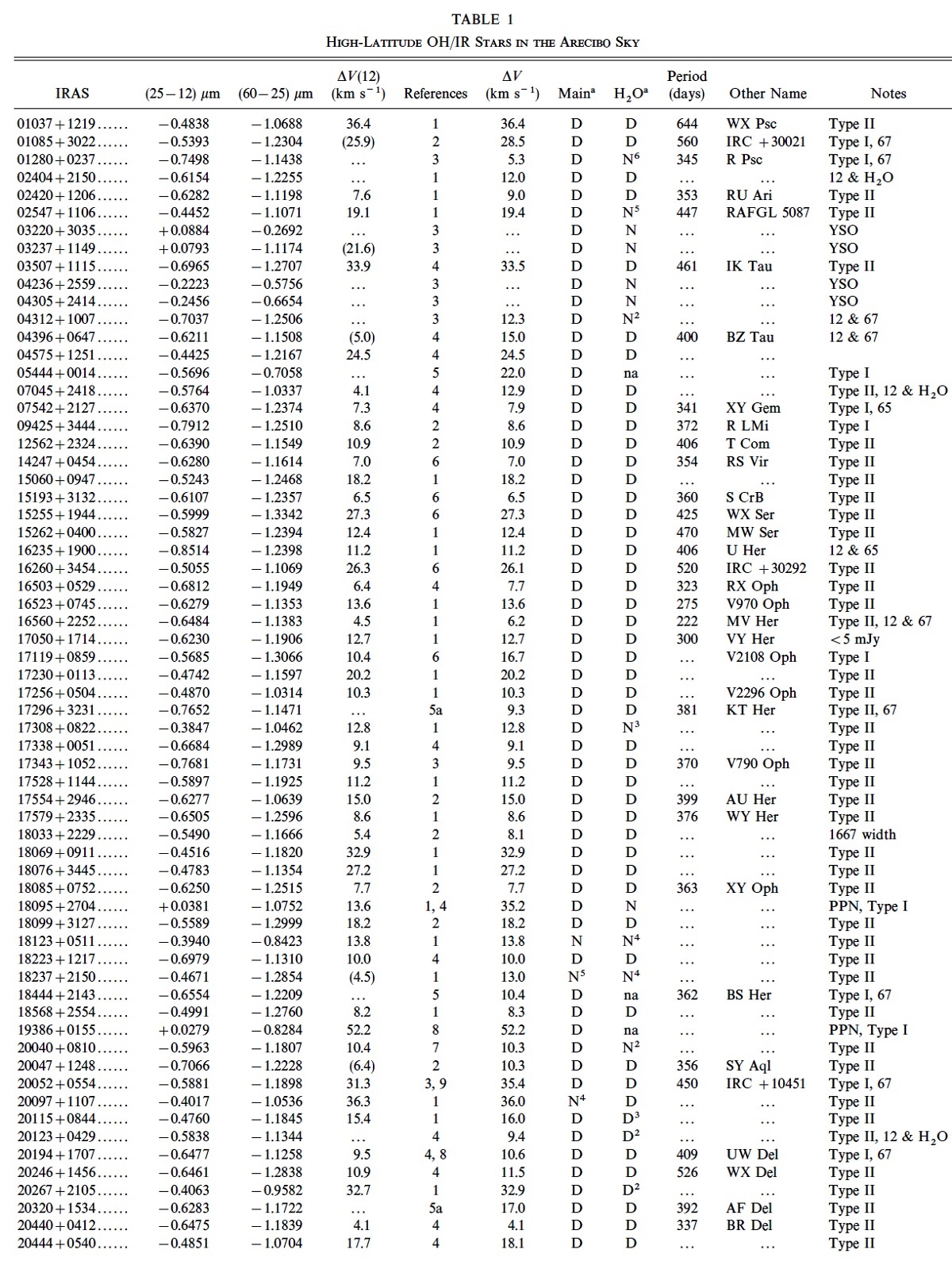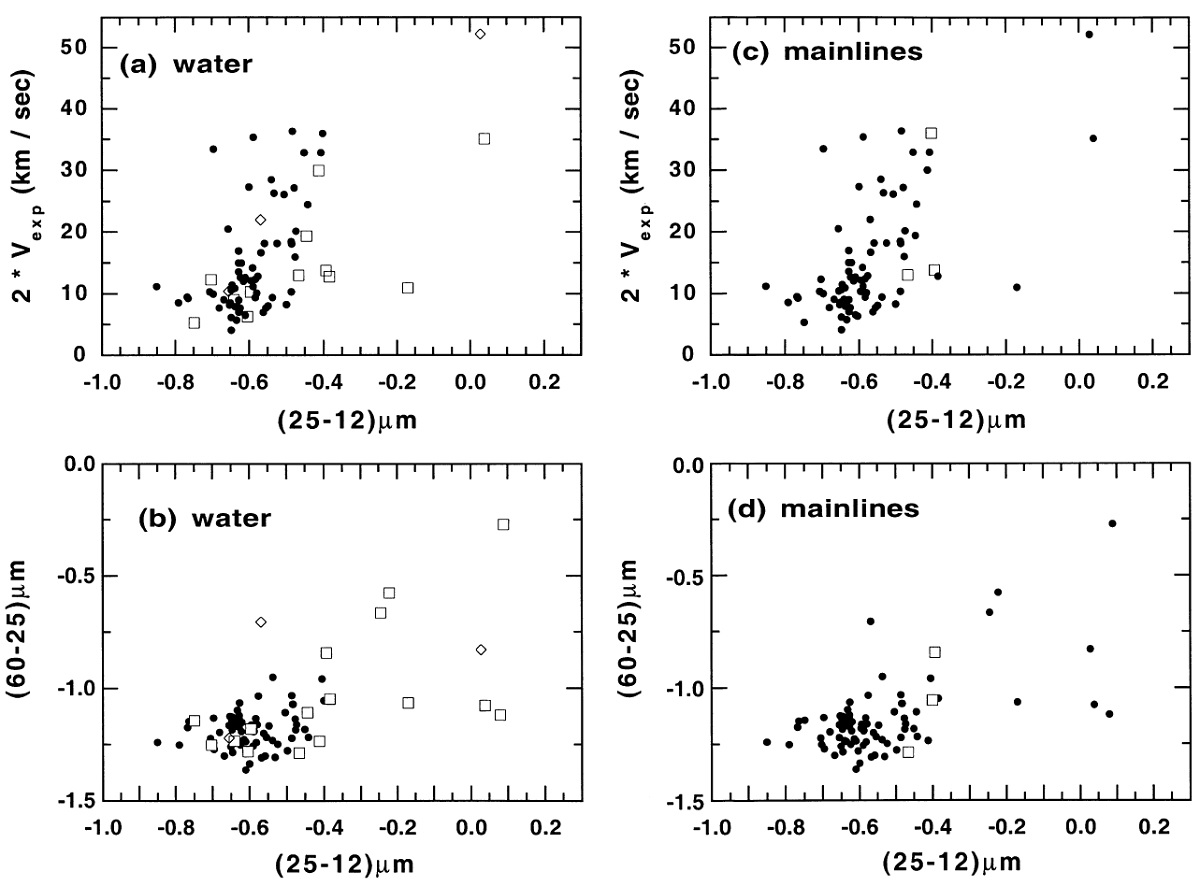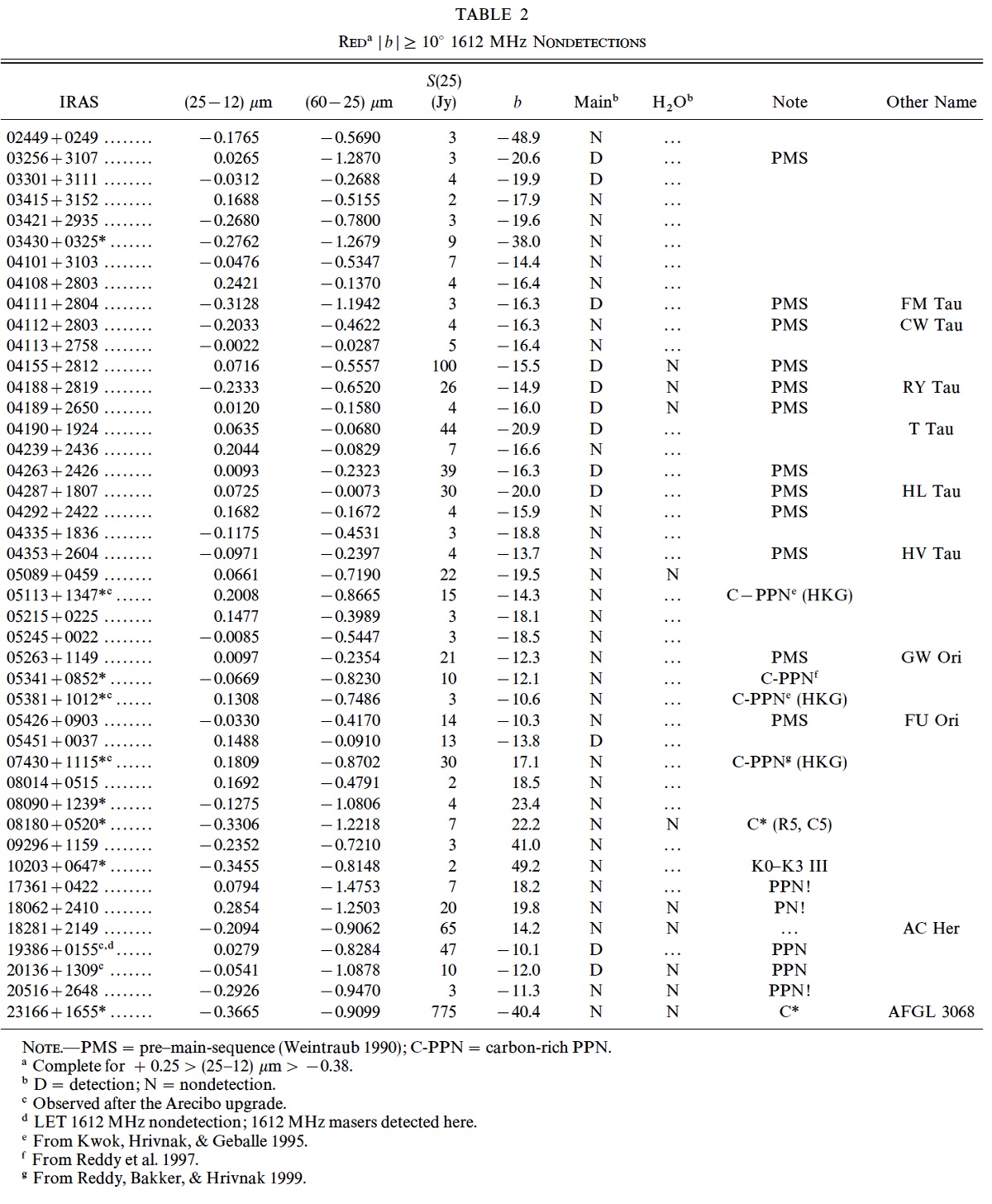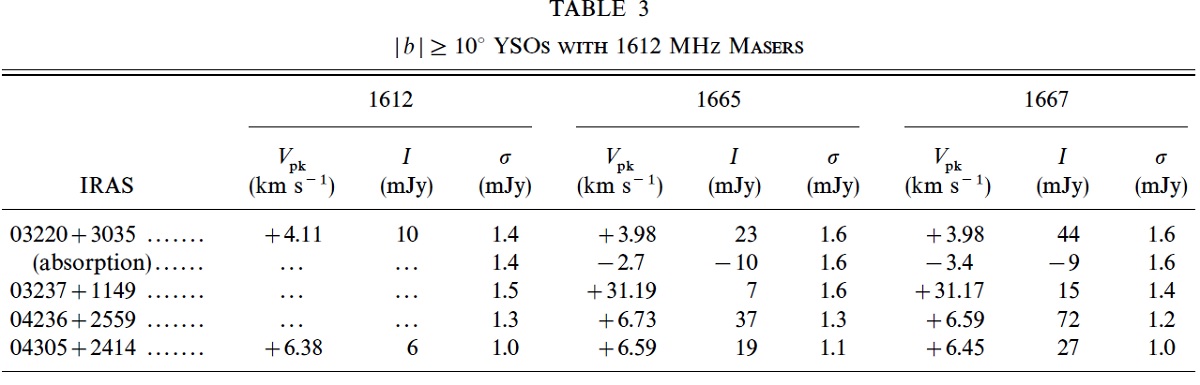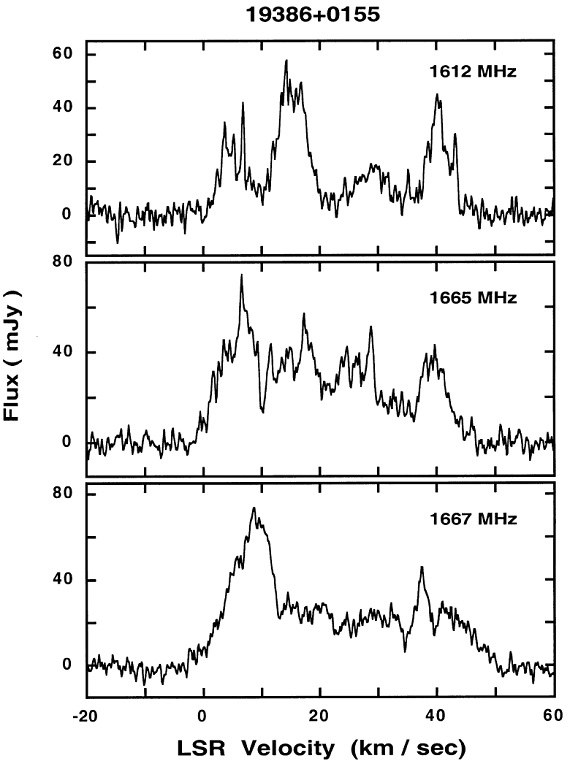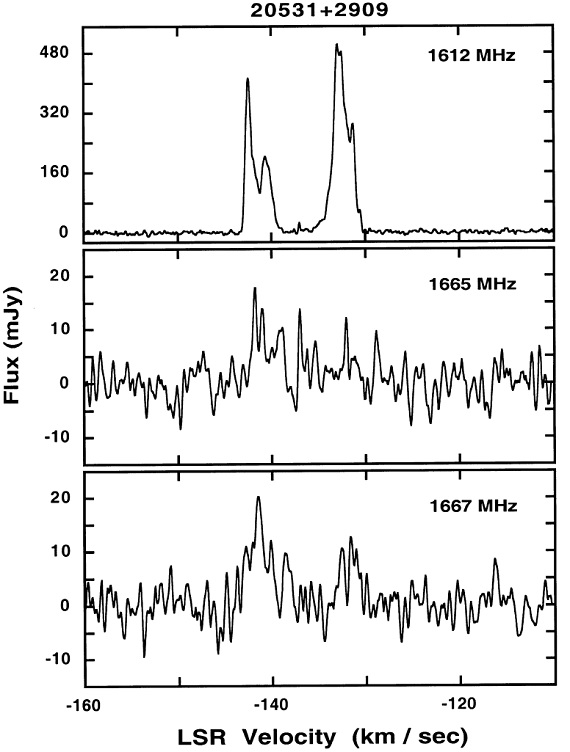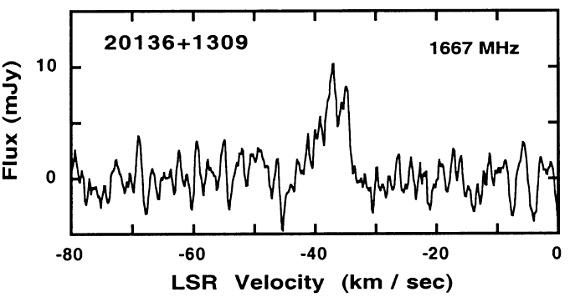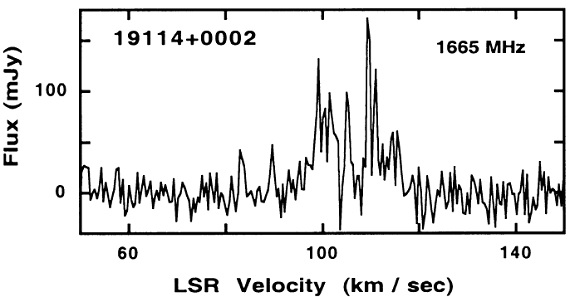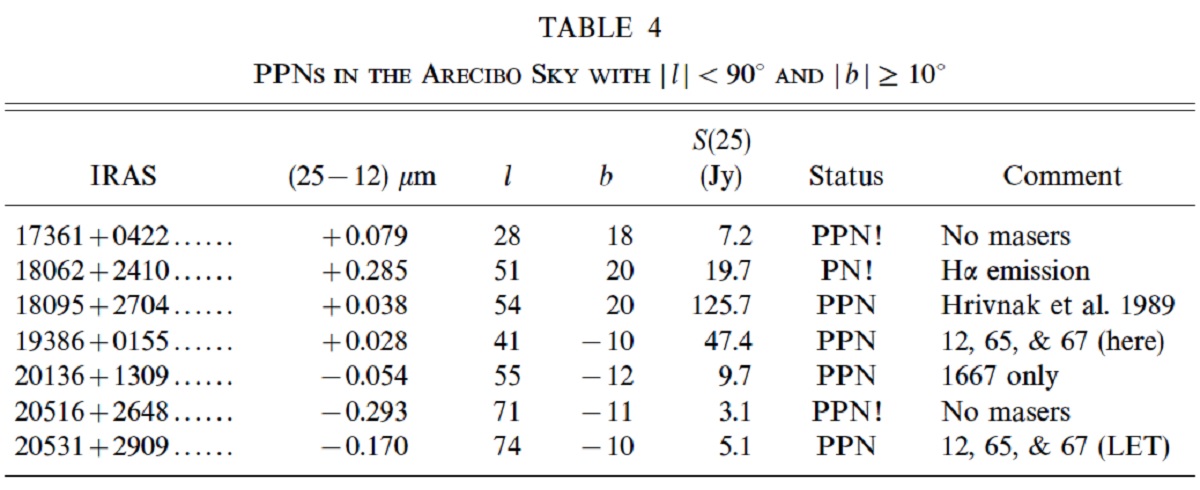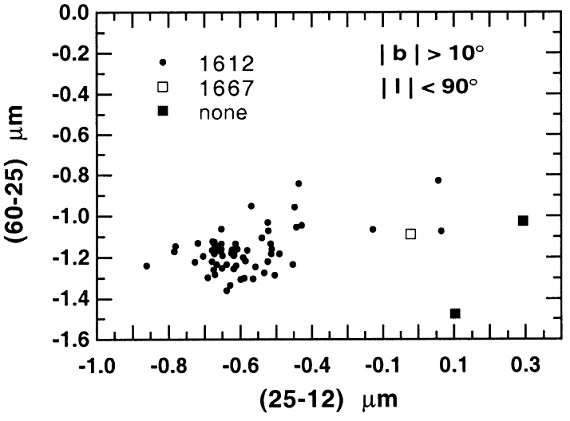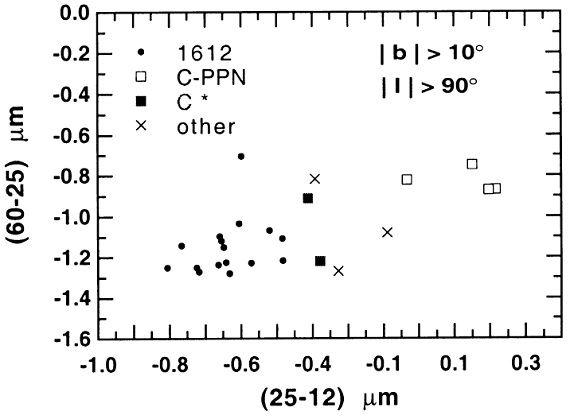メーザー源の二色図
Olnon, Baud, Habing, de Jong, Harris, Pottasch (1984)
はメーザー星の系列を IRAS 二色図上に描いた。アレシボ δ - [0,38]
領域で F12 > 2 Jy の OH メーザー源のカラー区分は、
(60-25) < -0.9 で、-0.7 < (25-12) < +0.25
-0.9 < (60-25) で、2.0x(25-12) - 0.9 < (60-25) < 2.25x(25-12)
(25-12) = log(S25/S12)-0.41,
(60-25) = log(S60/S25)-0.42 を使うと、
log(F60/F25) < -0.48 で、-0.29 < log(F25/F12) < +0.66
-0.48 < log(F60/F25) で、
2.0xlog(F25/F12)-1.3 < log(F60/F25) < 2.25x(F25/F12)-0.5
図1にはアレシボ OH/IR 天体の二色図を |b|>10 源に強調を付けて示す。
大部分は pre-IRAS OH/IR 星とミラ型星をつなぐカラー帯に存在する。
-0.38 < (25-12), つまり 0.03 < log(F25/F12) にはサンプル星が殆ど
存在せず、あったとしても全体の集合の縁にへばりついたものである。
表1=リスト
表1には S(25) ≥ 2 Jy の 1612 MHz, |b| 6gt; 10 アレシボ天体 81 個
のリストを載せる。周期は GCVS, Whitelock et al 1994 および
Jones, Bryja, Gehrz, Harrison, Johnson,
Klebe, Laurence (1990)
から採った。
図2=ΔV
図2には ΔV と (25-12) の関係、および二色図を示す。プロット点は
メインラインと水メーザーの検出状況をコード化してある。大部分の点はどち
らも検出されていることを示す。
図2a の右半分側にある天体は 22 GHz =水メーザーが検出されないのに、
反対側では大部分で検出されているのは注目すべきである。
同様に、図2c において、メインラインが検出されない(水非検出の間違い?)
3天体は赤い側の端に固まっている。これらは
Lewis (1989)
が提案した時間系列から期待されるパターンと一致している。
| |
PPNs の特徴
そう言うわけで、18095+2704, 19386+0155 = 1612 MHz よりメインラインが
強く、水メーザーを持たない赤い天体、は PPNs なのである。一方、図の青半分
にある星は OH/IR 星、またはミラ型星である。
ミミックの検出率は低い
それら OH/IR 星における水
メーザー検出率 92 %, メインライン 97 % という高い検出率は、カラー選択
した最初のサンプルの 75 % を占めるミミックと好対照を示す。
(数字の表現が整理されていないので
イライラする。ミミックって 1612 MHz 非検出の星? )
ミミックでは、水メーザー検出率は 36/111 = 32 %、メインラインは 41/206 =
20 % である。
YSO ?
03220+3035, 03237+1149, 04236+2559, 04305+2414 は図2の赤い側星の半数
だが、膨張速度が決まらない。それらは 1612 MHz と同じ速度に孤立した 1665,
1667 MHz ラインを示す。さらに 4 天体は RA = 3 - 5 h で Orion-Taurus 分
子雲複合に近い。したがって PMS 星の可能性がある。
ミミック
カラー選択した |b| > 10 の IRAS 天体中 75 % は 1612 MHz 非検出である。
これらの内で赤い天体は Lewis 1992 により、ミミックと名付けられた。
-0.7 < (25-12) < -0.38 という OH/IR 星の狭いカラー巾により、この
命名をここでも使ってよいだろう。ミミックの多くは M-型の通常のミラ型星で
P = 300 - 450 d である。ミミックの割合は (25-12) > -0.5 では 29 %
以下に低下する。
|