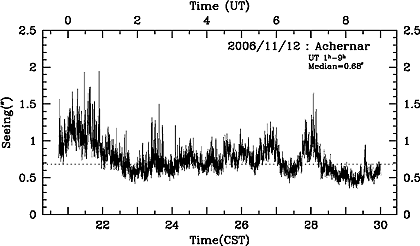|
東京大学アタカマ天文台 (TAO) 計画 |
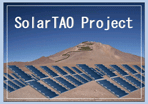
|
2006年11月チャナントール山山頂でのシーイング測定結果報告2007年4月9日発行
1. 今回の測定のまとめ2006年11月上旬に、ついにチャナントール山山頂 (標高5650m) での 3夜+α にわたるシーイングモニタ観測に成功しました。その結果は以下の通りです。
# メンバー : 本原、青木、宮田、酒向、三谷、峰崎
2. 測定概要シーイング測定は 11/7-11/13の夜に挑戦し、そのうち11/8, 9, 12, 13 の 4夜に測定を行うことに成功しました。 機材は前回2003年のシーイング測定時とほぼ同じです。ただし、山頂の低圧下ではハードディスク不調が続発することが判明したために、今回はデータ取得をコンパクトフラッシュメモリカードを使い、ハードディスクレスにしたノートパソコンで行いました。 また、ソフトウェアも大幅な更新を行い、オートガイド機能も搭載して、観測開始時に星を中心に入れればあとは明け方まで無人観測を行えるシステムとなりました。これにより、明け方6時までのデータを3夜取得することができました。作業としても、日没前後に山頂に上がり星の導入を行うのみで後は放置して下山できるため、肉体的な負担も大きく軽減されています。 ただし最後の一夜 (11/13) は、開始直後に雲が出て星を見失い、そのまま観測終了になってしまうという残念な結果となりました。
3. 測定結果シーイング測定結果は日による違いがあるものの、一晩を通じての中央値が0.6-1.0秒角程度と良好な値を示しています。これは2003年のトコ山 (5400m)、チコ山 (5200m)での測定結果と遜色のない値です。 特に11/12の晩は、図4に示したように中央値でも0.6秒角台で、比較的短時間ではあるものの連続して0.4秒角を記録するなど非常に良好な値を示しています。 また、今回の測定地点は山頂領域でも風上側の斜面から30m程離れた場所で、さらに周囲よりも2m程低くなっている領域であったので接地境界層乱流や、山肌を吹き上げた風が起こす乱流の影響を大きく受けていると考えられます。 このような必ずしも良くない測定環境ですら上記のような値が得られたことは、チャナントール山山頂でのシーイング環境のポテンシャルの高さを垣間見せた結果であると言えるでしょう。
4. 今後の予定今回は山頂でのパイロット的測定の面が濃いもので、測定条件も必ずしも理想的ではありません。 そこで、2007年度からはより接地境界層乱流などの影響を受けにくい、西側斜面に近い場所にタワーを設置しての測定を開始する予定です。 また、より統計的に意味のある、1週間以上の長期にわたる連続測定も行うことを予定しています。 今後の山頂でのシーイング測定にご期待下さい。 本原顕太郎
Copyright(c) 2007 東京大学大学院理学系研究科 TAO計画推進グループ
当サイトについて |