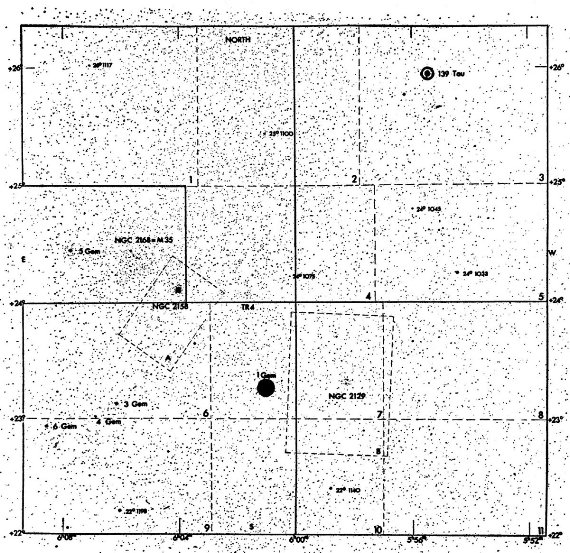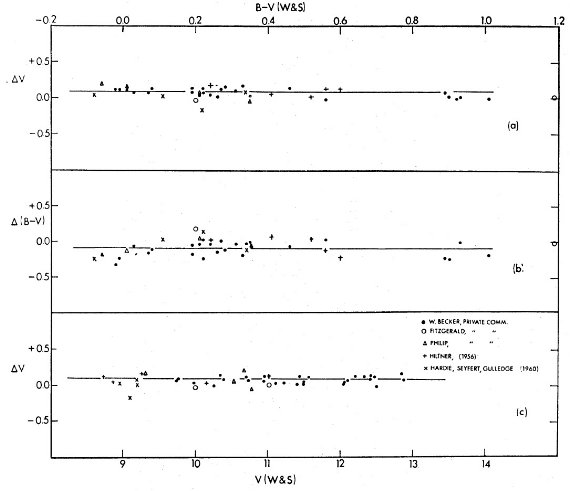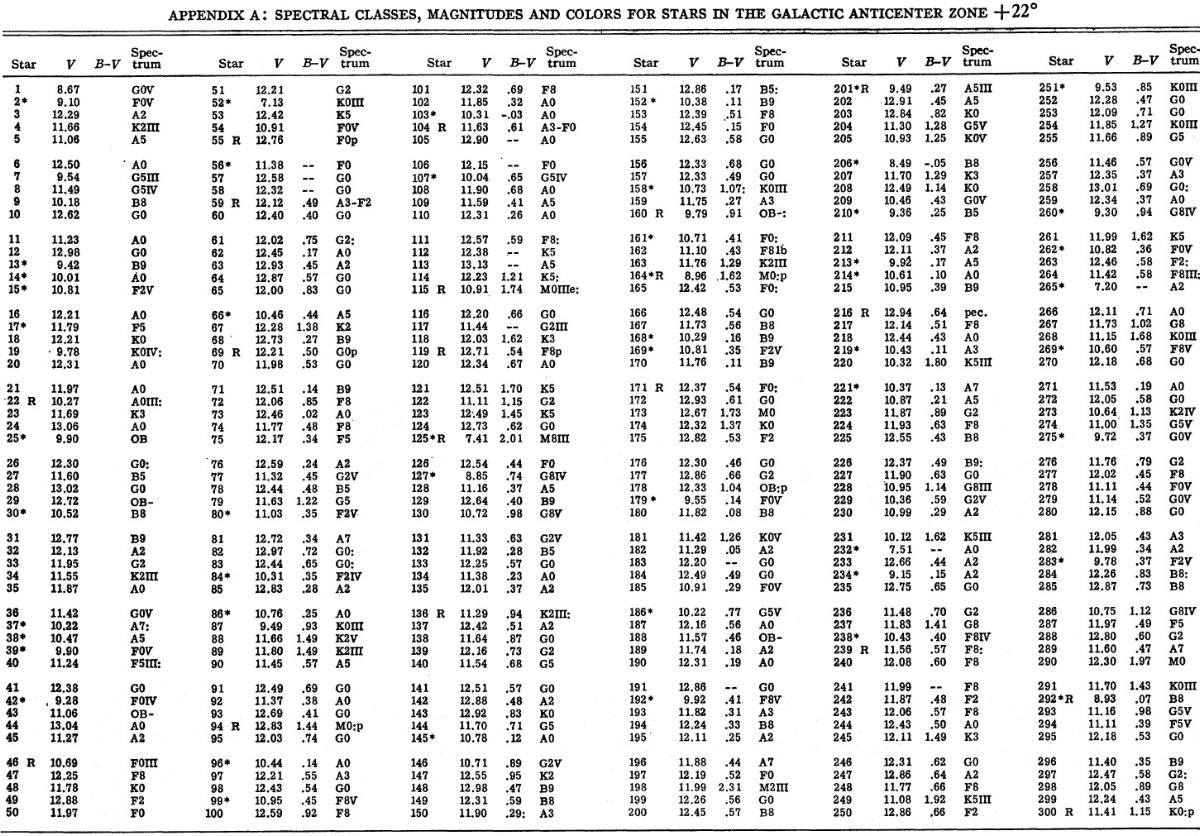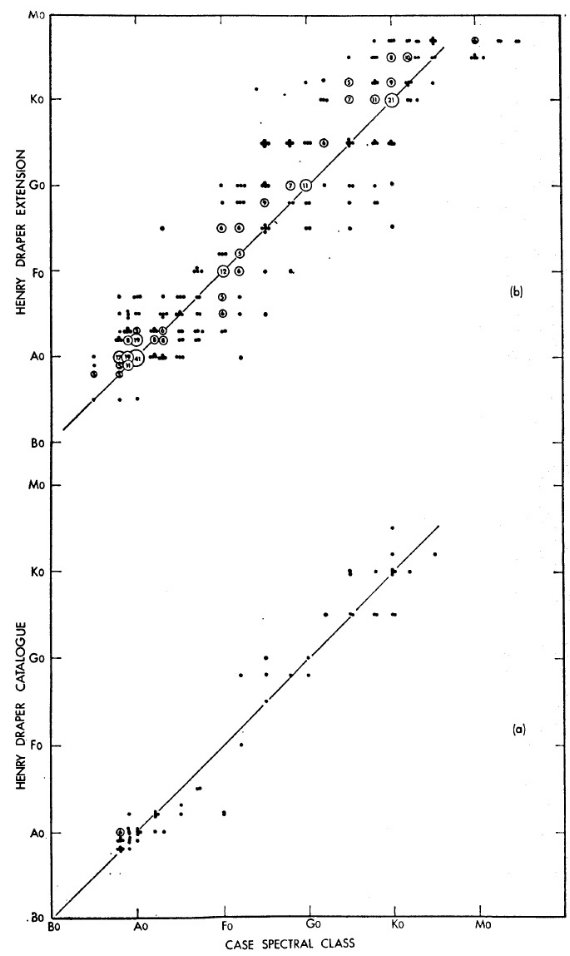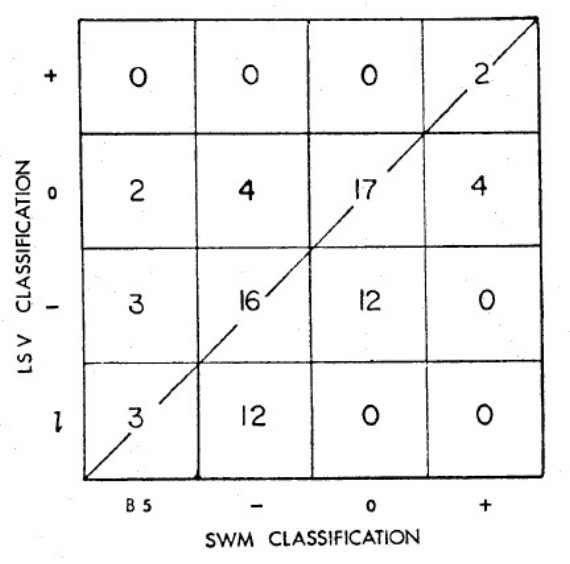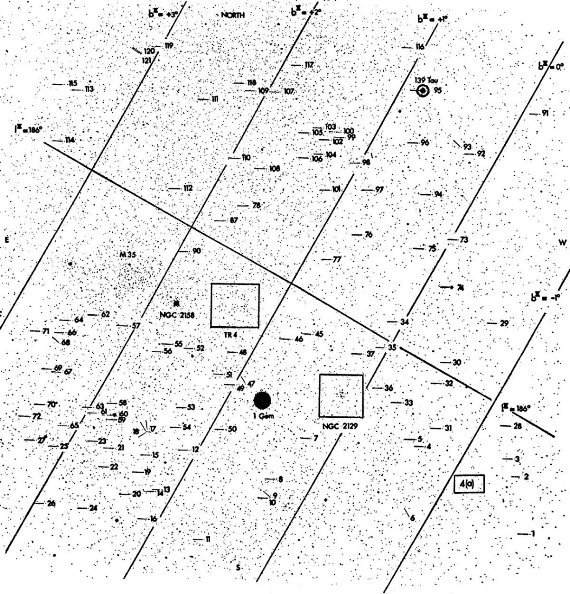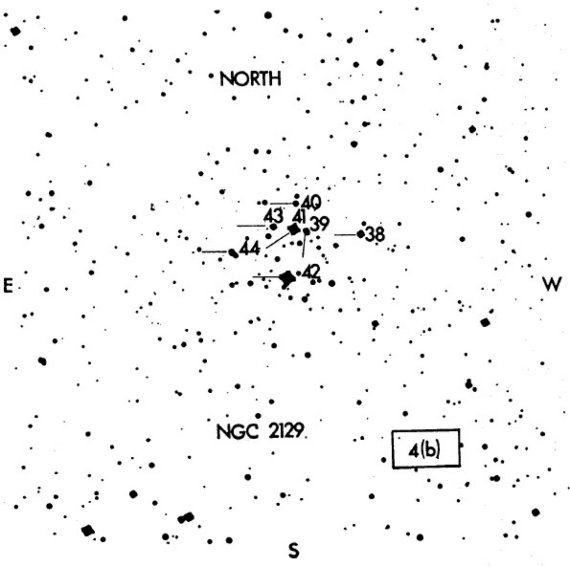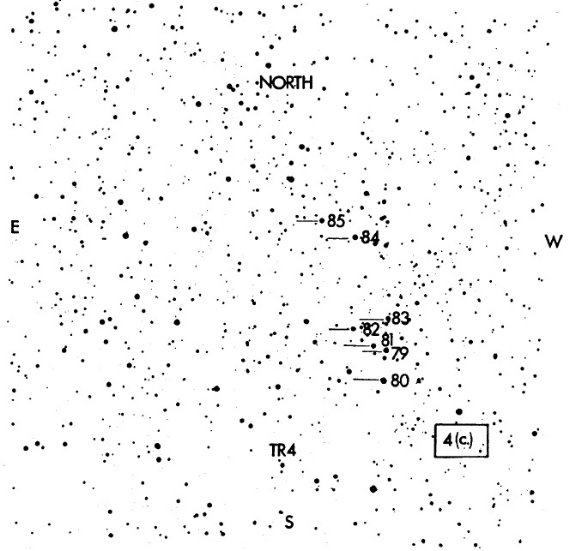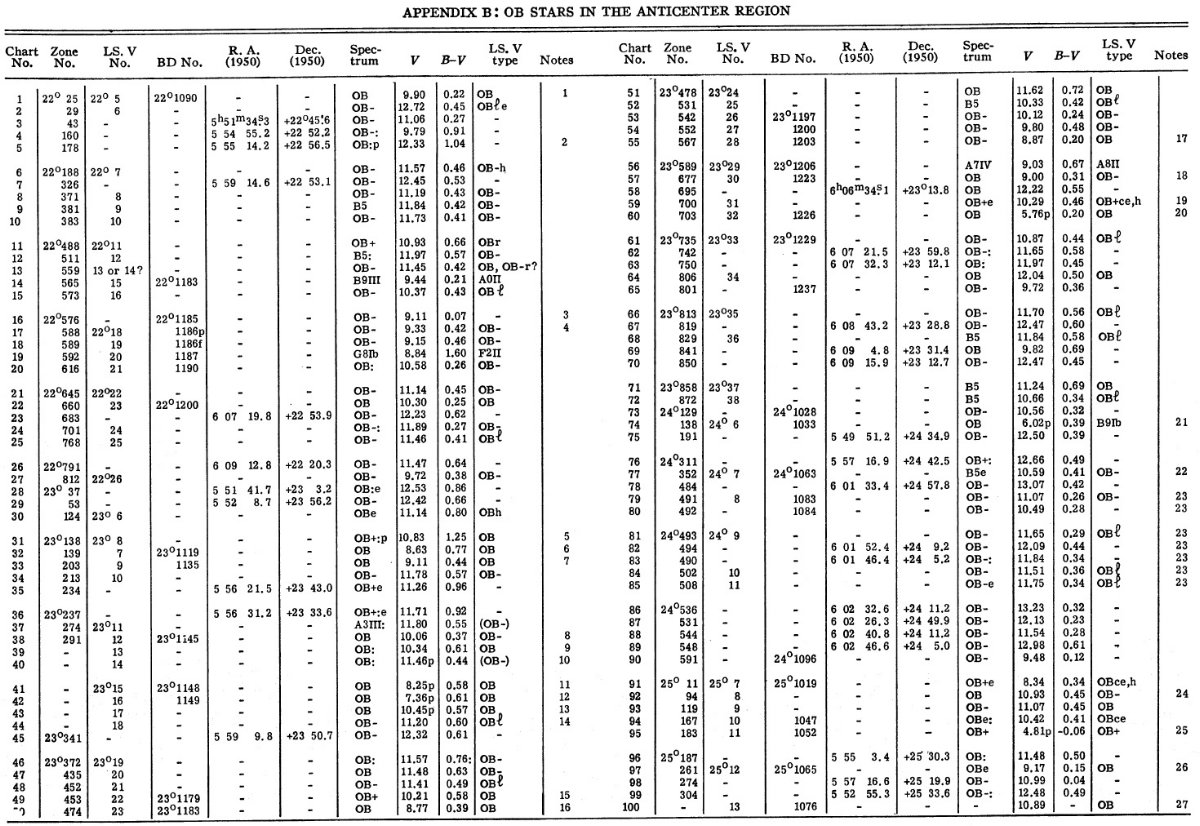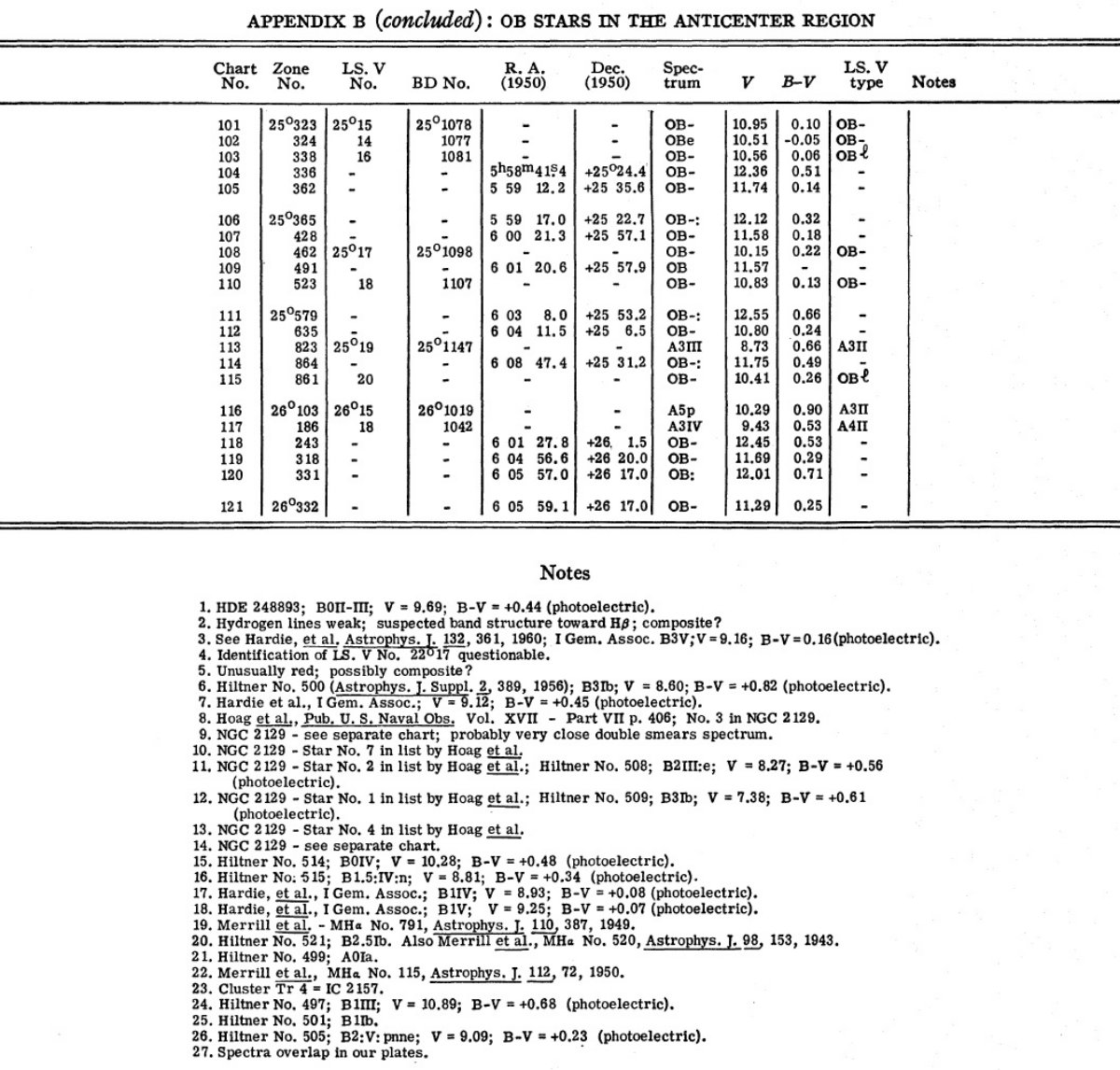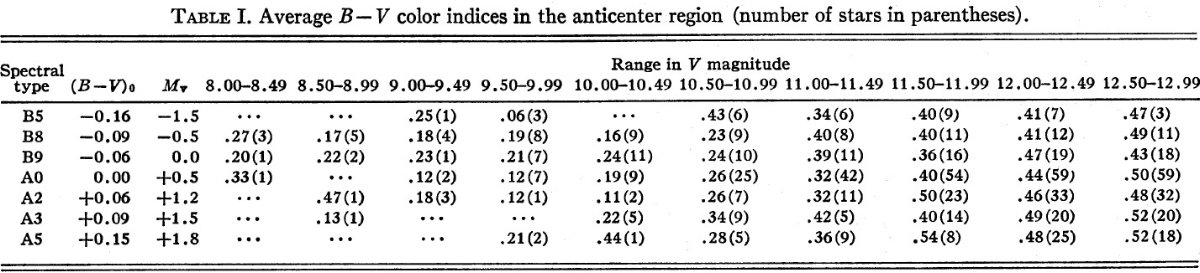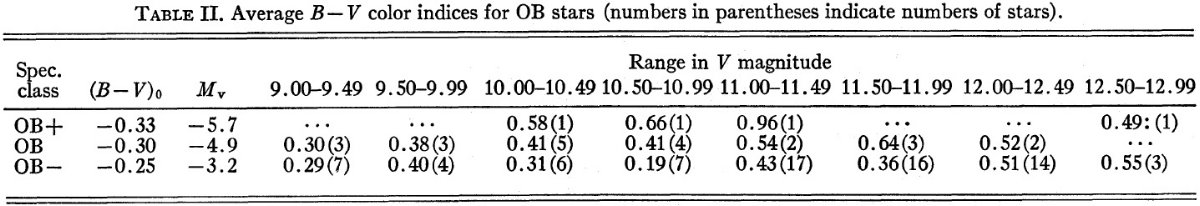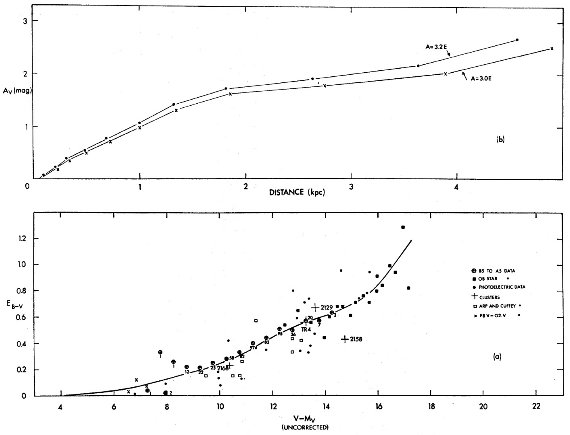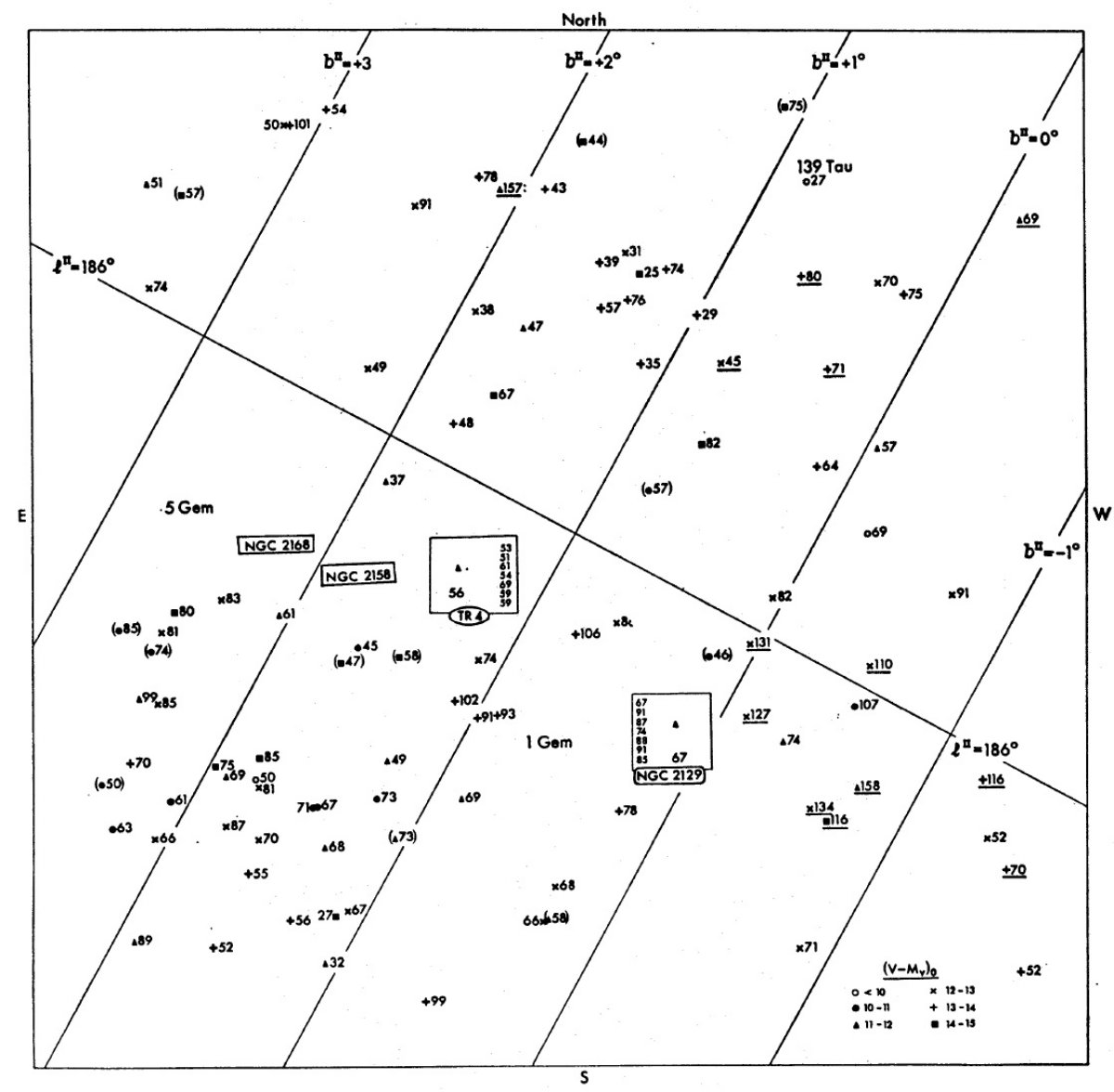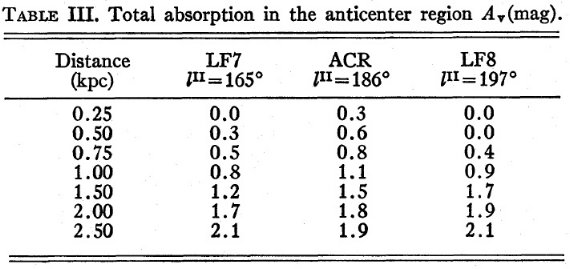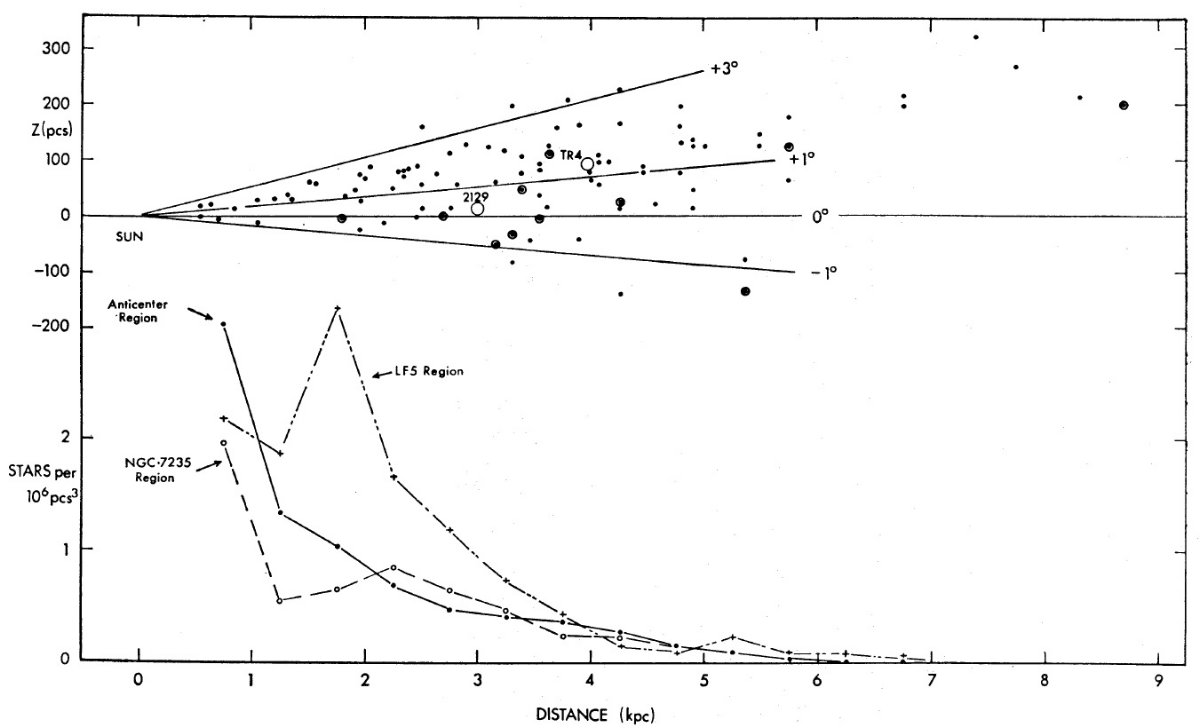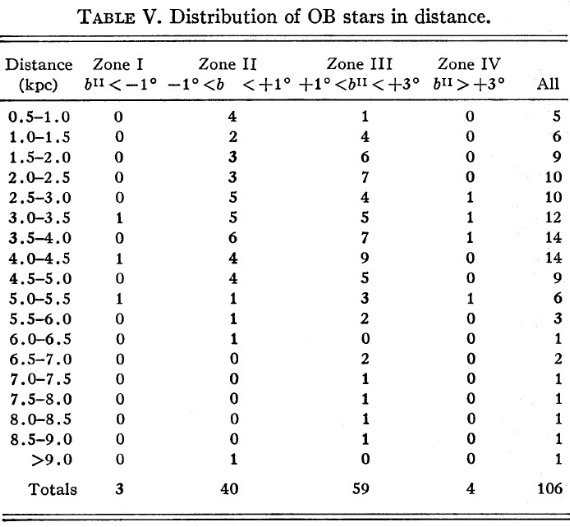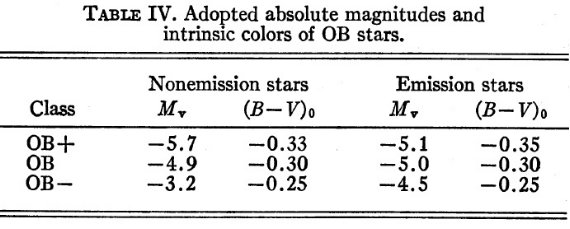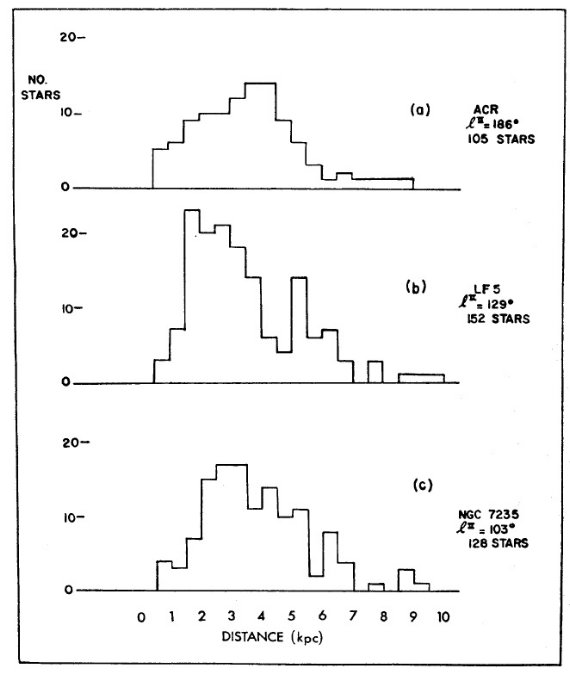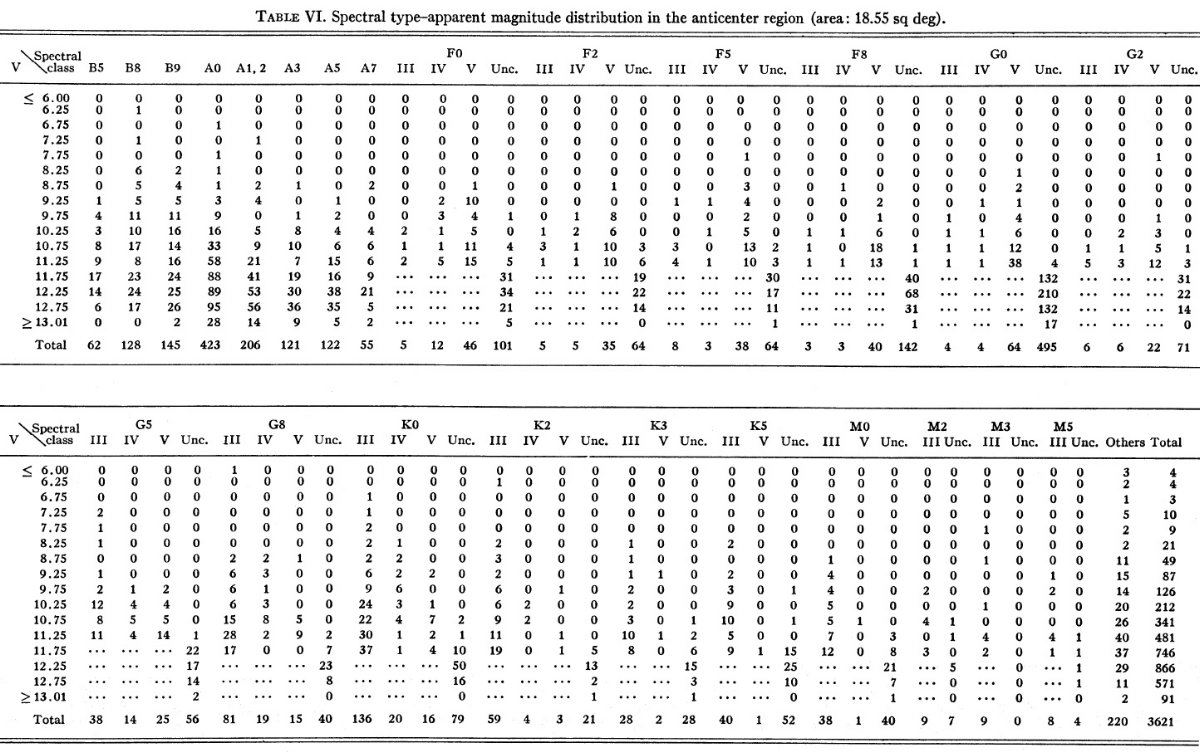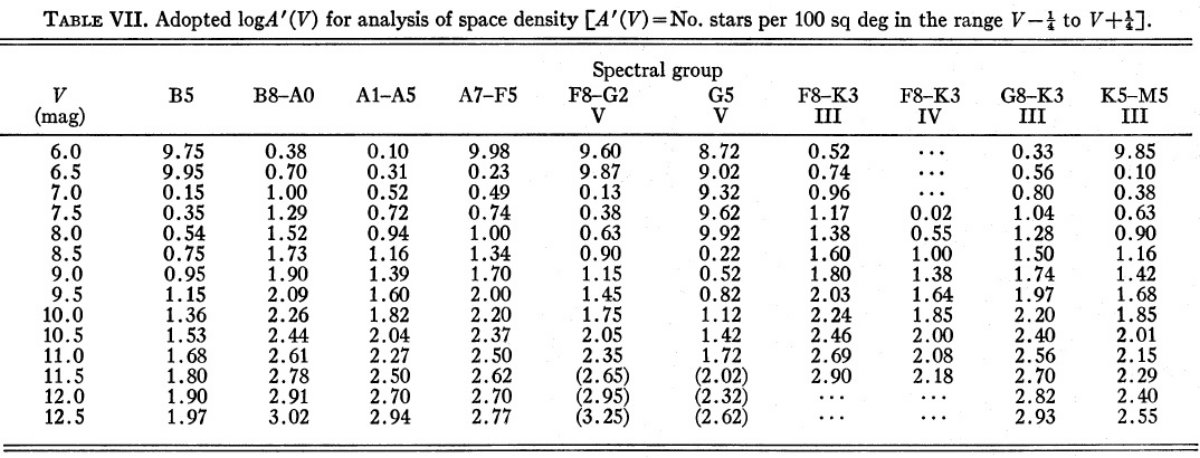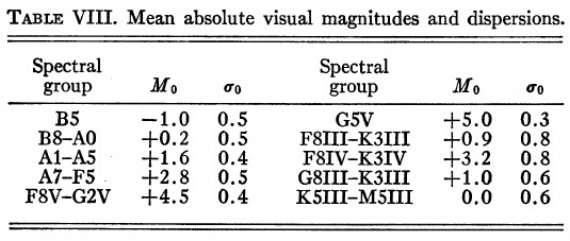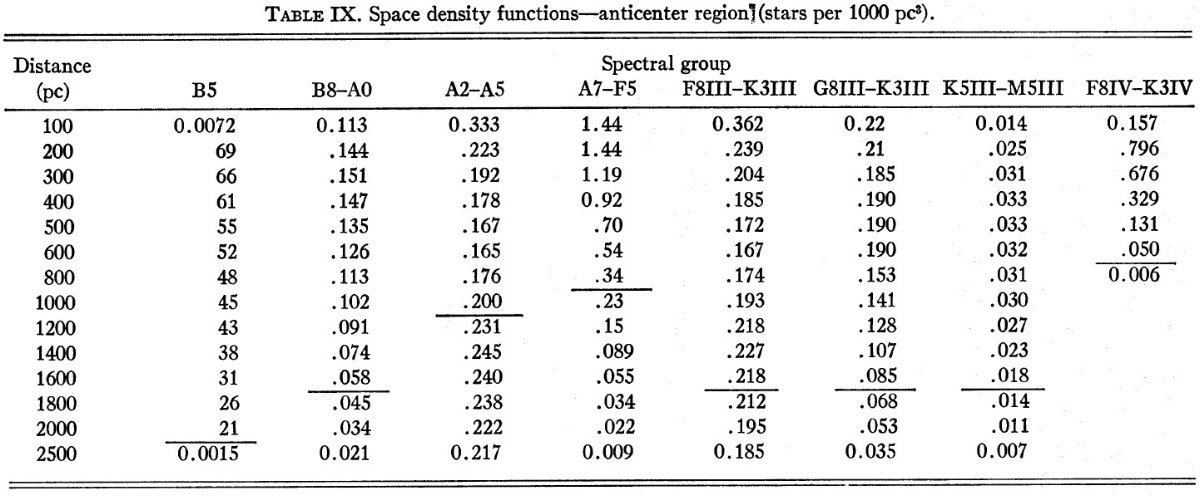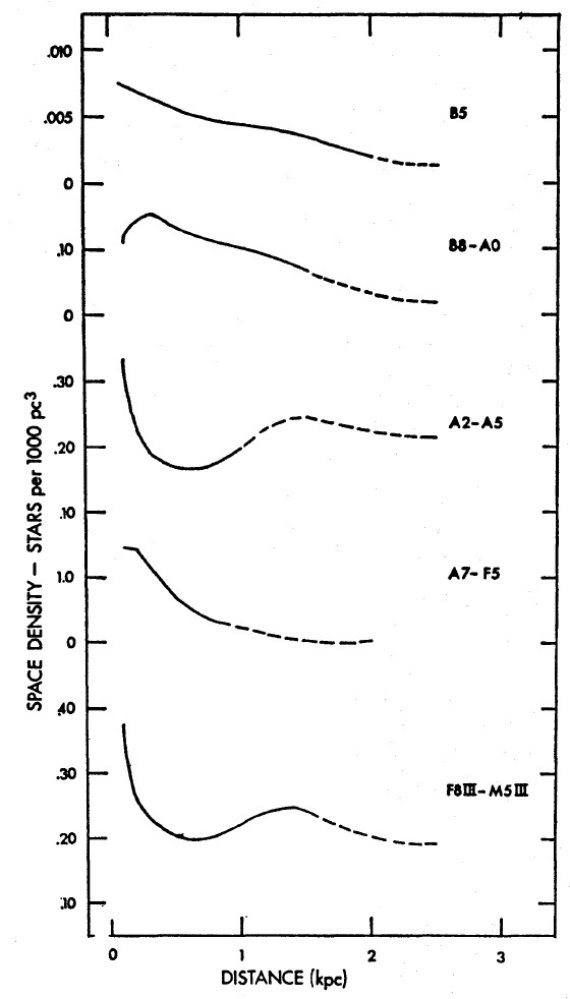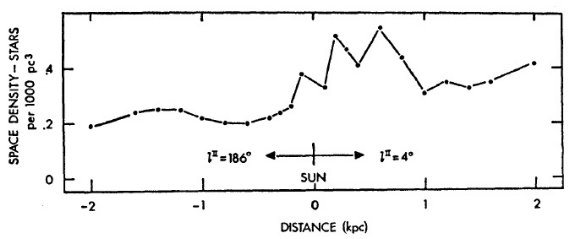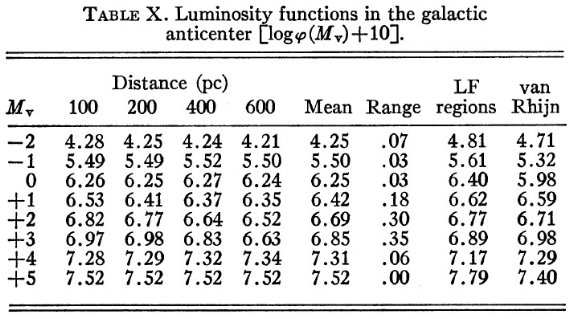表5.OB 星の距離分布
OB-星の距離
付録Bにある OB-星の大部分については、表4にある絶対等級を用いて、距離
を求めた。星間減光の補正は前節に述べた E(B-V) に R = Av/E(B-V) = 3.2 を
仮定して行った。表5には l = 186 で銀緯を4つの帯に分けて 106 OB 星を
距離グループに分けた結果を示した。
83/106 星は 0 > z > 200 pc で銀河面の北側に存在する。この偏りは
図8にも示されている。 OB 星の大部分が +1 > b > +3 に存在する。
ここで見ている星は明らかに銀河面の北側、厚さ 150 pc の層を成している。
この分布は Hardorp, Theile, Voigt 1965 の LS.V カタログにも現れている。
これらの星の多くは I Gem アソシエイションに属している。
見かけ距離分布のピーク
図9a は OB 星の距離分布を示す。r = 4 kpc の所に極大があるように見える
がこれは巾の広がり効果による見かけである。実際の空間密度を計算してみると、
図8に示すような分布となる。OB 星の数が 5 kpc より先で減少しているように
見えるが、これは観測限界によるためかも知れない。 5 - 6 kpc より遠方の星
は見かけ等級 12 程度となり、検出限界に近い。この結果は、LF 5 (lII
= 129) McCuskey, Houk 1964, や NGC 7235 方向 (lII = 103) Seebach
1967 の結果と類似している。図9 b, c にそれらを示す。図8下には実際の
空間密度を比較した。
3つの方向の比較
まず、LF 5 に現れる距離分布のピーク (図9b) は空間密度, 図8, に直し
ても依然として r = 1.8 kpc に存在する。このピークは McCuskey, Houk 1964
で既に指摘されていた。この方向では、OB 星の分布は b = [-4, -2] よりも
[-2, 0] に集中する。
NGC 7235 周辺方向では図9c にあるように、 OB 星が最も集中するのは r =
3 kpc 付近であった。空間密度にも r = 2.3 kpc に弱いピークが見られる。
Schmidt-Kaler 1966 によるペルセウス腕中心位置は NGC 7235 方向
, lII = 103, で r = 2.7 kpc, LF 5 方向, lII = 129
で r = 2.3 kpc である。つまり、OB 星空間密度ピークはペルセウス腕の
中央から 0.4 - 0.5 kpc 太陽側にある。
これらのピークを渦状腕に伴う構造と解釈すると、OB 星の集中はペルセウス
腕の内側縁の存在することになる。
ただし、誤差の大きさには留意すべきで、例えば仮定した Mv が 0.4 mag
減少すると、推定距離が伸びて OB 星集中の位置は、銀河星団、 HIIR など
で表されたペルセウス腕の中央に乗ることになる。
| |
表4.OB 星の絶対等級
図9.OB 星の距離分布。上から、 lII = 186, 129, 103.
Hα 輝線その他の異常が見える星は除いた。
反中心方向に腕の証拠なし。
反中心方向 lII = 186 には OB 星の分布には、局所腕の先に
渦状構造の証拠が見えない。渦状腕の最もよい指標となる OB+ 星の分布
は r = 0.85 - 4.9 kpc に散らばっている。総数でわずか 7 個である。内
4 個が r = 2.6 - 4 kpc にあるが、集中というには弱すぎる。
Klare, Neckel 1967 にも反中心腕はなし
ここで得られた結果は最近、
Klare, Neckel 1967
が発表した 6173 個の OB 星の分布と一致する。それにはオリオン腕、サジタリウス腕、
ペルセウス腕に付随するかなり幅の広い星の集中が認められた。しかし、ペルセウス腕の延長
は反中心方向には認められられなかった。
|