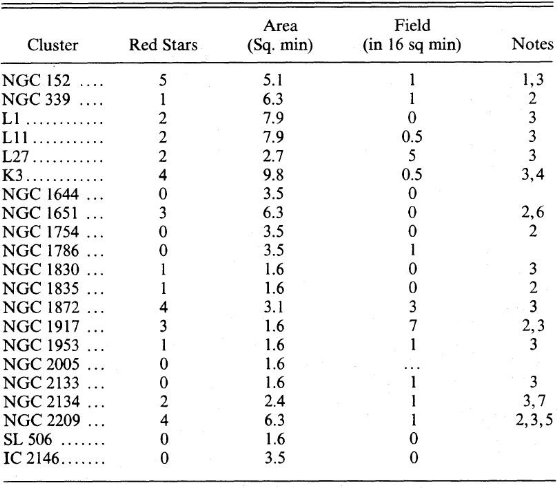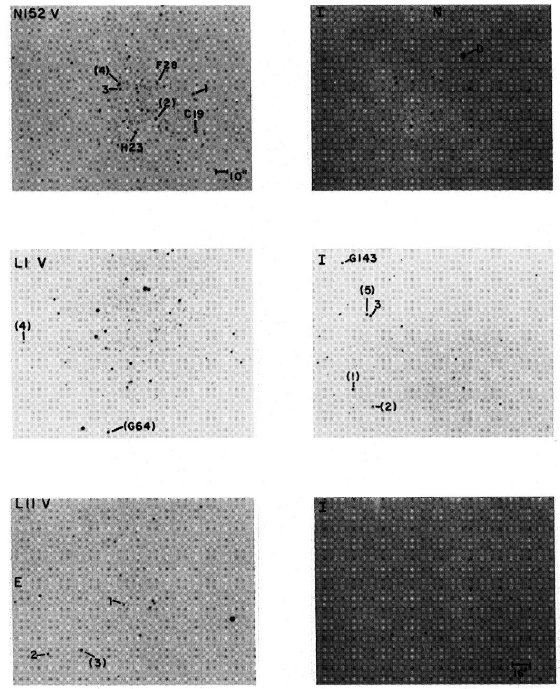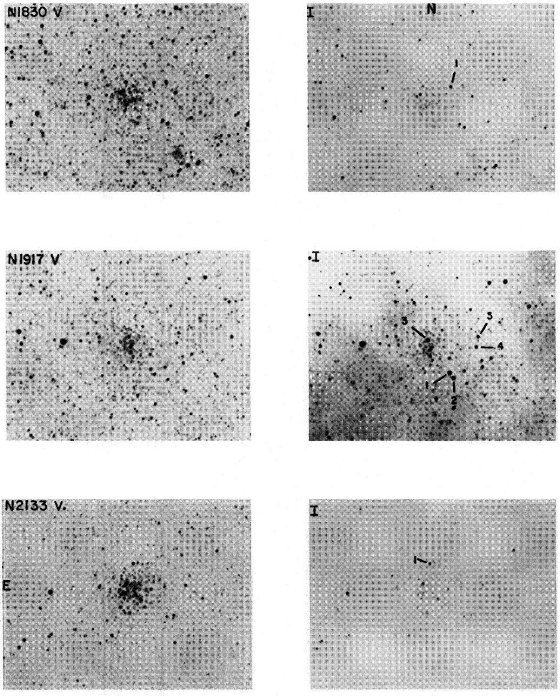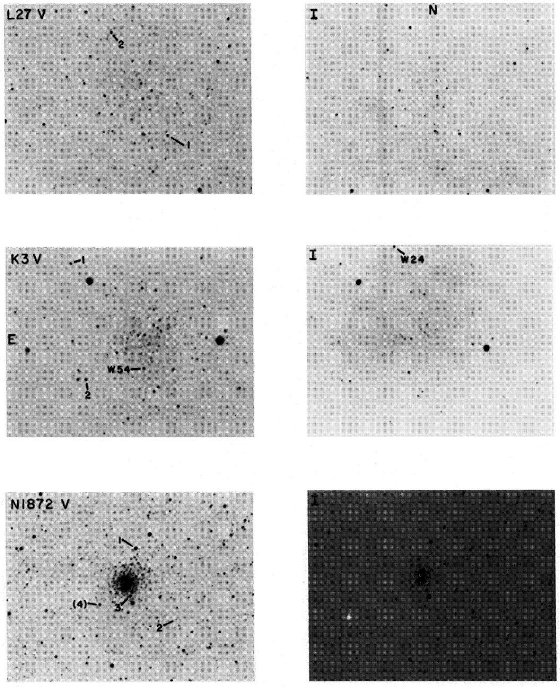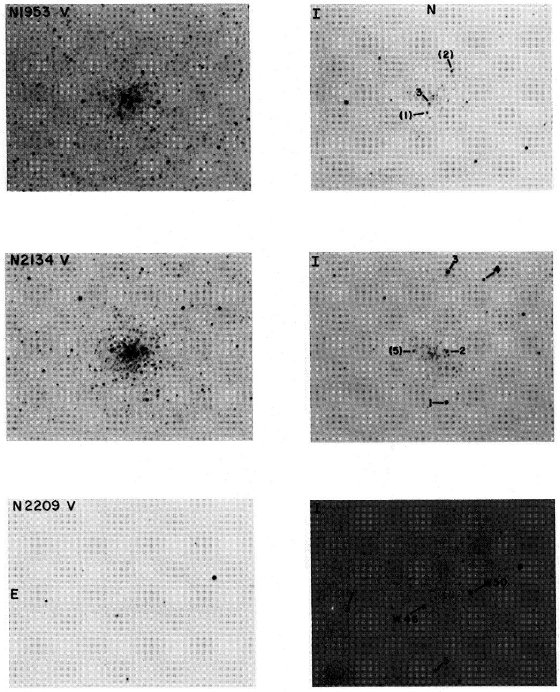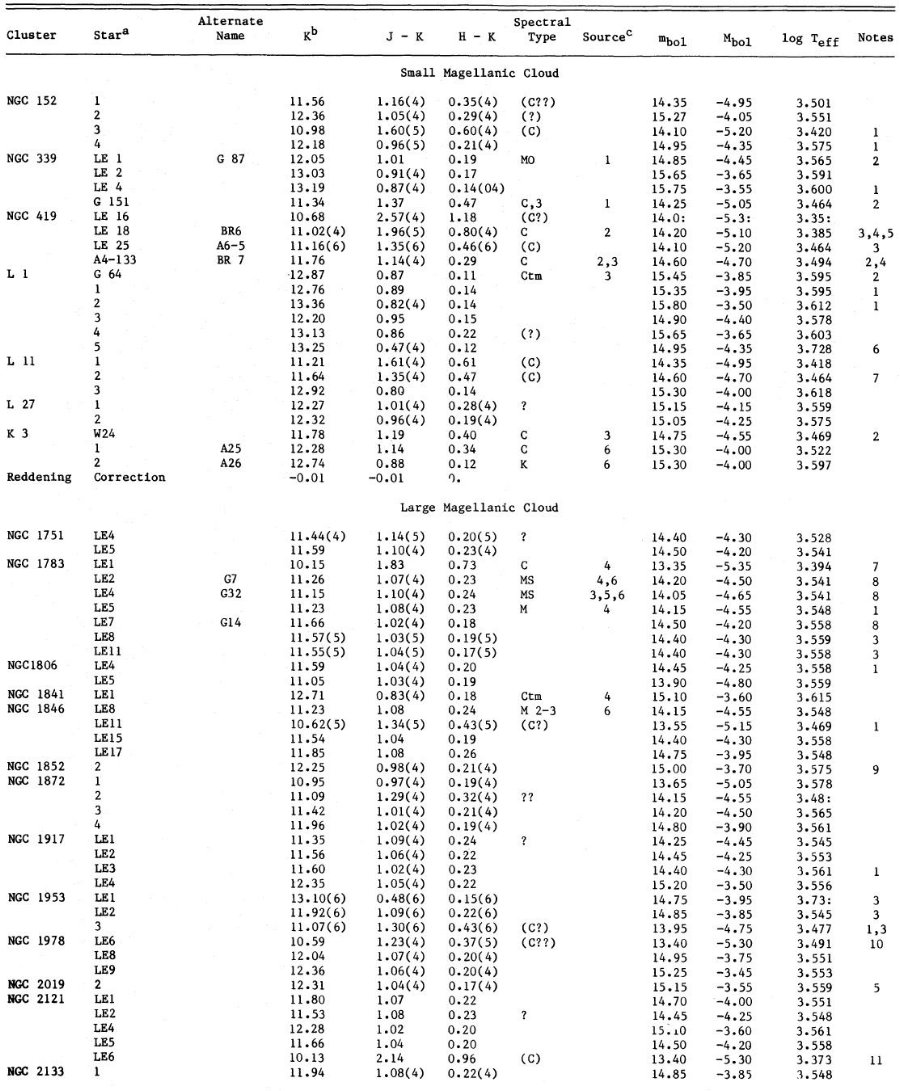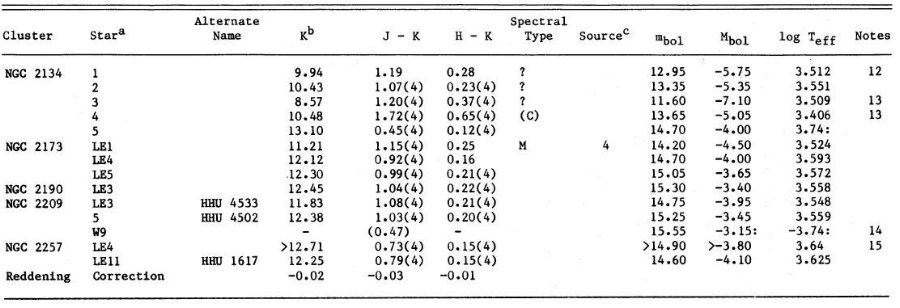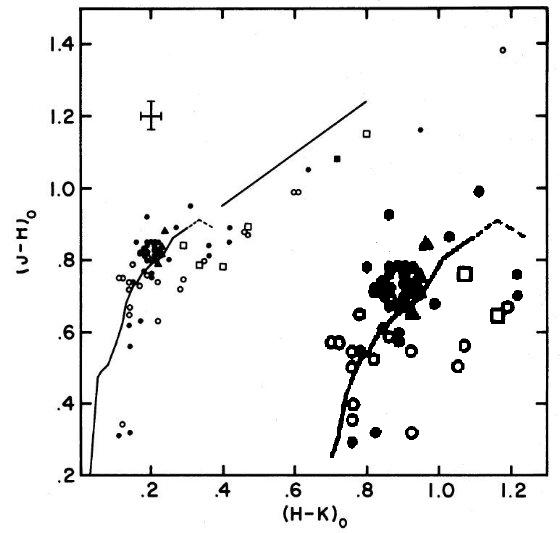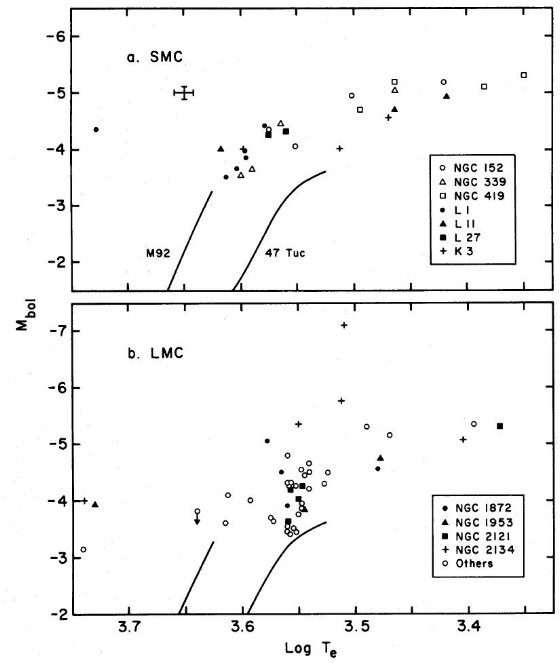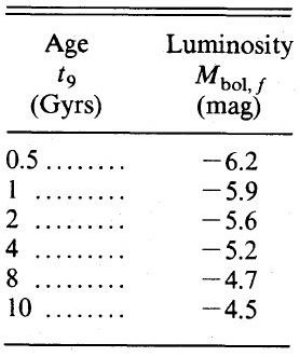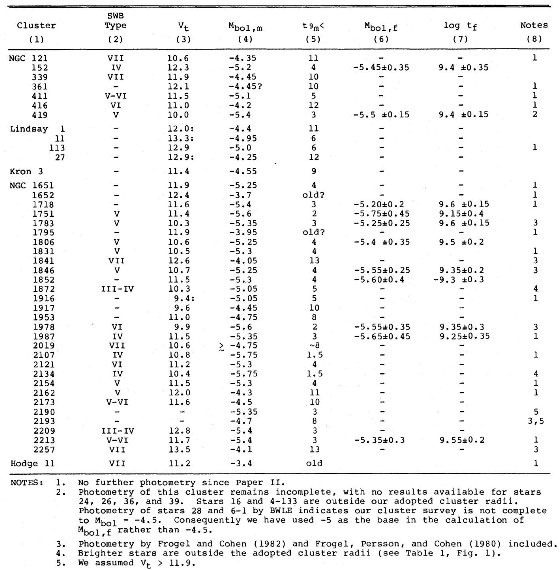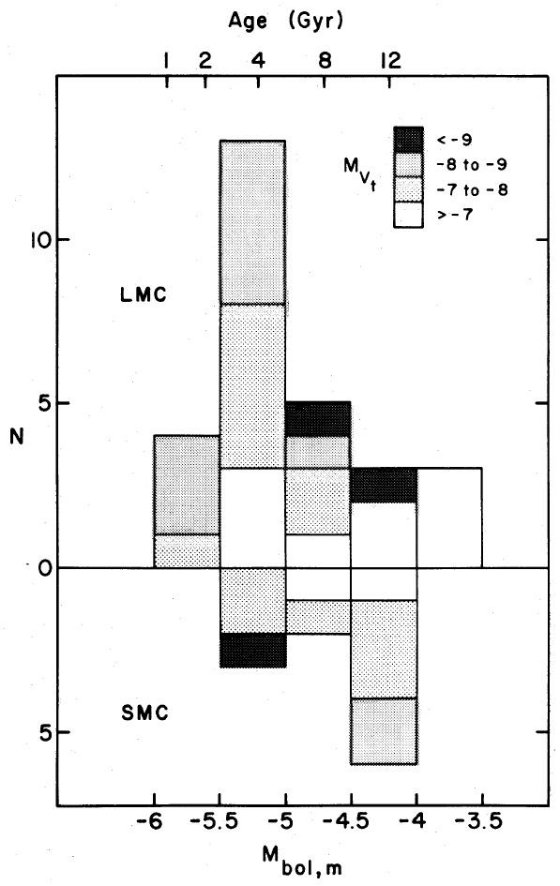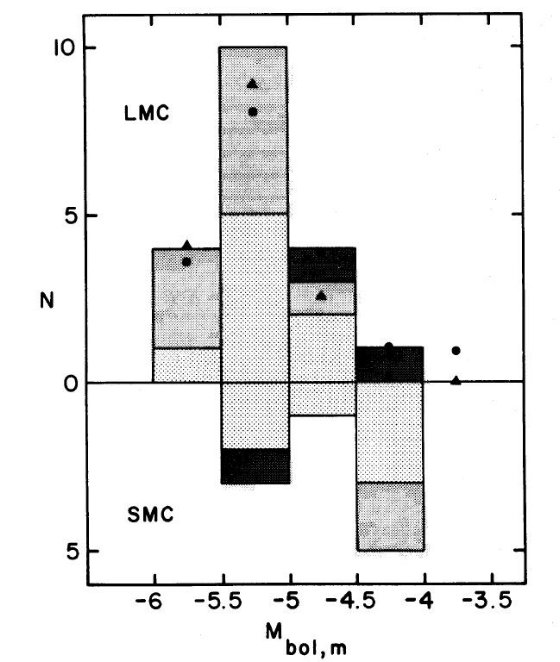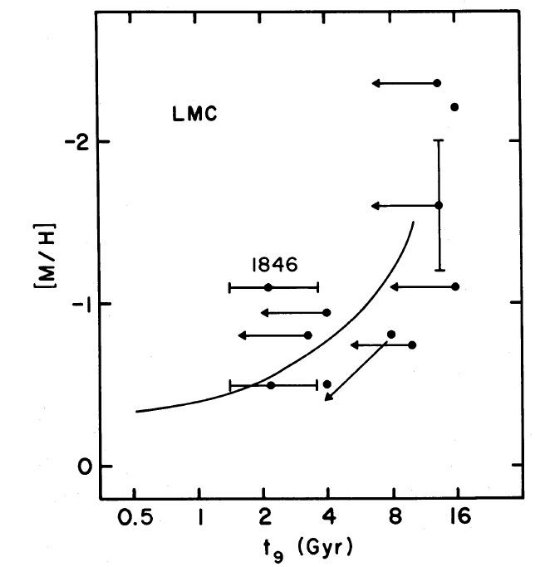表4は星団形成史を表わすのか?
図4は観測された AGB 先端光度の分布。表3を用いた年齢目盛りも付けた。
そのまま見ると星団形成率の変化を表わしているようである。不適切な結論
を導かないよう、次の点に注意する。
(1)データは観測値 Mbol, m で区切られている。これは
年齢較正に使う Mbol, f より暗い。その差はストカスティック
である。Mv < -7 の星団ではその差は1ビン以内である。
(2)星団光度は時間と共に暗くなる。等級リミッテッドなサンプリングを
行っていると若い星団ほど観測対象となりやすい。
(3)潮汐破壊の効果が不明瞭である。
早急な結論は慎むべきだが、図4の強いピーク、Mbol, m = -5.25 は
Butcher 1977
が LMC 主系列光度関数から提唱した大規模星形成の開始
を反映しているのかも知れない。それとも、Gerald et al 1980 が言う
矮小銀河の爆発的星形成なのだろうか?
より慎重な見方
より保守的な立場からは、現在のデータが星団形成率一定という仮説
と適合するのかという問いを設定できる。これに答えるため以下の仮定で
簡単なモデルを作った。
(1) Tinsley 1972 による星団の進化。
(2)星団の初期質量関数はべき乗型。
図4.観測された AGB 先端光度の分布。上=LMC 星団。下= SMC 星団。
ヒストグラムの色分けは星団光度の区分。
| |
(3)この初期関数の高光度カットオフ Mv,min(t)
過去数 Gyr NGC 121 ほど明るい星団が生まれていない
(4)Renzini 1977 の式 2.5, 6.18 の恒星進化の式
Mv,min(16 Gyr) = -13, Mv,min(0.1 Gyr) = -11
のモデルは LMC データに合う事が判った。それを図5に示す。大事なのは
このモデルが星団形成期間にあまりよらないことで、期間 16 Gyr も 6 Gyr
も同じくらいよくデータに合う。
SMCの場合
SMCの星団光度分布を再現することは難しい。10 サンプルで,
n(-3.5 to -4.5) > n(-4.5 to -6) の例が出来るのは 1% 以下であった。
LMC 星団系の年齢は全体として若い?
区切りが粗いのではっきり見えないのだが、Mvt < -7 の
星団は、 Hodge 11 を除いて、全て同じくらいのメタル量を持つ銀河系球状
星団の巨星枝より先まで伸びている。LMC "古い" 星団で言うと、NGC 121 は
Aaronson, Mould 1982
で見る通り伸長した AGB を示すし、 Frogel, Cohen 1982 が扱った NGC 1841 も
同様である。今回 NGC 2257 にも Mbol = -4.1 の LE 11 が見つかった。
NGC 1466 が残っているが、これがメンバーかどうか問題にされている。 Rabin 1982
は NGC 1841 に関してもバルマー線強度から似た結論に達している。
彼は非常に低メタルの系では水平枝が数 Gyr の変化を吸収(?)するとした。
我々のデータは LMC の星団系は銀河系に比べ 3 - 5 Gyr 程度若いのでは
ないかと疑わせる。
図5.Mv < -7 に限定し、図4と同じことをした。黒印は
星団形成率一定(黒丸= 16 Gyr の間, 三角= 6 Gyr)の場合
のモデル。
|