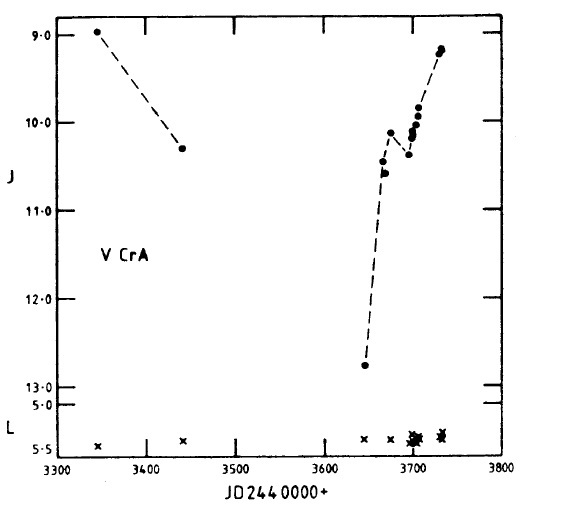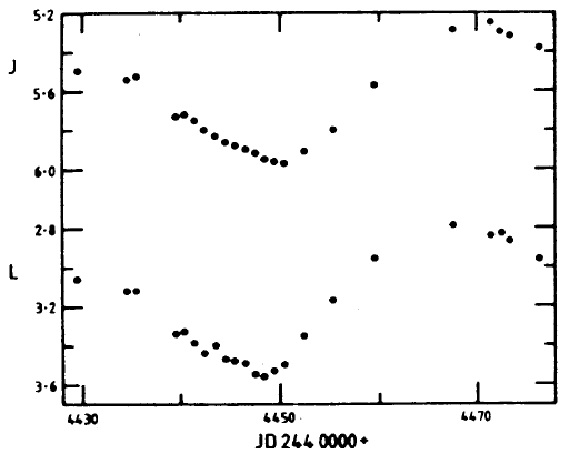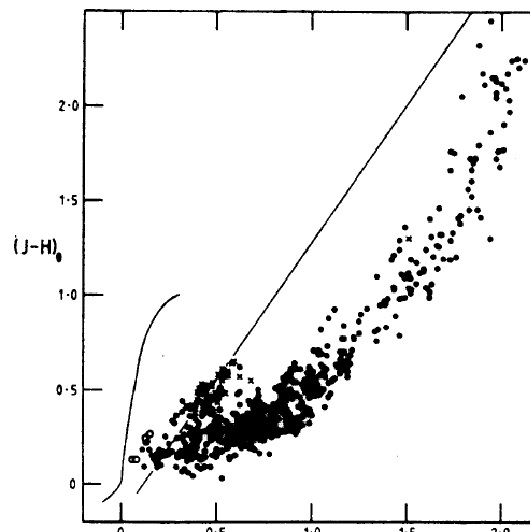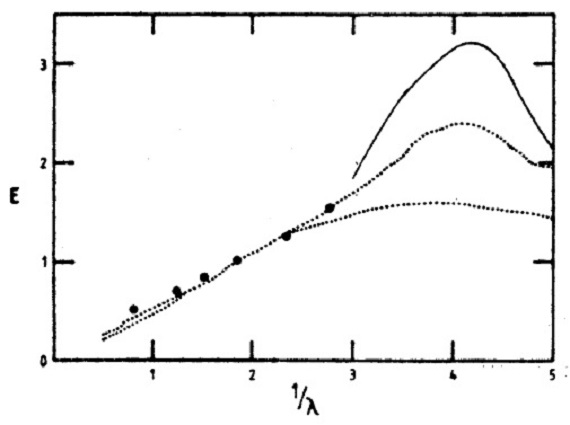二色図
図3は 12 RCB 星の (J-H)-(H-K) 図である。3つの高温星 MV Sgr, DY Cen,
V348 Sgr を除くと、極小時を含む全ての観測点が狭い帯の中に入ることが
わかる。個々の星はこの帯に沿って動き回っている。これは、 RCB 星の特性が
星本体、シェル双方ともに、極めて狭い範囲に限定されることを示す。
HdC 星
白丸は HdC 星であるが、RCB 星がもしシェルを伴わなければ予想される位置
にあることは興味深い。Glass, Catchpole 1974 は正常星の2色図が黒体から外
れる原因を調べ、それが主に H- オパシティによることを明らかに
した。HdC 星では H- オパシティの働きは弱く、それが HdC 星の
位置を黒体に近づけているのである。
RCB 星表面温度
Schonberner 1975 は RY Sgr と R CrB の温度を Teff = 7000 K とした。
しかし、 RCB には様々な強度の C2 吸収帯が見られる。中でも
S Aps (図3のバツ印)は非常に強いバンドを示す。これらからは、5000 K まで
下がる温度が推測される。それは炭素量が大きいせいかも知れないし、表面温
度の不均一によるのかも知れない。二色図上の S Aps の位置は温度が低いため
かも知れないが、弱い星周減光があるのかも知れない。この問題に関し、興味
深いのは、 Espin 180, 1894, 1900 の観測で、一週間ほどの間、 R CrB が
強い C2 バンドを発達させたが、その時期 R CrB は極大期にあった。
RS Tel は Payne-Gaposchkin 1936, 1963 によると R8 の非常に冷たい
RCB 星であるが、 Bidelman 1953 は C2 が弱いとく、 UBVRI
データ(Kilkenny, Whittet 184) からはこの星が異常に低温という証拠は
得られなかった。Payne 1928 はこの星を R0 とした。初期の分光観測データ
は再チェックの必要がある。Saio, Wheeler 1984 は 7000 K 以下では脈動振
幅を安定に保てなかった。このように、 RCB 星の温度巾は未定である。
RCB 星は脈動変光星か?
全ての RCB 星は脈動変光星だろうか? Kilnenny 1982 は RY Sgr
が平均周期 38.6 日で 1 秒/日 の割合で短くなっていくことを見出した。これ
は Schonberner 1977 の計算とも合う。すべての RCB 星はわずかな変光を極大
時に示すので、脈動変光星なのかも知れない。しかし未確定である。 Fernie et
al 1972 は R CrB に 44 日周期を見出した。Griffin 1985 は視線速度の変化が
49 日周期を持つとした。また、 Batesin 1972, Kilkenny, Flanagan 1983 は
UW Cen に 43 日周期があるのではないかと述べている。
| |
図3.12 RCB 星の (J-H)-(H-K) 図。モニター観測結果を全て載せた。
バツ印= S Aps. 白丸=HdCs.直線=黒体。曲線=正常星。
Kilkenny 1983 の観測
は S Aps が現在 40 日付近で変光していることを示すが、周期 120 日
が以前には言われていた。一層の観測が必要なことは明らかであるが、しかし、
RCBs が大体 40 日の周期を有するという仮説は捨てきれない。
星とシェルの相対光度比
ここまで、星とシェルの温度が狭い範囲に集中することを強調してきた。この
近縁性は星とシェルの相対光度比に及ぶ。極大時の J 平均値と L 平均値から
計算した (J-L)=2.48±0.12 はシェルの相対光度がファクター3以内に
収まることを示す。
|