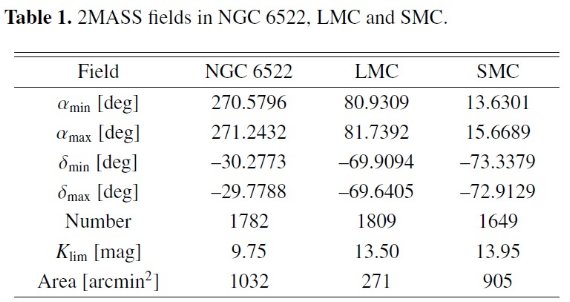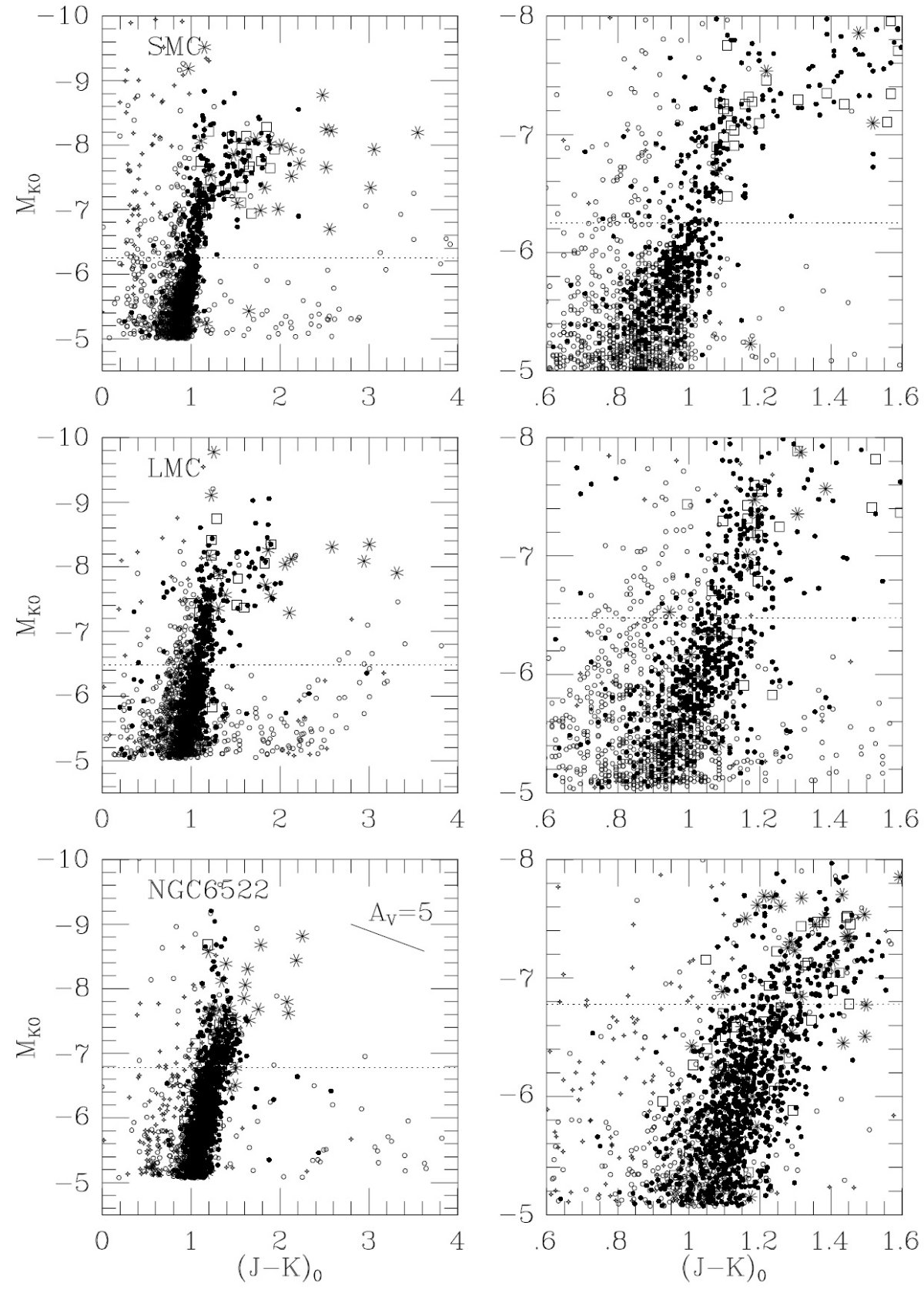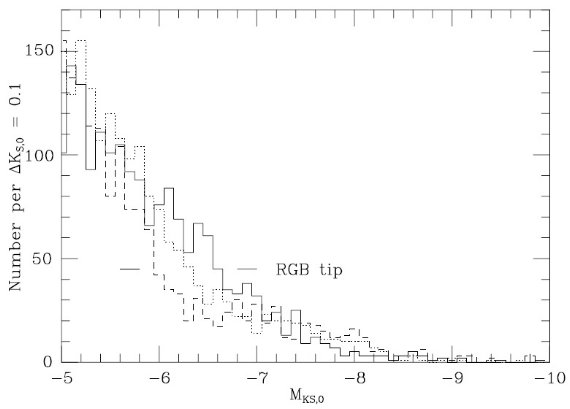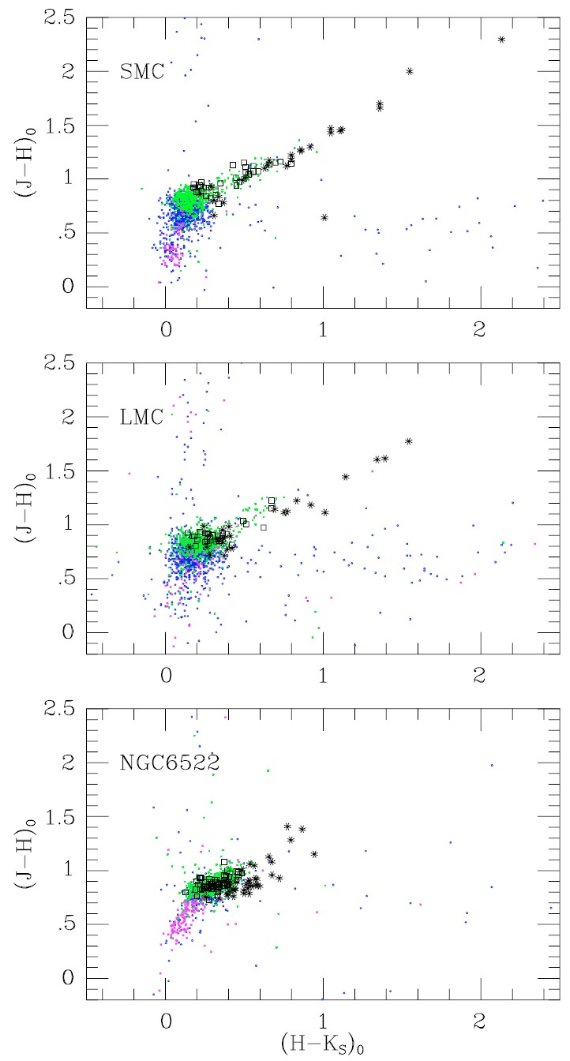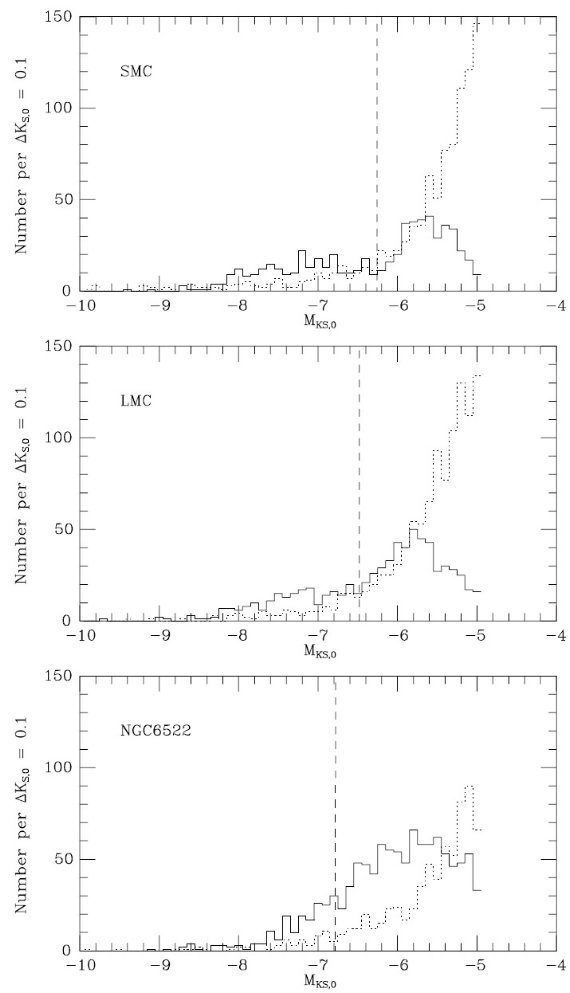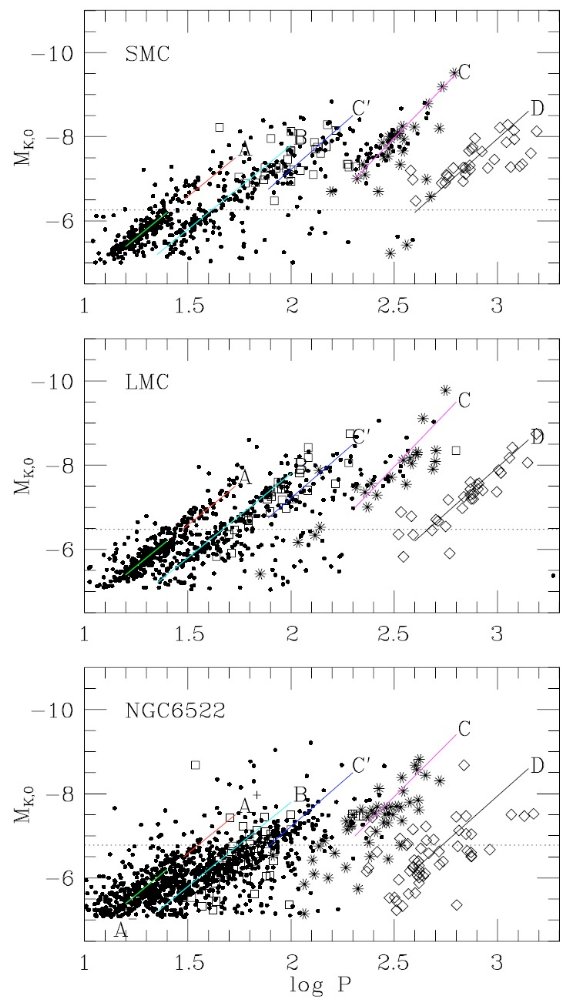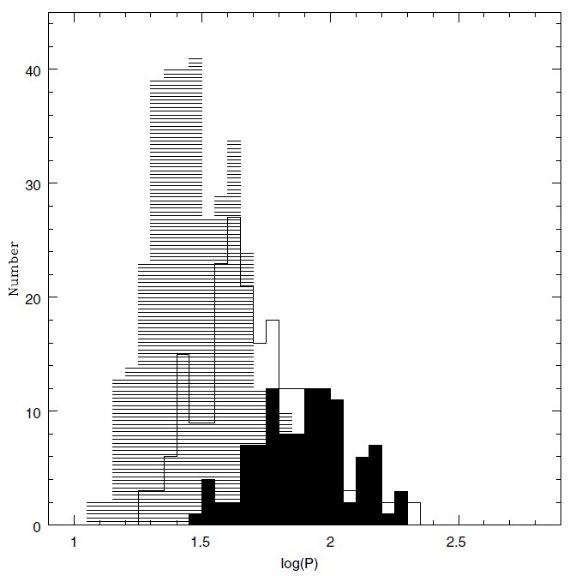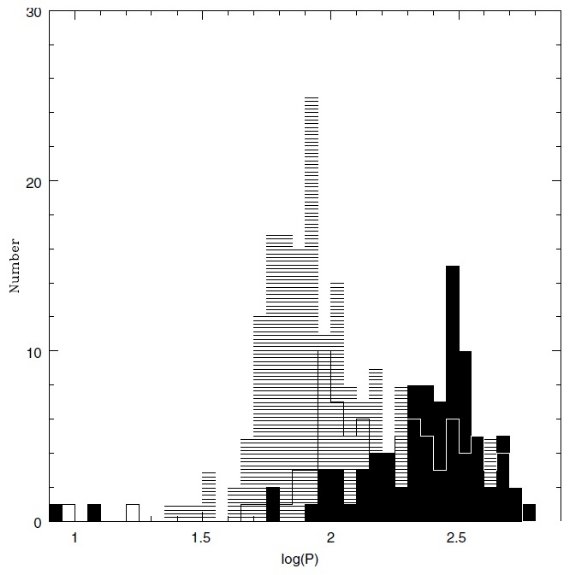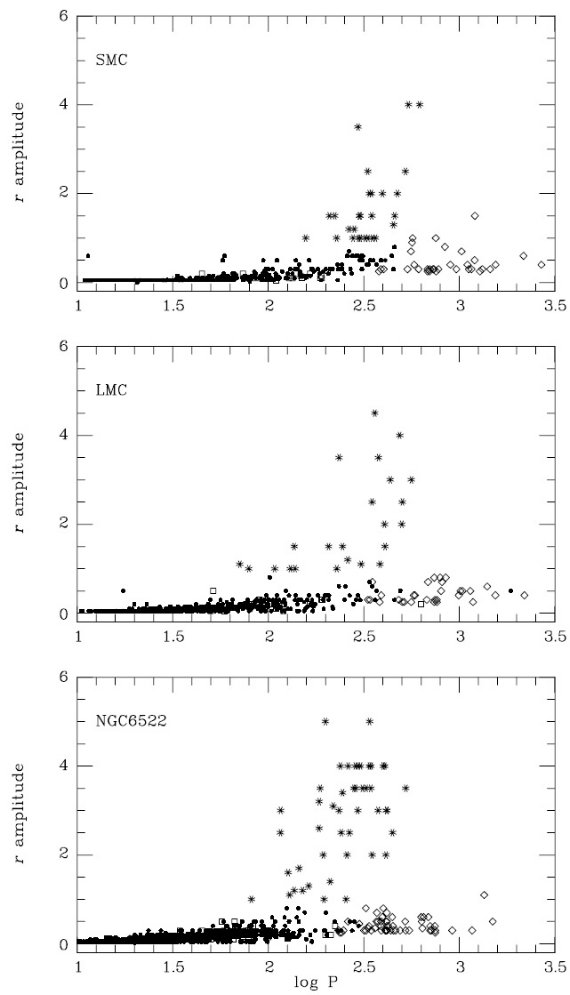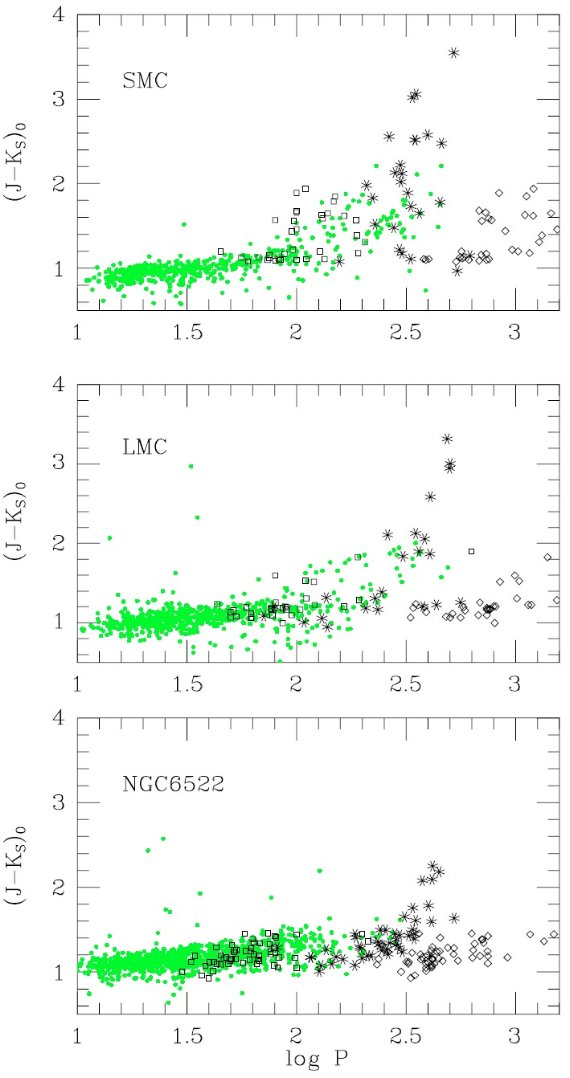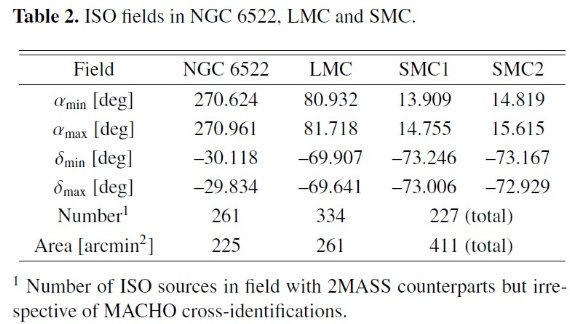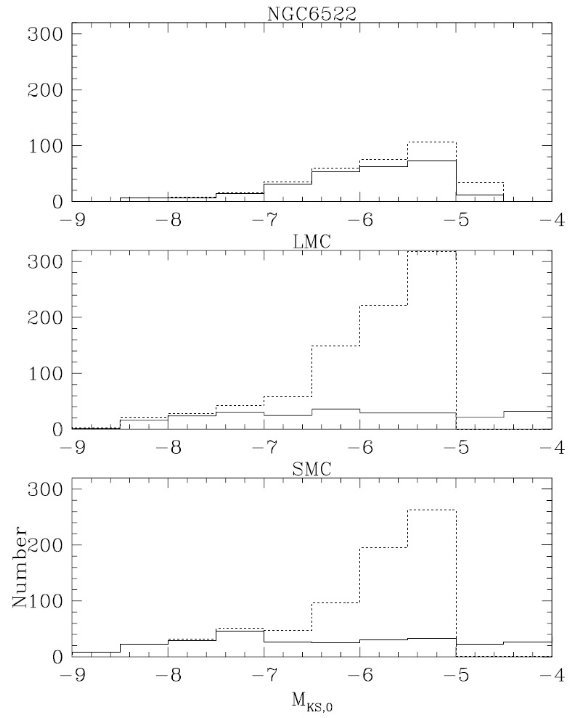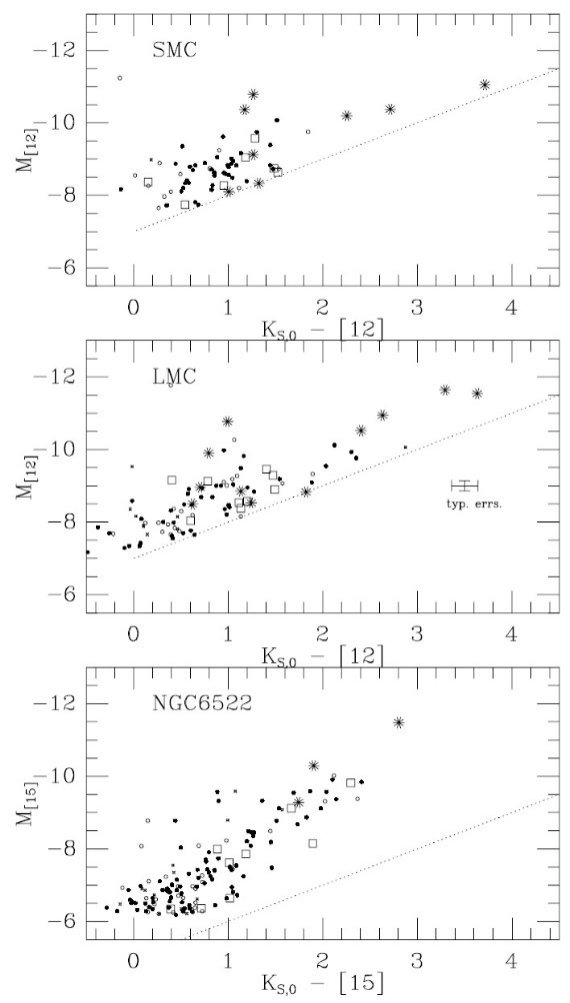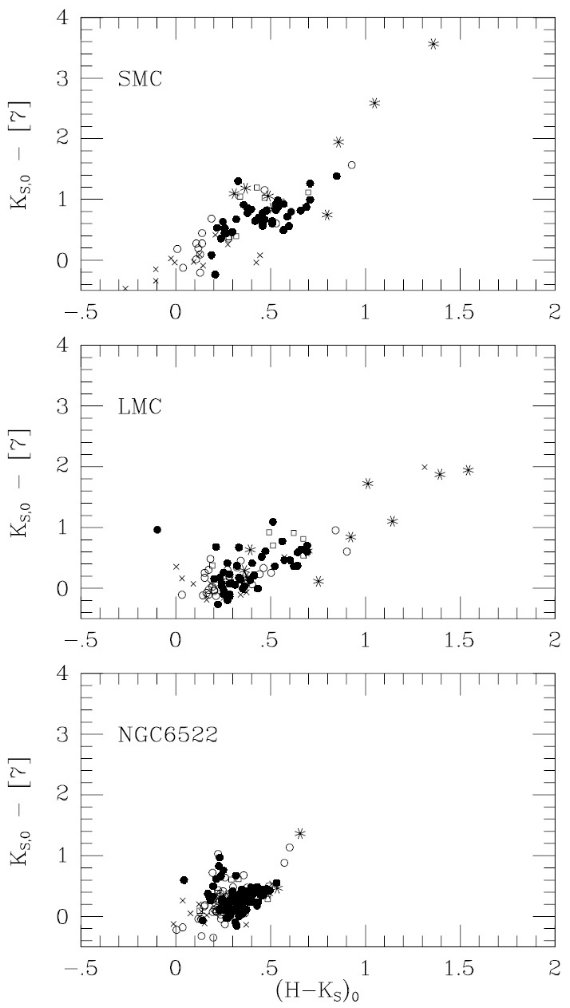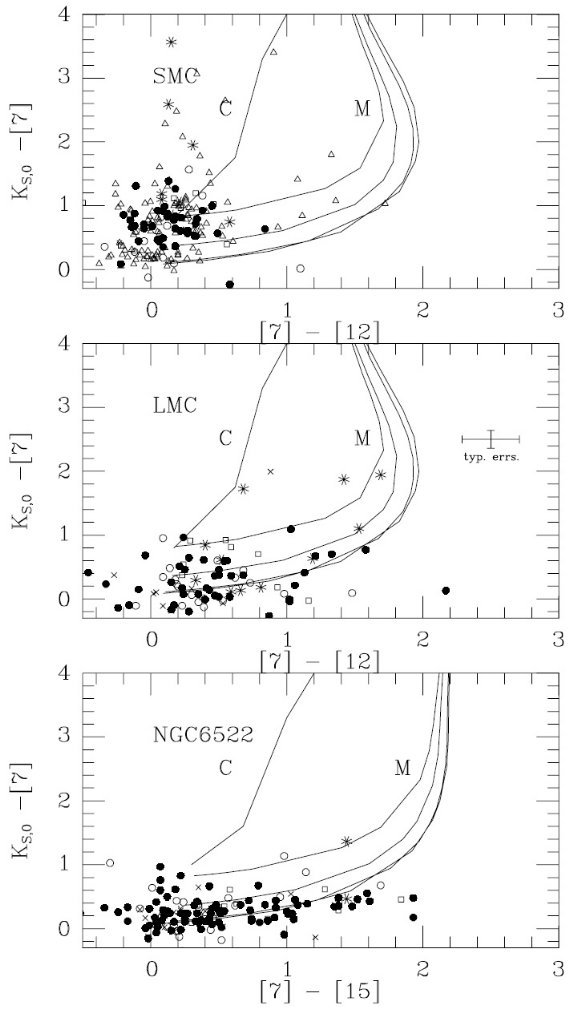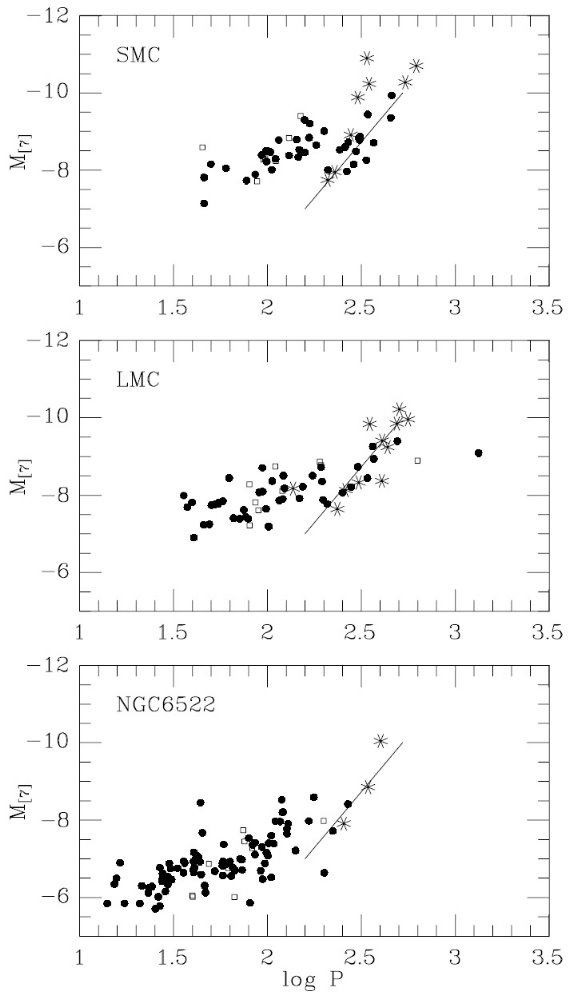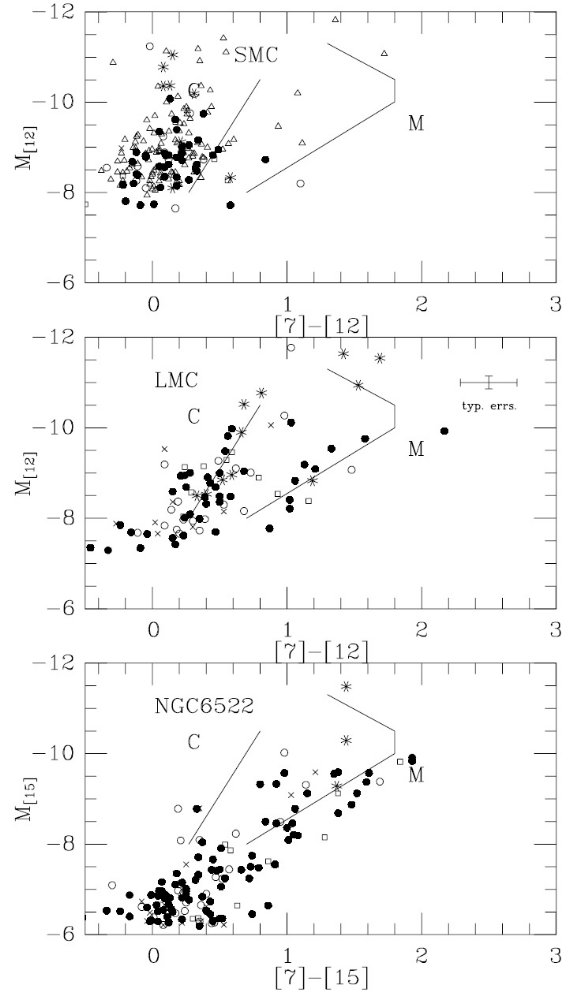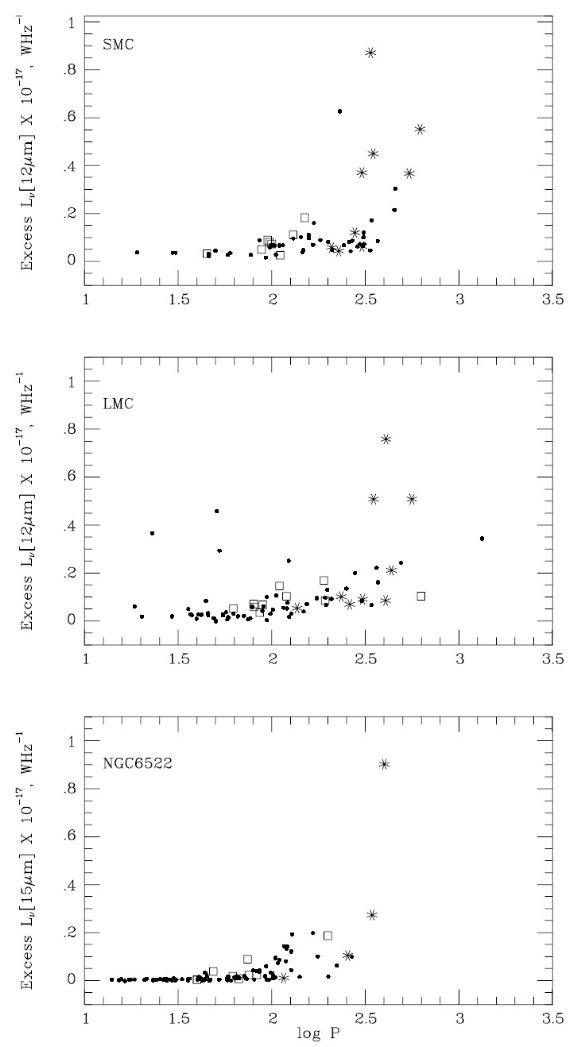3領域間の巨星枝カラーと先端等級のシフト
3領域の CMD を較べて最も目立つ特徴は、NGC6522, LMC, SMC の順に巨星
枝が青い方へ移って行くことである。Kiss, Bedding 2004 は RGB 先端等級
を LMC で MKs,o = -6.48, SMC で MKs,o = -6.26
とした。図2に示した Ks ヒストグラムを見ると、崖位置が SMC と LMC とで
0.3 等、LMC と NGC 6522 の間も同じくらいの差がある。
TRGB 等級
Ferraro et al 2000 によると、銀河系球状星団では、
MKoTip = -0.59[Fe/H] - 6.97
Ks2MASS と KSAAO の間には少し変換が必要である。
したがって、もし Kiss,Bedding 2004 の図を取って、NGC 6522 の RGB 先端が
LMC より 0.3 mag 明るいと仮定すると、NGC 6522 で [Fe/H] = -0.32,
LMC で [Fe/H] = -0.85, SMC で [Fe/H] = -1.22 というやや低い値となる。
RGBカラー
与えられた MK での (J-K)o もメタル量の指標となる。
MKs,o = [-5.25, -5.75] のカラーは NGC 6522 で 1.09, LMC で
0.99, SMC で 0.89 である。これらの値を Ferraro et al. 2000 の使用した
SAAO システムに変換するには、
(J-Ks)2MASS = 9.44 (J-K)SAAO - 0.005
すると SAAO システムでは、NGC 6522 で (J-K)SAAO = 1.16,
LMC で (J-K)SAAO = 1.05, SMC で (J-K)SAAO = 0.95
である。Terndrup et al. 1990 は内側バルジフィールド M 型巨星に対し
[M/H] = 0.2 を得た。LMC の t < 109 yr 星は [He/H] = -0.2,
SMC では -0.5 である。しかし、Feast et al 1989 は古い種族ではそれより
1 dex は低いとした。RGB 先端値から導かれるメタル量は約 0.4 dex 低い。
Ferraro00 から、[Fe/H] = -(M(Ko)+6.97)/0.59 なので、Ks=K として
SMC M(Ks)=-6.26, [Fe/H]=-1.20
LMC M(Ks)=-6.48, [Fe/H]=-0.83
NGC6522 M(Ks)=-6.78, [Fe/H]=-0.32
この値とどれが 0.4 dex の差になるか、わからん。
| |
図2.Ks,o ヒストグラム。崖= RGB 先端。実線=NGC6522, 点線=LMC, 破線=SMC.
とにかく
とにかく(?)メタル量の絶対値では外れているが、バルジと LMC,
LMC と SMC との間でメタル量が 0.4 - 0.5 dex 違うことについては
分光の結果と一致している。年齢効果が RGB 先端等級 M(K) = -5.5
からずらしている可能性がある。
(この -5.5 はどこに出てた? )
|