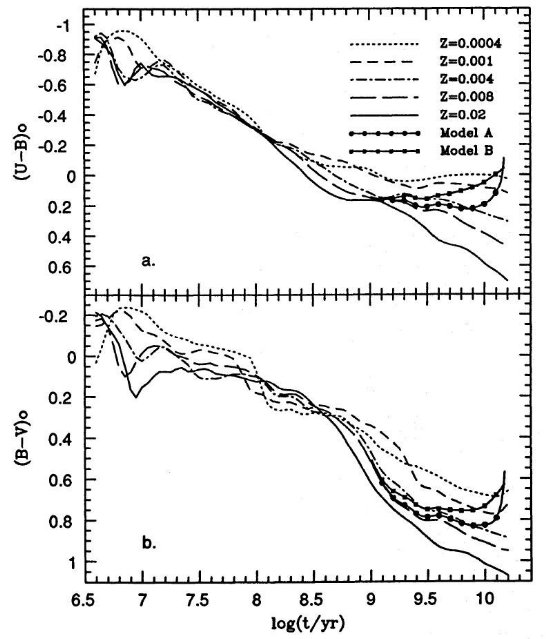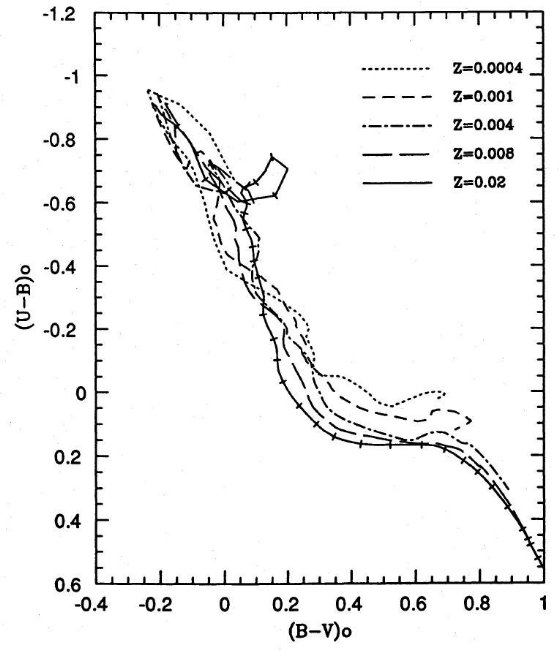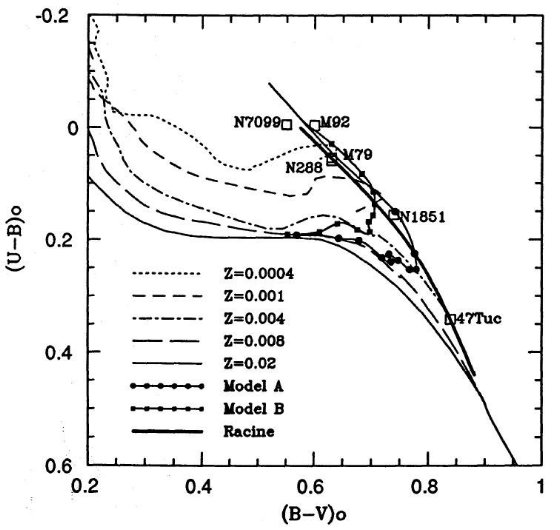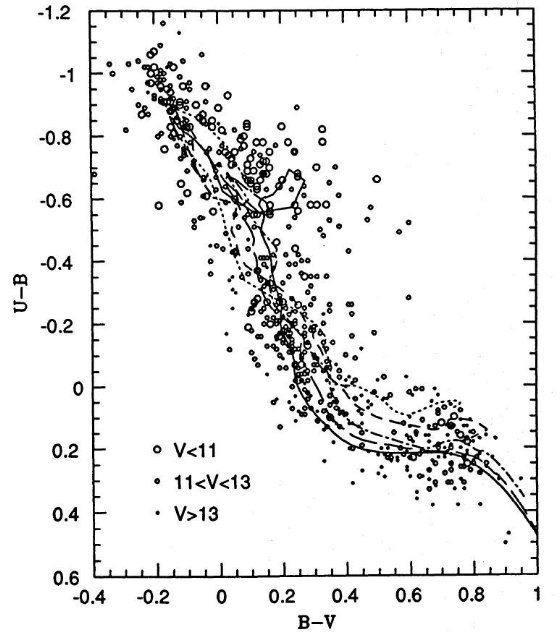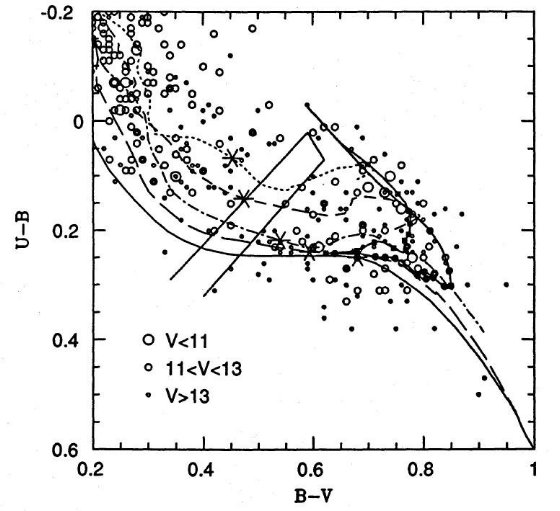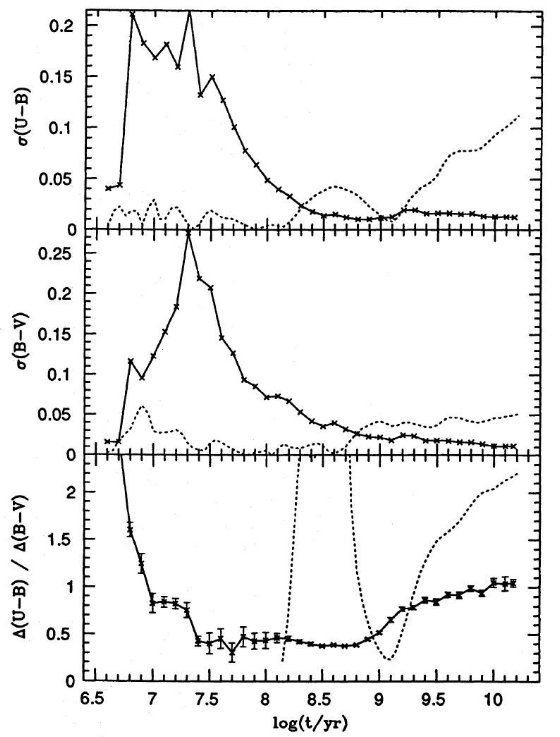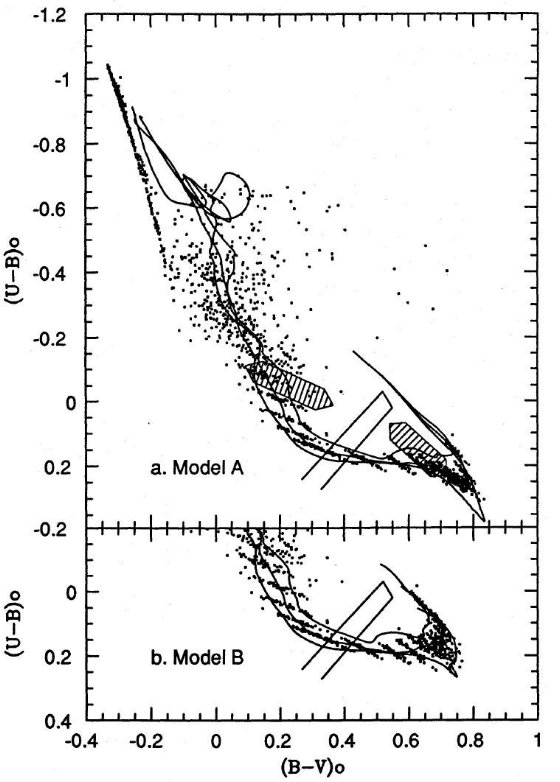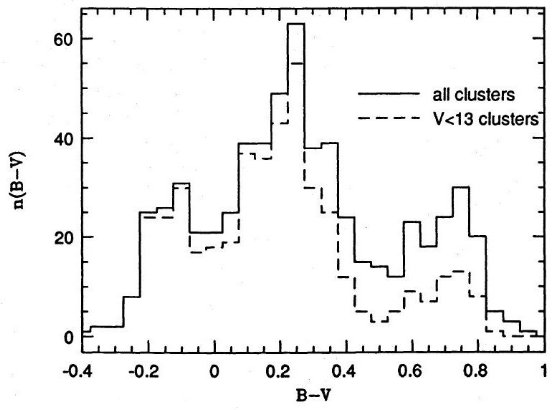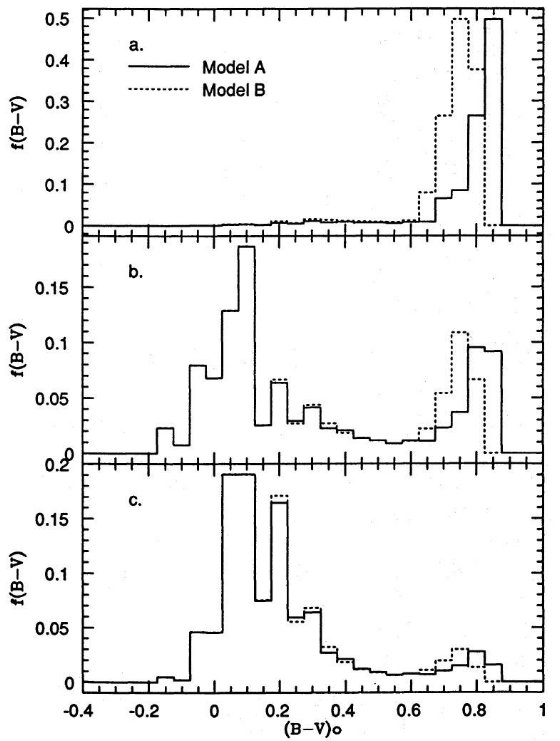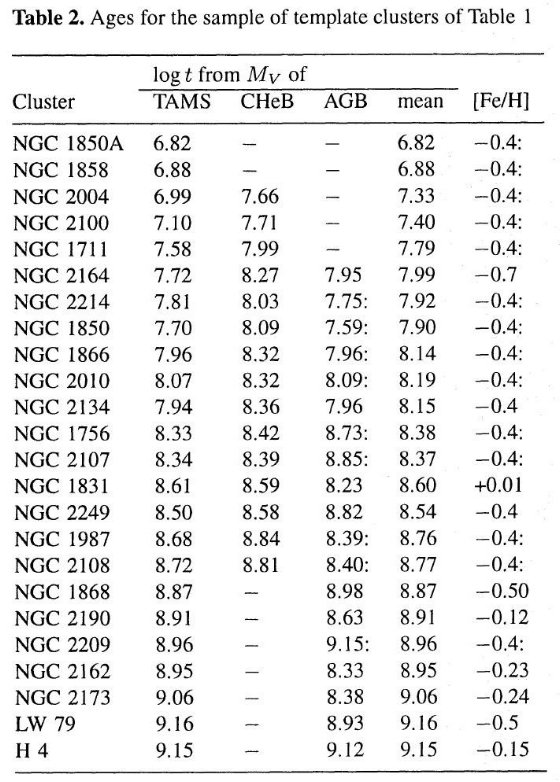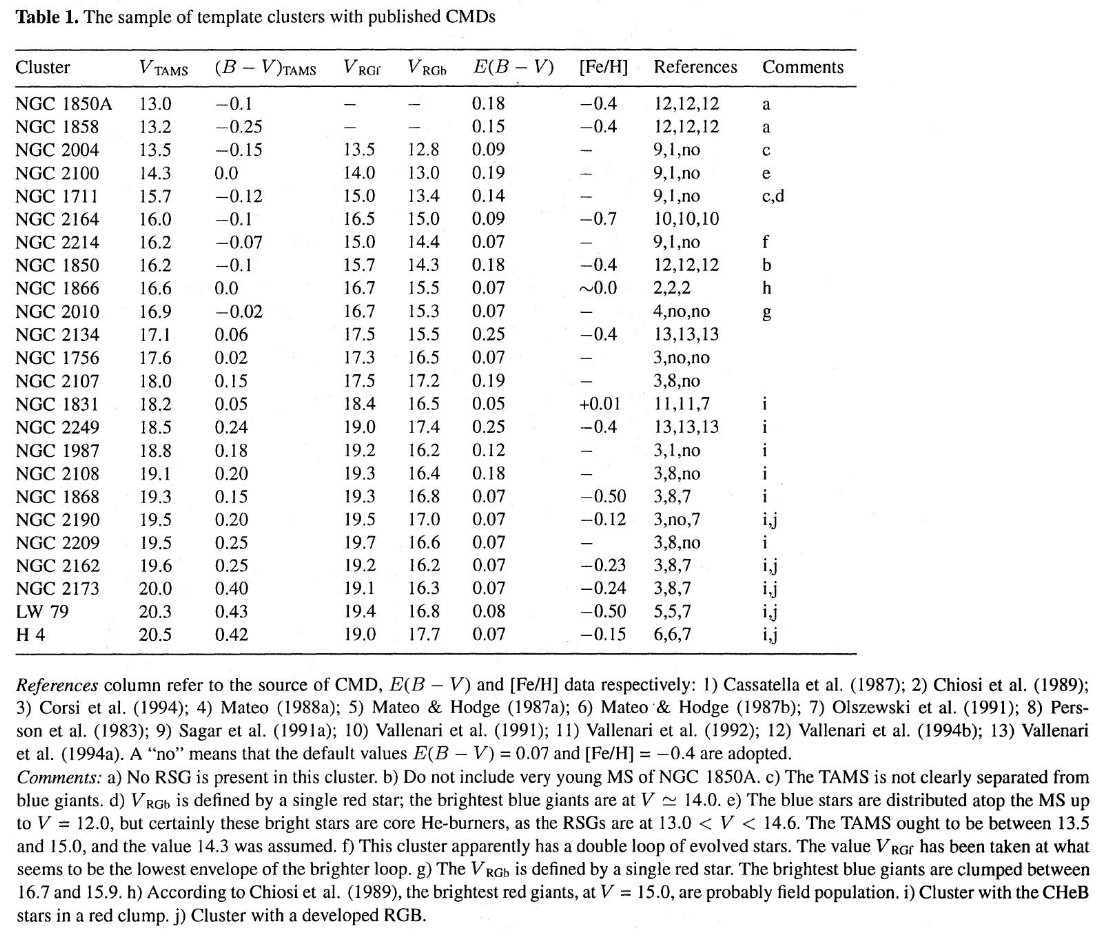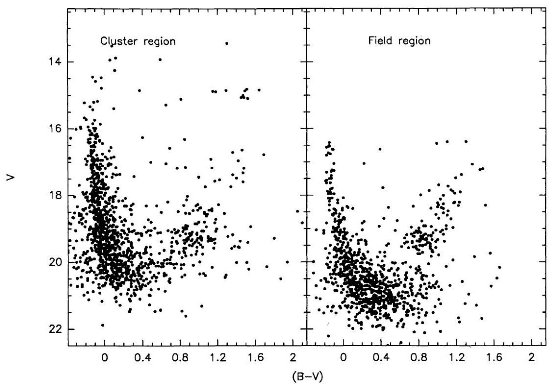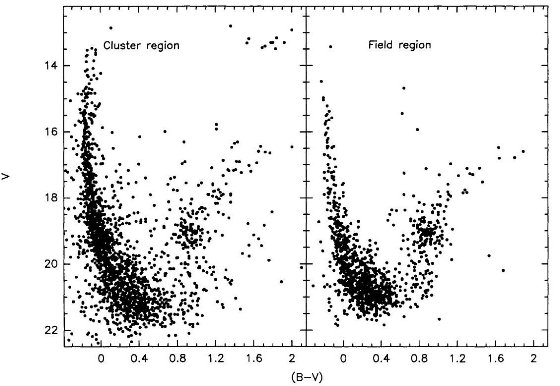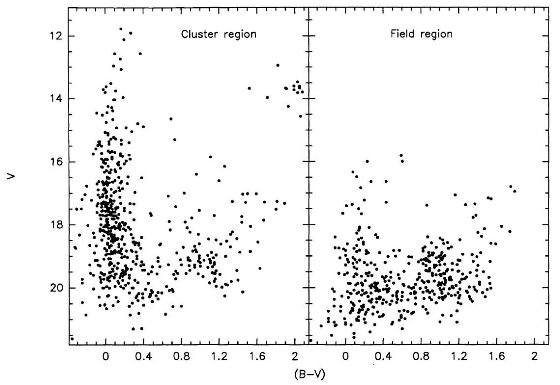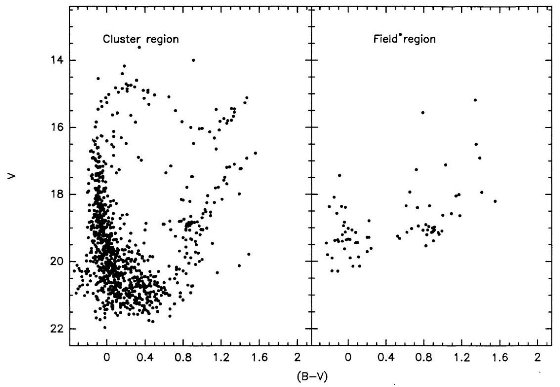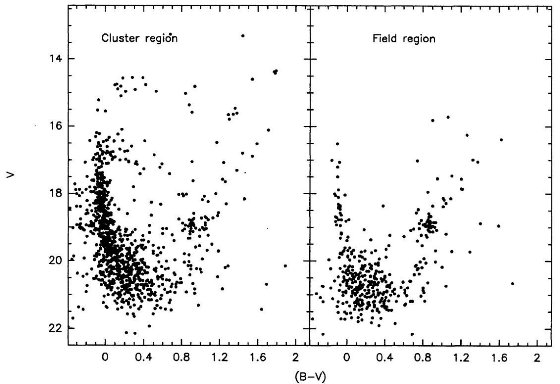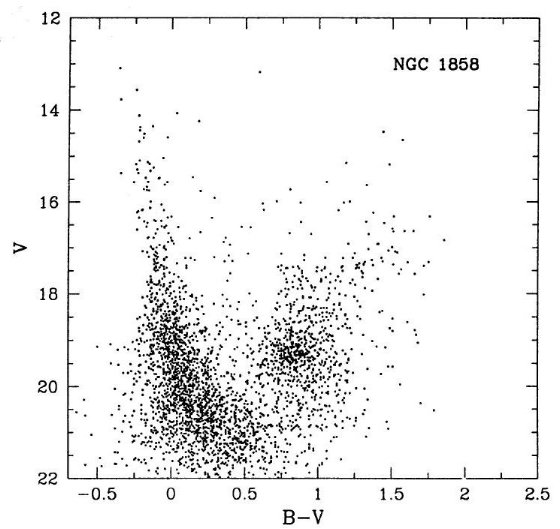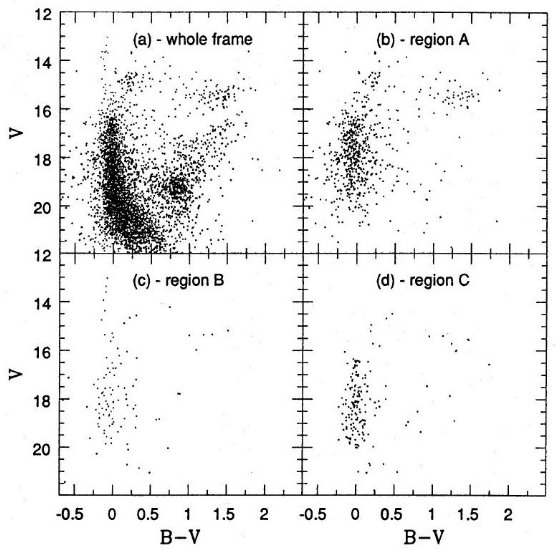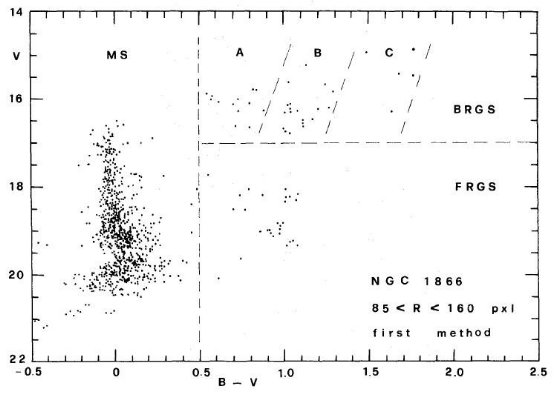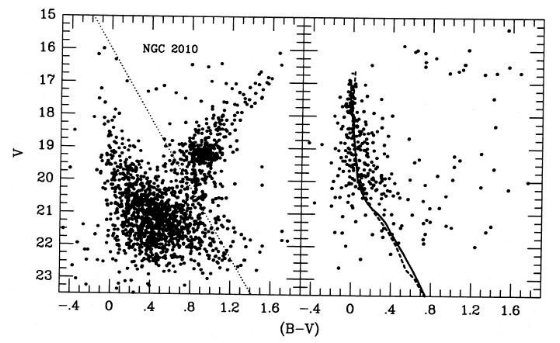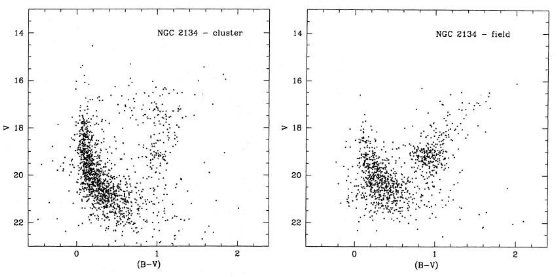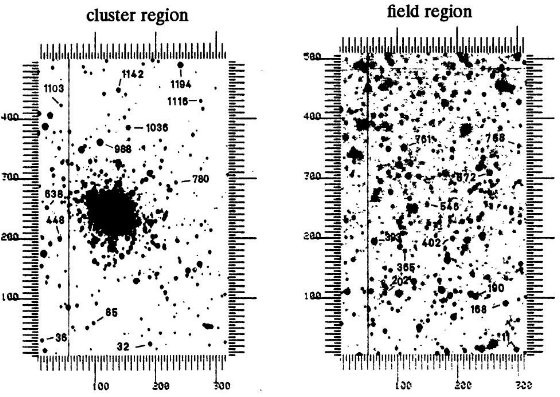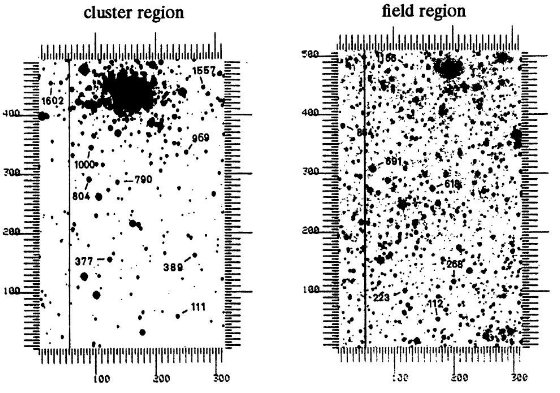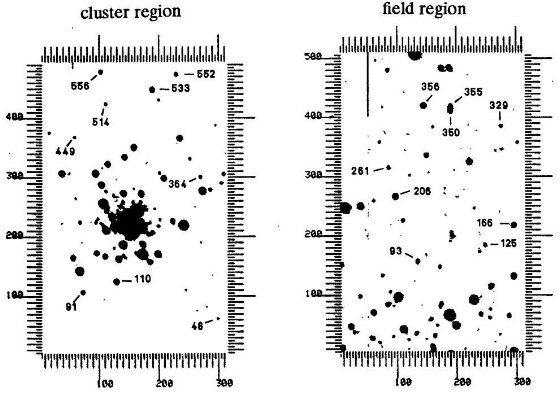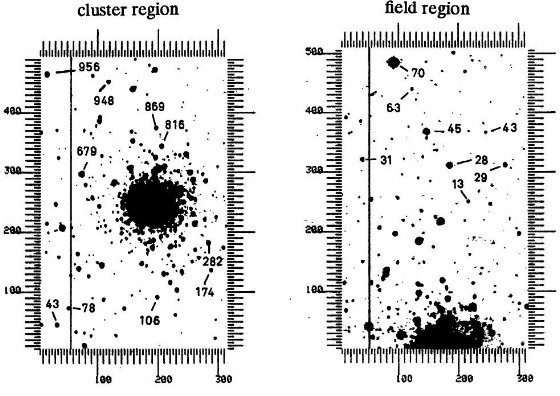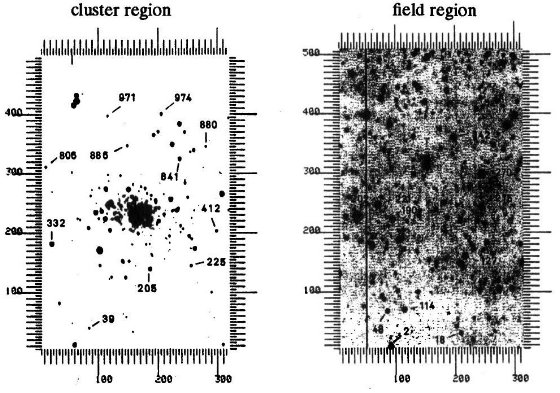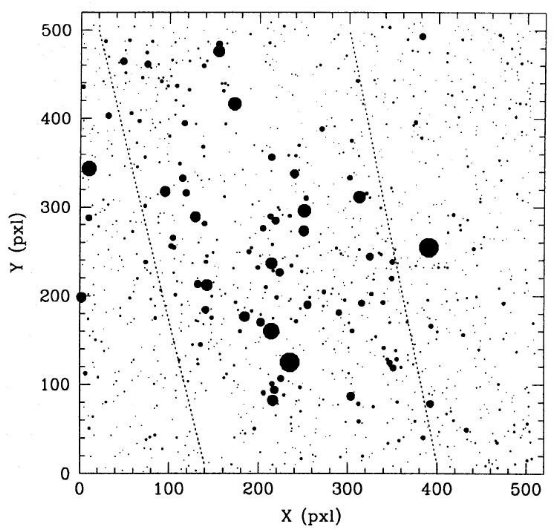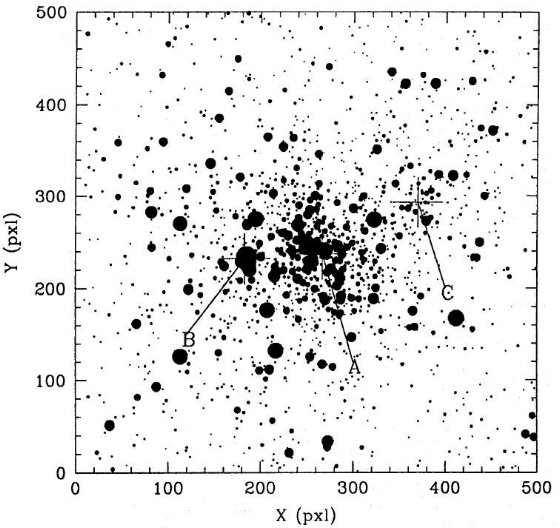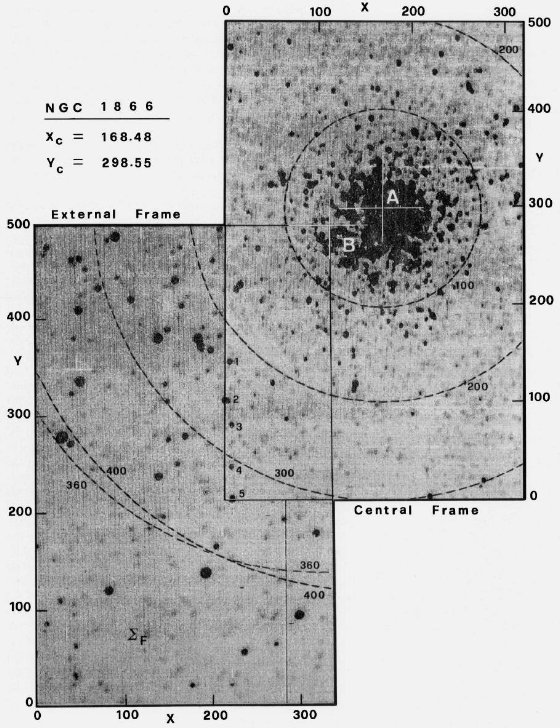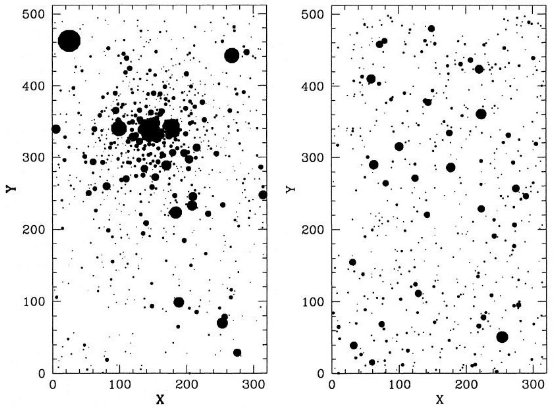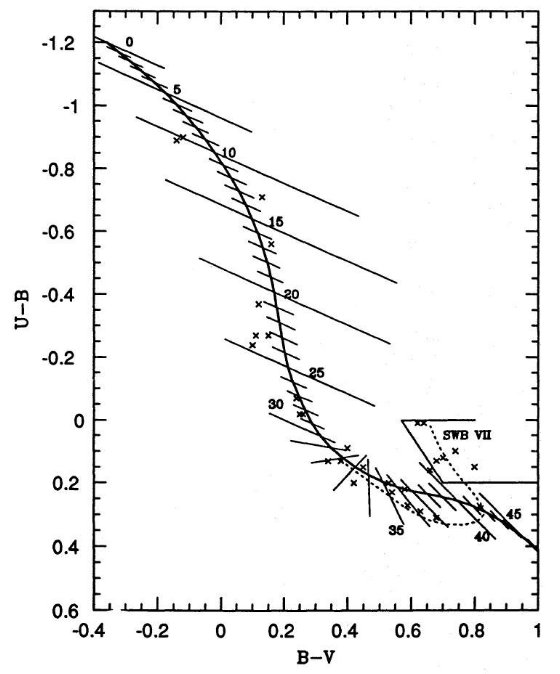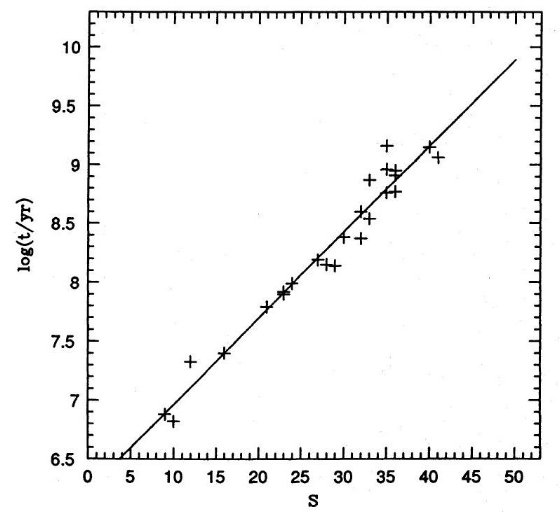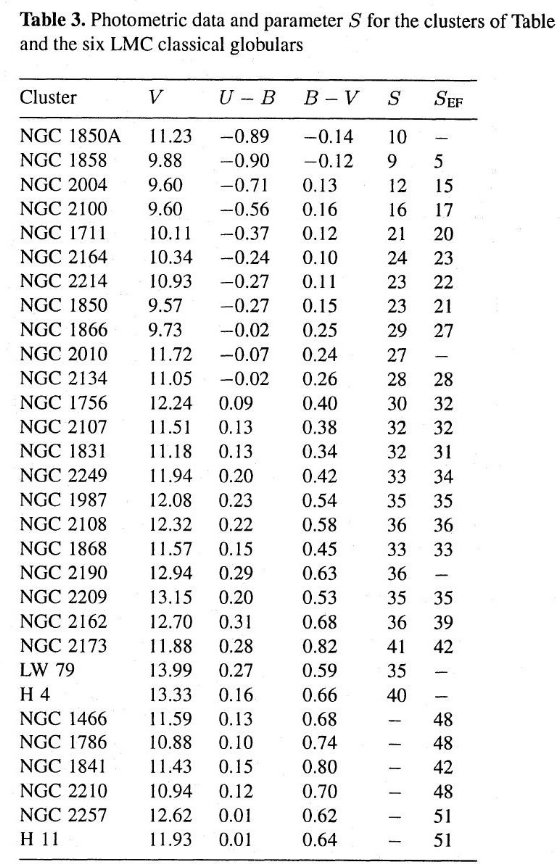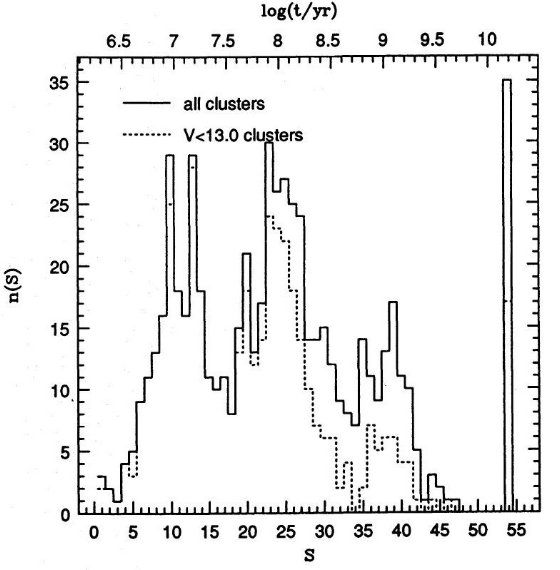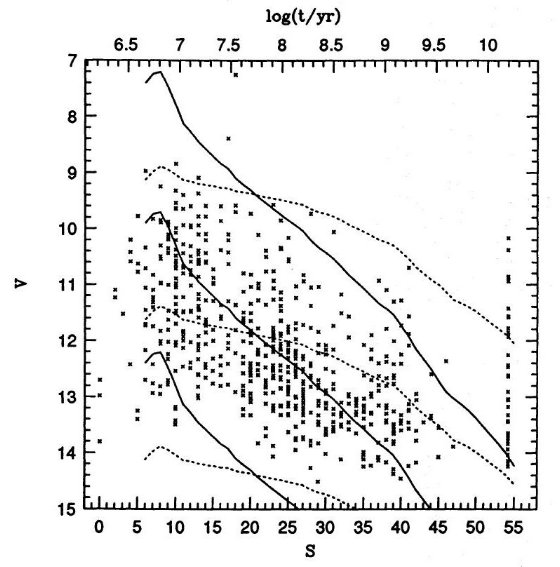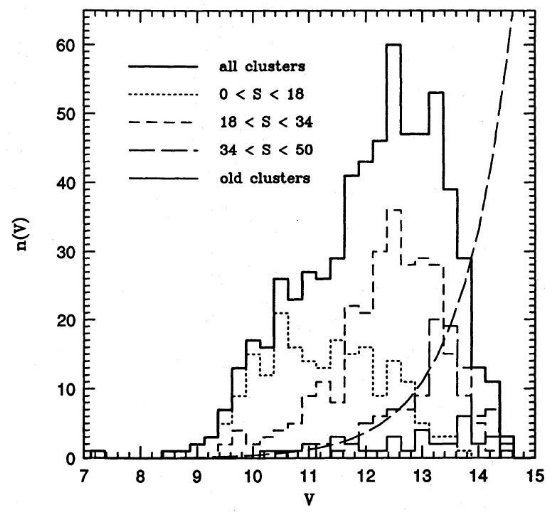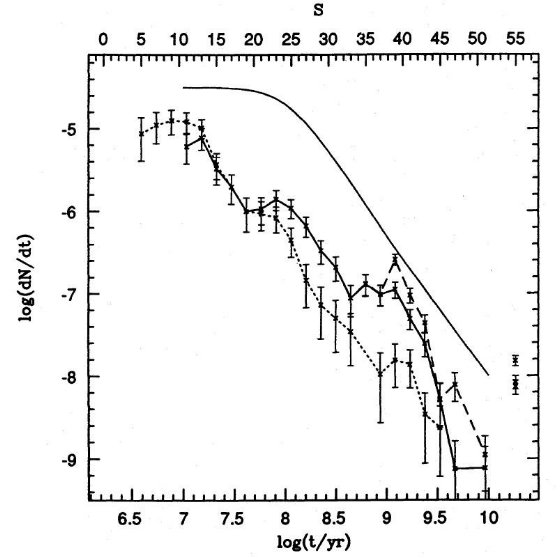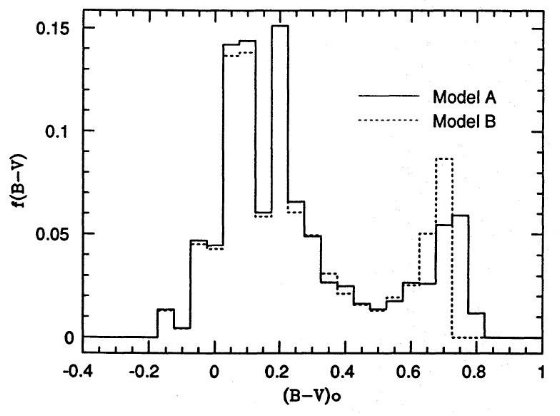7.1.Elson,Fall 1985 法の改良
EF85 法の不定性
有名な Elson,Fall 1985a で、彼らは積分 UBV カラーから年齢を求める
方法を与えた。ここに示したように実際の星団はそのカラーを分散させる
多くの影響を受ける。したがって、年齢だけでカラーが決まるわけではなく、
EF85 法には多くの不定性が含まれる。ここではそれを改良する2つの方法を
提案する。
Sの意味
既に 2.1.節に述べたが、(U-B, B-V) 面上での SSP のカラー進化は
log t で測って一定のスピードで変化する。これは太陽メタル量付近では特に
そうであり、例外は 107 年付近での赤色超巨星出現のあたりのみ
である。したがって、EF85 の経験的な方式が成功したのは当然であった。
もし我々が (U-B, B-V) 図を等しい大きさの区間(パラメターS)で区切れば
単純な線形関係が S と log t との間に成立するであろう。
Sは古い星団に弱い
しかし、 EF85 には、星団の年齢が変わるとメタル量が変わることを考慮
すると、大きな欠点がある。古い星団では S と log t の間の線形関係は
成立しなくなる。これは図1、図3のモデルAとBを見ると分かる。古い
星団は小さな log t の間にカラーの大きな変化を示している。実際、カラー
の内在的分散を入れると、この系列の星団は全て同年齢と言ってよい。
このように古い星団のSパラメターを並べることは、同一年齢でメタル量の
増加して行く順を示すもので、同一メタル量で年齢の増加していく系列と
考えるべきでない。この年齢領域の星団には S 法は信頼できる年齢を与えない。
Sがギャップを表わさない理由
EF85 で導入された S は 3 Gyr - 12 Gyr のギャップを表わしていない。これは
Sが大きな星団をつなぐラインに沿って決められたからである。5−2節で
述べたように、年齢ギャップは (U-B, B-V) 面上では見えない。これが EF85 が
van den Bergh 1981 サンプルでは、ギャップも星団の爆発的形成もないと述べた
原因である。
7.2.Sパラメターの定義
新しいS系列
先の議論から我々はS系列を定義し直すことにした。EF85 と異なり、E-SWB VII
の古い星団はこのSパラメター法の適用から外す。それらは CMD から全て古典的な球状星団
(van den Bergh 1991) とされている。それらに対しては一律に log t = 10.2 (15Gyr) とする。
Sパラメターを導くやり方は次の通りである。
(1)EF85 図10のSカーブを Z = 0.008 の SSP 経路(図4)と比較する。
B-V < 0.5 では 2本のカーブが一致していることが分かる。
B-V > 0.5 では 2本のカーブは大きく離れる。
(2)EF85 のSカーブは E-SWB V 型星団、NGC 2190, NGC 2162, NGC
1806、の下側をなぞっている。それに対し、SSP Z = 0.008 カーブは、
E-SWB V 型星団の平均値を貫いている。そこには他の星団 NGC 1783,
NGC 1644, NGC 2154 がそんざいする。
(3)5-4節で議論したように、V, VI 型の分散方向は Δ(U-B)/Δ(B-V) ∼ 1
したがって、我々は E-SWB V, VI 星団の分布を Z = 0.008 系列からの
分散として解釈したい。これを B-V = 0.8 まで妥当と考える。
| |
(4)この先 Z = 0.008 系列は U-B が増加し続ける。しかし、S カーブの細
かい形は重要でない。その辺には星団がほとんど無いからである。
(5)最終的に採用する S カーブは B-V < 0.5 では EF85 カーブ、その先
0.8 までは SSP Z = 0.008 を使う。合成ラインを図10に示した。
星団にS値を付ける
Sカーブ上にない星団からは分散の方向に線を延ばして、カーブとの交点をその
星団の S とする。分散方向の傾きは、青い星団で Δ(U-B)/Δ(B-V) ∼ 0.45
青い星団では 1 である。S = 30 - 36 では分散の方向が S カーブと平行なので
特別の注意が必要である。そこでは星団に S 値を付けることが難しい。
同様の困難は非常に若い ( ∼ 107 yr ) 星団でも起きる。そこ
ではストカスティックな過程で大きな分散が起きる。
カラー分散の方向が S カーブに直交していないという効果を無視すると、
赤い方に分散した星団の年齢を過大に評価し、青い方に分散した星団の年齢を
過小に評価するだろう。van den Bergh 1981 データにこの方法を適用すると、
古い方法の時と同じような年齢を与えるだろう。それはこのサンプルはカラー分散
がほとんど無いからである。対称的に BCDSP データにはかなりの違いをもたらす。
図10 採用したSパラメター。クロスは年齢較正に用いた星団。
SWB VII と名付けた領域には非常に古い星団が存在する。
|