地球接近天体2012 TC4
2012 TC4は2012年10月にハワイにあるPan-STARRS望遠鏡によって発見された小惑星です。光度から大きさは10-30mほどと推定されています。2013年2月にロシア チェリャビンスクに落下し、広範囲にわたって人的被害をもたらした隕石と同程度の大きさです。2012 TC4は日本時間2017年10月12日14時42分(日本の昼間)に地球に最接近します。最接近時の距離は約50,000km(地球中心と2012 TC4の中心の間の距離)と推定されています。これは、地球と月までの距離のおよそ13%(月軌道の内側)に相当します。2012 TC4のような直径10m以上の小惑星は、地球大気に突入した際に燃え尽きずに地表に到達するためチェリャビンスク隕石のような災害をもたらします。そのため、直径10m以上の小惑星は監視を重視すべき天体とされています。月軌道の内側を通過する直径10m以上の小惑星は、1年間に5件程度が確認されています。今後の観測により、この数は増加する可能性があります。2012 TC4のような直径10m以上の小惑星が地球に衝突した場合には、市民生活・経済活動に甚大な影響を与える可能性があります。一方で落下地点が事前にわかれば避難することで被害を最小限に抑えることも可能です。今回の2012 TC4の観測は、2012 TC4の未来の軌道を精度良く決定することに加え、衝突危険性のある天体の軌道を正確にもとめる技術を獲得する観点でも重要な取り組みと言えます。
観測装置
木曽観測所は東京大学大学院理学系研究科付属天文学教育研究センター(本部 東京都三鷹市)が運用する天文観測施設です。広い視野を特長とする口径105cmシュミット望遠鏡が主力望遠鏡です。 105cmシュミット望遠鏡の観測視野は日本が保有する他の望遠鏡を圧倒しており、今回のような空を高速に移動する天体の観測や、新しい天体現象を見つけるために空を広く探査する目的に適しています。現在、木曽観測所では105cmシュミット望遠鏡の広い視野(Φ9度、焦点面にてΦ52cm)のすべてを84台のCMOSイメージセンサで覆う超広視野高速カメラ「トモエゴゼン」の開発を2018年完成予定で進めています(リンク)。2017年10月3日には、カメラ筐体に4台のCMOSセンサを搭載した試験機がファーストライト観測に成功しました(リンク)。今後、1年間をかけて段階的にCMOSセンサの数を84台にまで増やしていきます。トモエゴゼンは105cmシュミット望遠鏡との組み合わせにより、動画観測において国内最高感度の広視野観測を実現します。従って、2012 TC4のような空を高速で駆け抜ける微弱な天体を捉えるのに最適な観測装置と言えます。トモエゴゼンの本格稼働により、今後、多くの未発見の地球接近天体が見つかると期待されています。
取得した画像データ
東京大学木曽観測所が保有する口径105cmシュミット望遠鏡に広視野高速カメラ「トモエゴゼン」を搭載して、2012 TC4の通過予想天域を観測しました。取得した画像データをまとめます。
2017年10月11日のデータ
2012 TC4の通過予想天域(みずがめ座)を日本時間2017年10月11日20時40分36秒--21時04分36秒に観測しました。2秒露光の画像を720枚連続で取得しました。光学フィルタは使用せず波長400--650nmの可視光で観測しました。2012 TC4の明るさは約15.5等級でした。2012 TC4は見かけの移動速度=35秒角/分で南西の方角へ移動していきました。2012 TC4は約12.4分の周期で回転していることが知られています。今回の観測データでも2012 TC4の明るさが周期的(約12.4分周期)に変動する様子がとらえられました。取得したデータの一部をトリミングした画像を以下に置きます。トリミング画像の視野中心は赤経22時42分10.0秒、赤緯-7度23分9.9秒です。トリミング画像の視野サイズは17分角 x 9.53分角で、画像の上が北の方角です。本データ取得時の「地球中心」と「2012 TC4の中心」の間の距離は約420,000kmと推定されます。
- 動画データ
- 720枚の2秒露光画像からなるタイムラプス動画。総観測時間は24分間。x200倍速で再生。
- 動画の左上から右下へ移動する点源が2012 TC4。
- 移動する点源の明るさが周期的(約12.4分周期)に変動していることがわかります。
- 静止画データ

- 動画データを32秒毎に切り出して重ねた画像
- 2012 TC4の光跡を直線に並ぶ点源の集まりとして確認できる
2017年10月10日のデータ
2012 TC4の通過予想天域(みずがめ座)を日本時間2017年10月10日21時56分32秒--22時56分32秒に観測しました。10秒露光の画像を360枚連続で取得しました。光学フィルタは使用せず波長400--650nmの可視光で観測しました。2012 TC4の明るさは17等級でした。2012 TC4は見かけの移動速度=9秒角/分で南西の方角へ移動していきました。2012 TC4は約12.4分の周期で回転していることが知られています。今回の観測データでも2012 TC4の明るさが周期的(約12.4分周期)に変動する様子がとらえられました。取得したデータの一部をトリミングした画像を以下に置きます。トリミング画像の視野中心は赤経22時53分16.5秒、赤緯-4度4分40.8秒です。トリミング画像の視野サイズは17分角 x 9.53分角で、画像の上が北の方角です。本データ取得時の「地球中心」と「2012 TC4の中心」の間の距離は約980,000kmと推定されます。
- 動画データ
- 360枚の10秒露光画像からなるタイムラプス動画。総観測時間は1時間。x200倍速で再生。
- 動画の左上から右下へ移動する点源が2012 TC4。
- 動画の後半に流れる光跡は人工衛星もしくは流れ星。
- 動画の後半に全体を白く覆うパタンは視野を横断する薄雲。
- 移動する点源の明るさが周期的(約12.4分周期)に変動していることがわかります。
- 静止画データ

- 動画データを110秒毎に切り出して重ねた画像
- 2012 TC4の光跡を直線に並ぶ点源の集まりとして確認できる
- 画像右中央に確認できる光跡は、既知の小惑星1999 DB1(直径2.9km, 距離1.85億km)参考資料
クレジット
本サイトの画像を使用する場合は「東京大学木曽観測所」と併記してください。 例)画像提供: 東京大学木曽観測所
内容に関する問い合わせ
-
東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター・助教
科学技術振興機構さきがけ研究員(併任)
トモエゴゼン計画研究代表
酒向重行(さこう しげゆき)
sako
 ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0422-34-5163
ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0422-34-5163
-
東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター・特任助教
大澤亮(おおさわ りょう)
ohsawa
 ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0422-34-5163
ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0422-34-5163
- 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所・広報事務担当
森由貴(もり ゆき)
moriyuki
 kiso.ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0264-52-3360
kiso.ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0264-52-3360
- 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター三鷹本部 0422-34-5021
- トモエゴゼン計画は以下の研究機関との共同研究です。
東京大学大学院理学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センター、国立天文台、JAXA、東北大学、甲南大学、神戸大学、統計数理研究所、日本スペースガード協会、日本流星研究会 - トモエゴゼン計画は以下の企業の協力を得ています。
キヤノン株式会社(高感度35mmフルHD CMOSセンサ)、株式会社インタフェース(光通信機器) - トモエゴゼン計画は以下の機関より予算補助を受けています。
日本学術振興会、科学技術振興機構、国立天文台
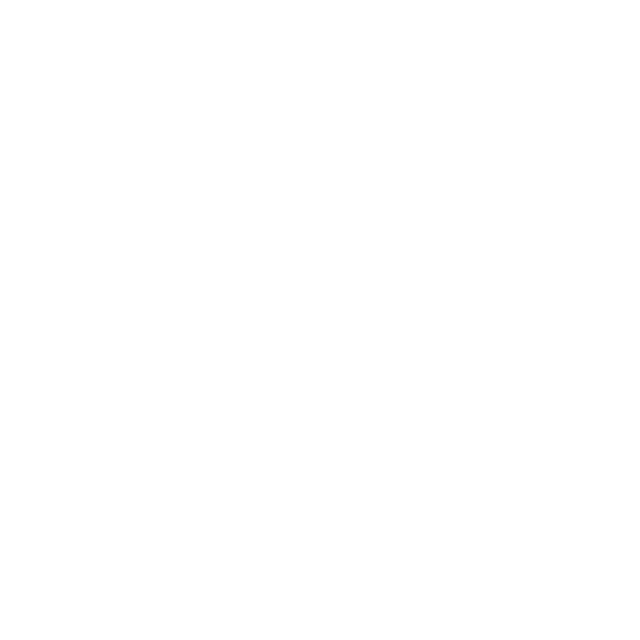 the Tomo-e Gozen project
the Tomo-e Gozen project