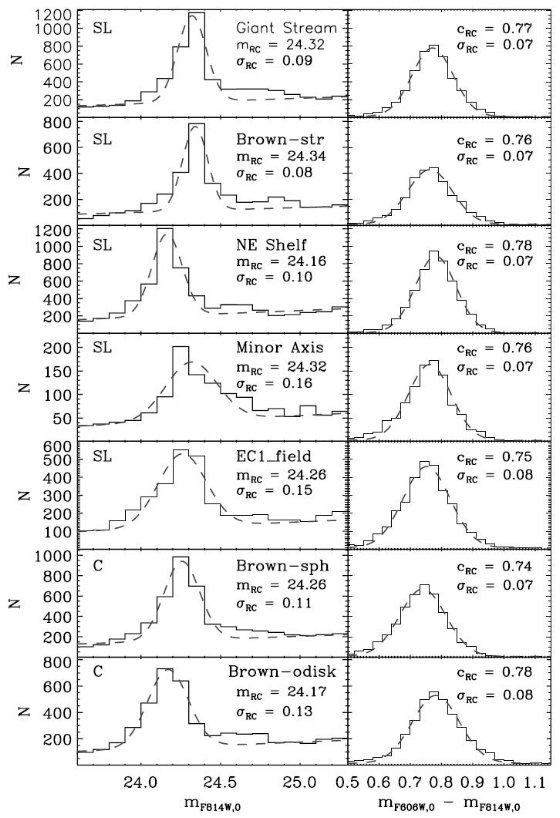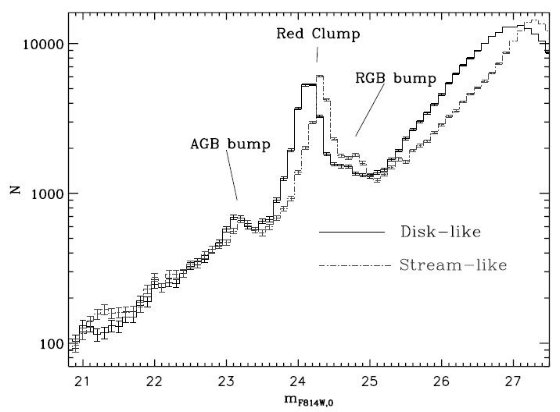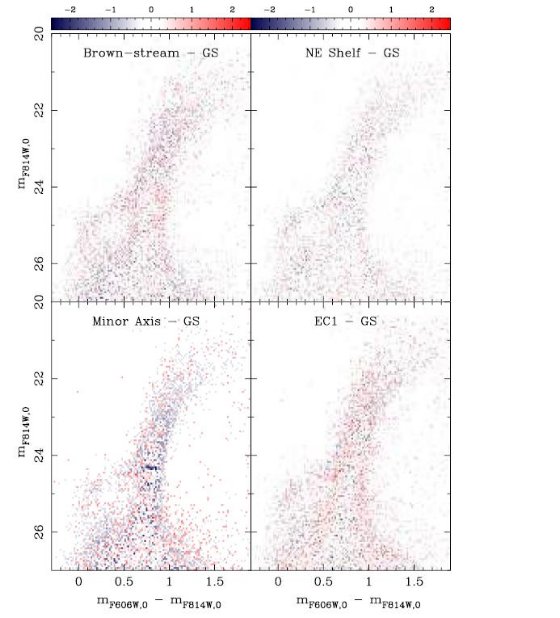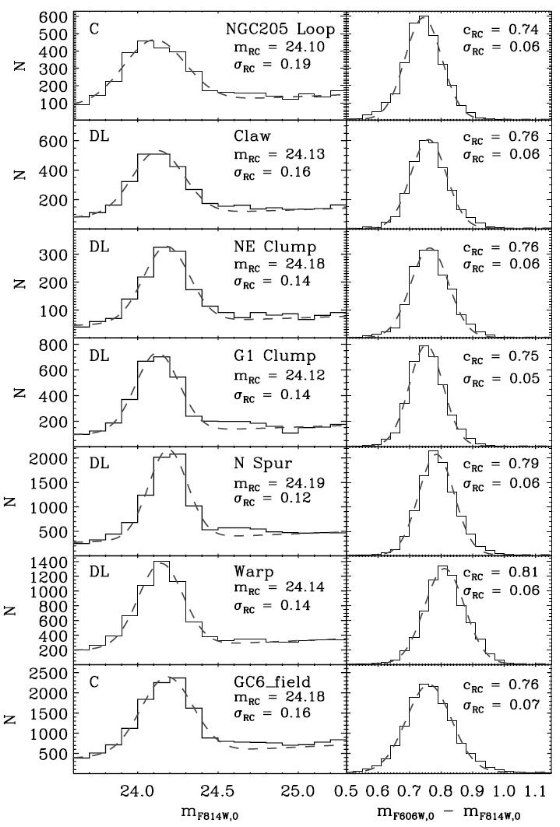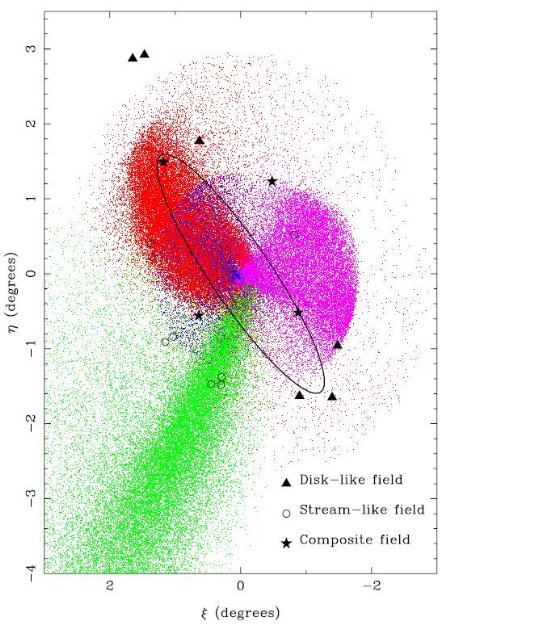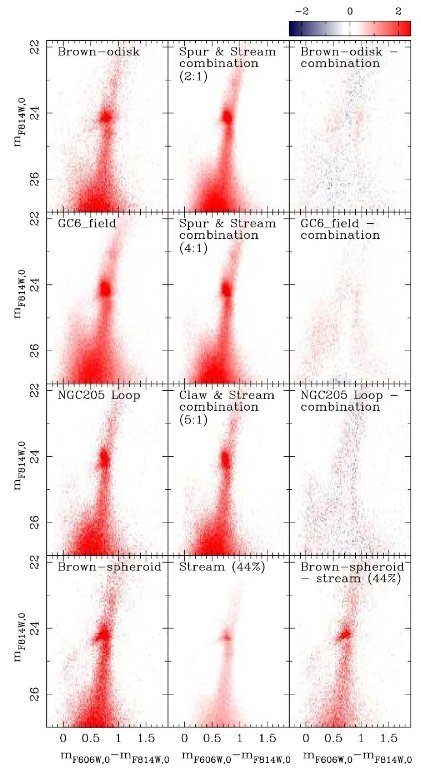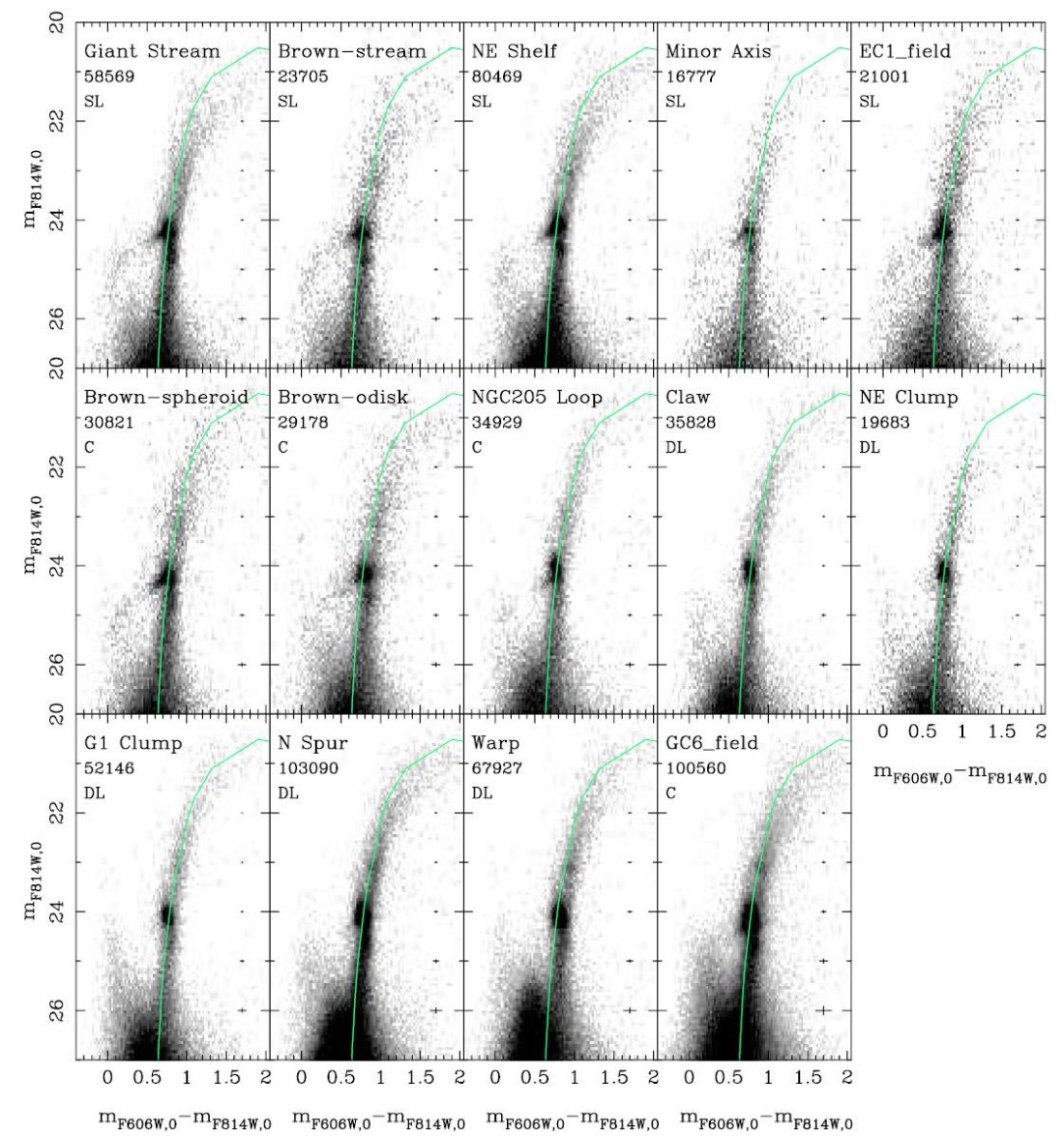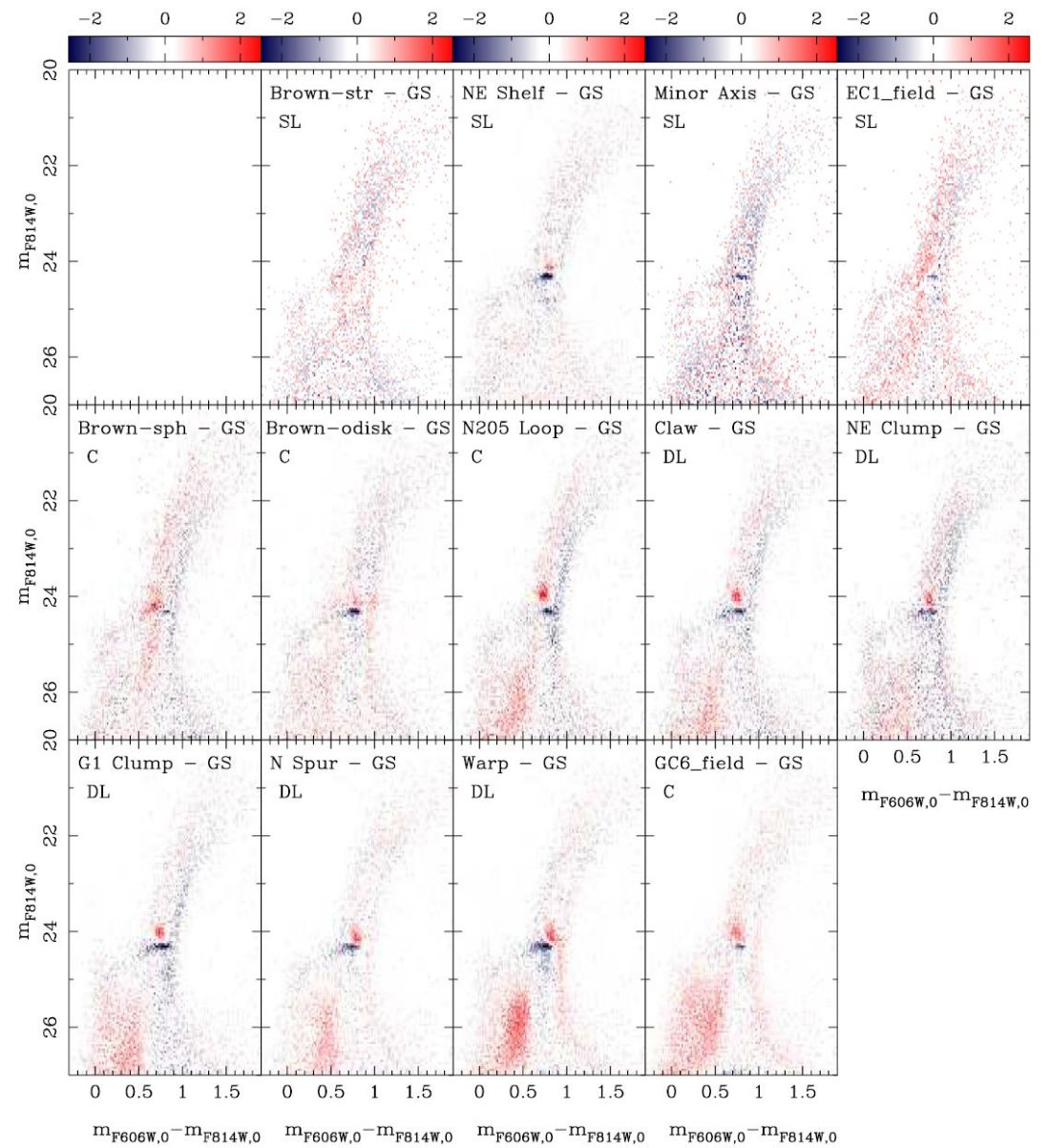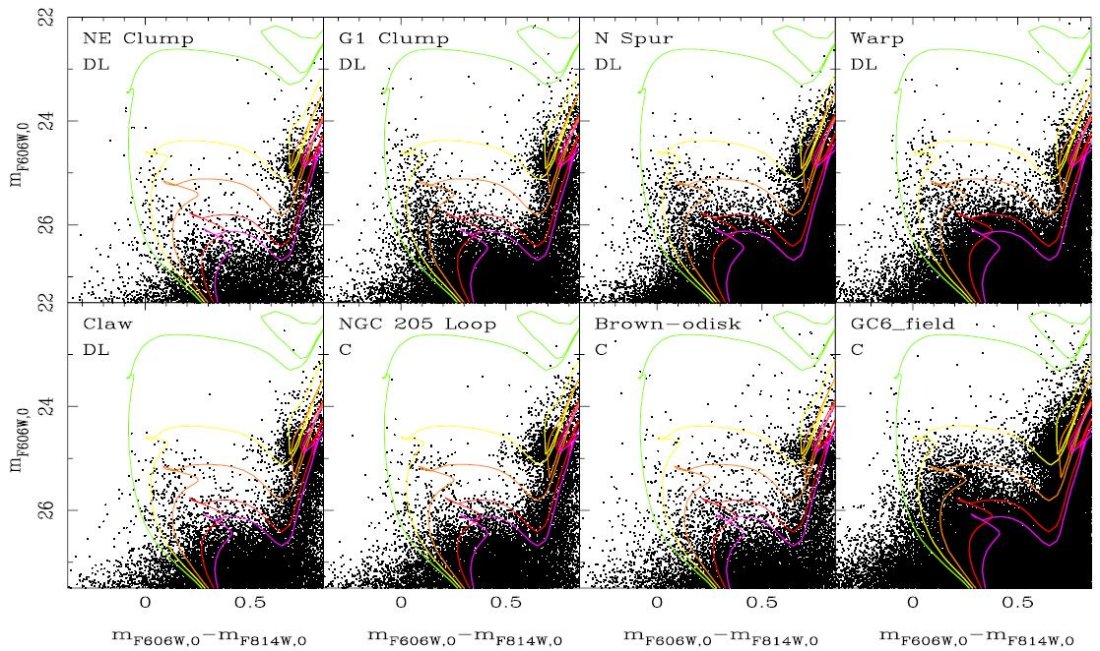HST/ACS を M31 11.5 kpc ≤ Rproj ≤ 45 kpc 14 箇所で
サーベイした。点の多くは INT/WFC 画像サーベイで見つかった連なる副構造を
サンプルしている。他の点は円盤上より広がった箇所を撮像した。星種族を
比較した結果幾つかの明瞭な傾向が明らかになった。
色等級図はレッドクランプの3等下まで達しているが、それらは二つのグループ
に分けられる。一つはジャイアントストリームに似ていて、レッドクランプが
青い側に slant していて、水平枝が発達している。若い種族の徴候はない。
このグループは「ストリーム的」フィールドと名付けられた。
もう一つはレッドクランプが真ん丸で光度巾も大きく、明瞭な水平枝を持たない。
最近 (∼ 0.25 - 2 Gyr) の星形成の証拠がある。このグループは「円盤的」領域と
名付けた。
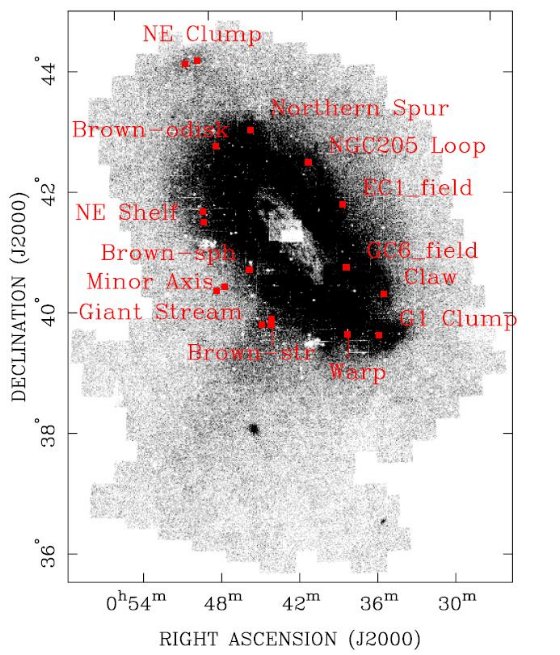
図1.INT/WFC サーベイ(Irwin et al 2005) による RGB 星分布図(95kpc×125kpc) 上に、HST/ACS 観測点(赤 0.8kpc×0.8kpc)をプロットした。
「ストリーム的」フィールドの空間及び視線速度分布を最近のジャイアントストリーム
母天体軌道モデルと比較した。両者はきれいに一致した。「ストリーム的」フィールド
は内側ハローの色々な場所を横切っており、この事件が原因で高い汚染が起きている
ことを実証した。
円盤的物質は M31 の円盤状構造の中にあり、 Rproj
∼ 44 kpc まで確認された。それらのフィールド間で種族が一様であること、
そこに若い種族が含まれていること、別のところで報告されたように強い回転を
示す事などは、この構造が現在ある薄い円盤が加熱され、引きはがされたものである
というシナリオに良く合う。この現象はおそらくジャイアントストリーム母天体の
衝撃によるものであろう。
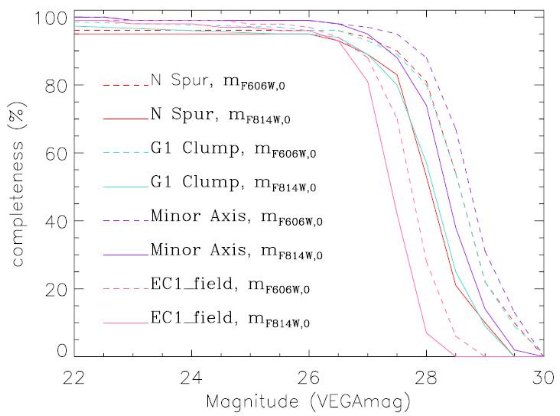
図2.混み具合による測光完全度の変化。