星のプロファイルをガウシアンと仮定し、アパーチャーによってTotal Fluxを
どのぐらいの割合でとれるかを計算してみる。
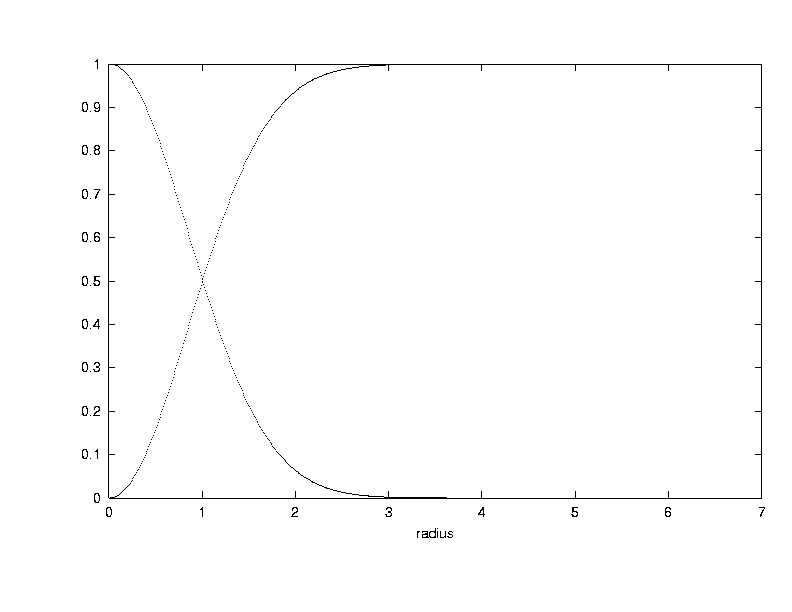
この図では、radius=1で星のプロファイルがピークの半分になるように スケーリングしている。また、星のピークとTotal Fluxを1で規格化している。 図を見ると、上下対称になっていて、星のプロファイルがおちた所でアパーチャーを とるとほぼすべてのフラックスをカウントしていることになる。
次に、スカイの測定誤差の影響を調べるために、スカイの誤差が星のピークに対して
0.1、0.01、0.001上下しているときのアパーチャーによるTotal Fluxの値が
どうなるかを計算した。これはあるスカイの誤差に対して星のピークがその
10倍、100倍、1000倍であることにも相当する。
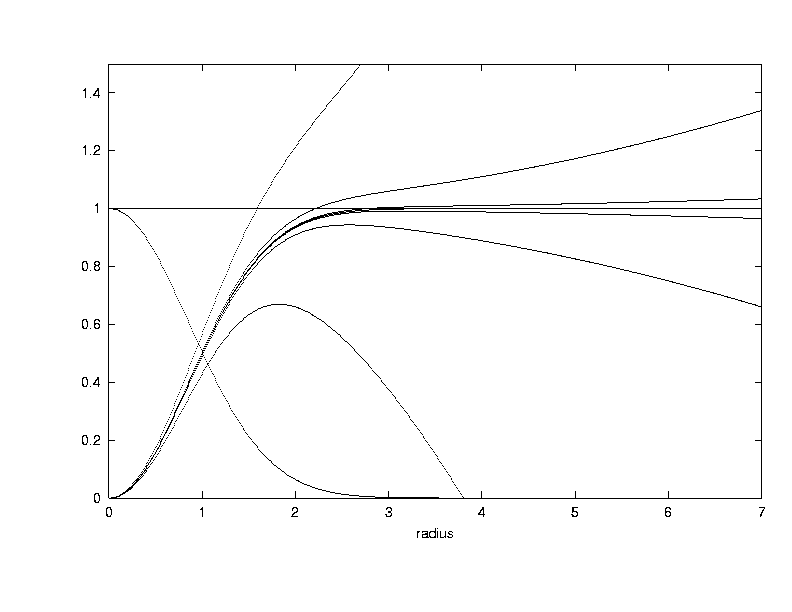
図をみると、スカイの測定誤差が大きくなるにつれてフラックスの値が大きく
ずれている。また、アパーチャーを大きくとるにつれてフラックスが真の値から
大きくずれることになる。この誤差を小さくするには、求める等級の精度にもよるが、
星のプロファイルがおちたぎりぎりの所でアパーチャーをとるのが良いと思われる。
また、星のプロファイルは、radius=2で0.06、radius=3で0.002、radius=4で1.5*10
-4、radius=5で3.1*10-8であり、アパーチャーをそれほど
大きくとらなくてもTotal Fluxを十分にとれることになり、また、
もとめるスカイの精度にも依るが、スカイをそれほど遠い所でとらなくても、
星のプロファイルのすそ野の影響は無視できるといえる。
次に、実際のデータについてアパーチャーやスカイを変えて測光をし、 結果を検討してみる。01/1/12に撮った絵のうちの1枚(onfocus)について、 数個の星を選び、3種類のパラメータで測光を試みた。1つは aperture=5(pixel)、annulus(ドーナツの内側の半径)=5、dannulus(ドーナツの幅)=5、 2つめはaperture=5、annulus=10、dannulus=10、3つめは aperture=10、annulus=10、dannulus=10とした。その結果のうちある1つの星について 整理すると
| Case1 | Case2 | Case3 | |
| Sky | 4112 | 4074 | 4074 |
| Flux | 164233 | 167215 | 178951 |
| mag | 11.96 | 11.94 | 11.87 |
の様になる。星のプロファイルをみると、図1、2のradius=1が1.5pixelぐらいに対応
していて、5pixelはradius=3.3ぐらいである。先の計算の結果から見るとradius=3
でTtal Fluxの99.8%を含有できるはずであるが、Case2のFluxはCase3のFluxの
93%しかない。これがスカイの測定誤差であるなら、Case3のFluxはCase2の
Fluxに対して、色々な星ではランダムに上下に出るはずであるが、他の星について
見ても一様にCase3のFluxがCase2のFluxより大きいので、別の原因があると思われる。
スカイをみると、Case1よりCase2、Case3の方が下がっていて、他の星でも同様なので、
星のすそ野がモデルより広がっているかもしれない。
01/1/12に撮った絵のうちofffocusの絵についても同様の測光をしたので
示しておくと、Case1はaperture=10、annulus=10、dannulus=10、
Case2はaperture=15、annulus=20、dannulus=10、Case3は
aperture=15、annulus=15、dannulus=10とし,先の星と同じ星について
| Case1 | Case2 | Case3 | |
| Sky | 4546 | 40529 | 4532 |
| Flux | 160772 | 185522 | 183349 |
| mag | 11.98 | 11.83 | 11.84 |
となる。ここでもアパーチャーを広げるとより多くのFluxを拾う傾向が測光した全ての
星に見られた。
アパーチャーを連続的に変化させてFluxを調べるような試みが必要と思われる。