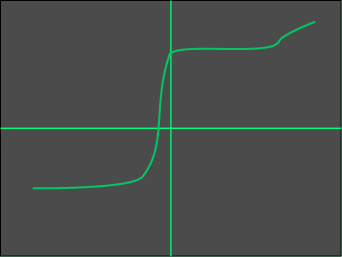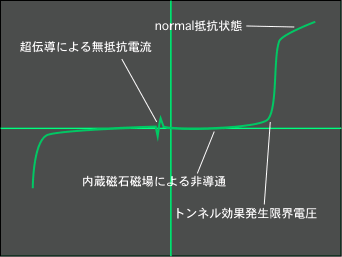VST1 SISミキサーの電流-電圧特性
2001/11/14 半田利弘
接続/測定の仕方はここ
正常状態(電波信号入力なし)
- 素子が4.2K以下に下がっているとトンネル効果発生限界電圧は2.5mV(モニタ端子出力で250mV)以上である。
- 素子のnormal抵抗は12.5Ω(モニタ端子電圧比でV:I=1:8)程度
正常に動作している場合、典型的なI-V特性は下図のようになる。
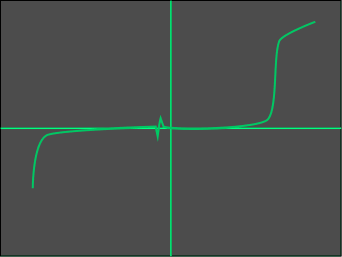 曲線の解説はここ
曲線の解説はここ
正常状態(電波信号入力あり)
- 信号が入力されるとステップが生じる。
- 信号が十分が強いとトンネル効果発生限界電圧での大きなステップが目立たなくなる。
正常に動作している場合、典型的なI-V特性は下図のようになる。

異常事態
- twin junctionで2素子が並列になっているので、片方がopenに
なると、normal抵抗値が2倍程度になる。
→
十分な性能は出ないので素子を交換する必要がある。
- twin junctionで2素子が並列になっているので、片方がshortすると
超伝導電流が流れっぱなしになる。
(ジョセフソン素子化?)
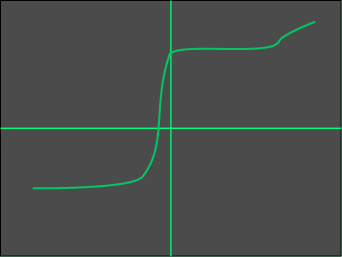
→
使い物にならないので素子を交換する必要がある。
- 冷え方が不十分だとトンネル効果発生限界電圧が下がってくる。
→
デュワ内部で素子が十分に4Kステージと熱接触していないことが考えられる。
- 内蔵の永久磁石が消磁してしまうと、ほとんど電圧0mVで
超伝導電流が流れ、I-V特性はヒステリシスを示すようになる。
(ジョセフソン素子化?)
→
分解して磁石を交換する。
特性曲線の説明
SIS素子の電流-電圧特性を調べると、
電波信号を入力しなくても基本動作が確認できる。
正常な素子の超伝導時の特性は以下のようになる。
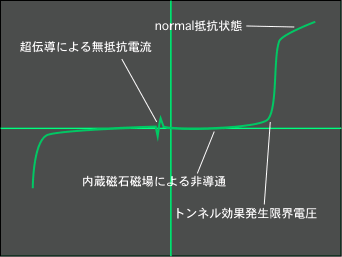
- 超伝導による無抵抗電流は、原理的に電圧0Vで発生する。
それからのずれは表示か直流雑音によると考えるべき
- normal抵抗値は、その状態でのI-Vの傾きで測るべきだが、この
直線はほぼ原点を通るので、絶対値の比で求めてもよい。
測定方法
I-V曲線の書き方には、以下の3つの方法がある。
- ミキサーバイアス電源をsweepモードにして、電流・電圧を
オシロスコープのXYに入力し、線として図示する
- ミキサーバイアス電源の固定電圧を変化させ、電流・電圧を
オシロスコープのXYに入力して、スポットの移動をみる
- ミキサーバイアス電源の固定電圧を変化させ、電流値・電圧値を
メータで読んで記録して図示する
以下では、sweepの場合を示す。
- BIAS BOXを商用電源(AC100V)につなぐ。
- MIXER BIASをBIAS BOXのMIXERというところにつなぐ。
- オシロスコープの
- X(縦軸)をBIAS BOXの電圧の端子(0.1V/mVとある方。)につなぐ。
- Y(横軸)をBIAS BOXの電流の端子(0.01V/μAとある方。)につなぐ。
- BIAS BOXのMODEをSWEEP MODEにする。
- MIXER BIASのPROTECTをはずす(上から下へ)。
- BIAS BOXのSafe→Operate、Protect→Operateとする。
- BIAS BOXのAMPLITUDEを適度に上げていく。
- オシロスコープのスケール,オフセットをずらして、I-V曲線の全体像を把握。
- BIAS BOXをFIXED BIAS MODEにする。
- トリプラーとローカルを導波管でつなぐ。
- ガンの電源をつなぐ。
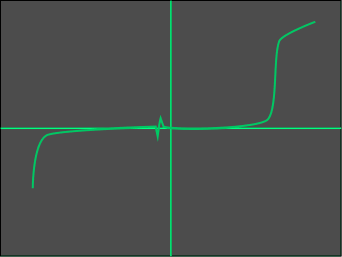 曲線の解説はここ
曲線の解説はここ
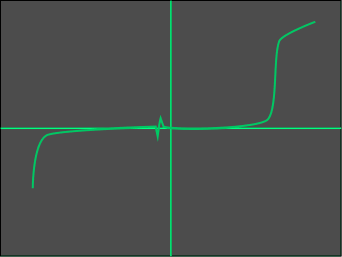 曲線の解説はここ
曲線の解説はここ