chimney, hbleft, hbright, nro45m, signのどれかに向ける。
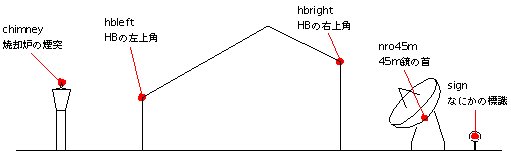
- opintやonoffで星や標準天体がちゃんと見えることを確認する。
- その位置からAzを2.5n[degree] (n=..., -1, 0, 1, ...)振って対象物を探し(Azエンコーダの読みは約2.5度単位で狂う)、 エンコーダの読みと実際のアンテナの向きのずれを測る。
- 測ったずれの量に基づいて、「実際のアンテナの向き」が180度になるように moveを使ってアンテナを動かす。
- 98にてantinitコマンドを実行し、そのままリターンを押してAzエンコーダをリセットする。 (注意:コマンド実行時に動作が和文表示されるが、 現状では、Azについては、そこに示された手順ではうまくいかないことが多いので、 このページに示したやり方で実行すること。)
- s (return)でElエンコーダのリセット操作をスキップする。
- chimney, hbleft, hbright, nro45m, sign を使ったポインティング確認の手順↑に戻る。